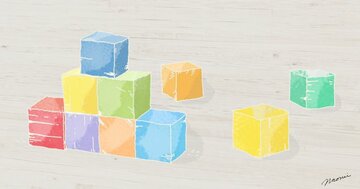対話によって得られる気づきが「思い込み」を減らす
今井さんが神戸大学で学び始める少し前、今井さんのクリニックでは、知的障がいのある村田さん(仮名)が働き始めていた。「村田さんは対人関係が苦手で、掃除しかできない人」とハローワークから伝えられていた。そこで、今井さんは、他のスタッフと接点の少ない夕方だけ、短時間の清掃業務を村田さんに任せることにした。しかし、働き始めた村田さんが、他のスタッフから孤立してしまっている状況を目にした今井さんは「このままではいけない」と感じるようになっていった。
そうした悩みを抱えていた今井さんは、神戸大学で学び始めて出会ったKUPI(Kobe University Program for Inclusion)の取り組みから大きな刺激を受けたという。KUPIは、神戸大学で実施している知的障がい者に大学教育を開く「学ぶ楽しみ発見プログラム」という取り組みである(*)。
* 「HRオンライン」 “学び”での、「自分を成長させたい」思いと、「学習者に寄り沿う」大切さ 参照
KUPIは、知的障がいのある学習者中心の授業を17時から20時まで展開するが、知的障がいのある学習者が帰っていった後、知的障がい者の学びを支援する役割を負った学生たちが集まって、ミーティングを行う。
このミーティングでは、それぞれの参加者が知的障がいのある学習者の学びをどう捉えているかということや、支援がうまくいかない悩みなどが語られる。そうした語り合いによって、参加者が囚われていた「思い込み」に気づくことがある。
例えば、SDGsをテーマに授業を展開していたとき、ペアとなった学習者が、SDGsに関心が向かないようで、「どう支援をしたらよいか困っている」と発言した学生がいた。この学生は、SDGsの17の目標のどれにも関心が向かない学習者に対して、いずれかの目標に食いついてもらうための働きかけの方法で悩んでいた。その学習者は、パワーポイントでプレゼンテーション資料を作成することには強い関心を示すものの、与えられた学習テーマには気持ちが向かないようだった。悩む学生に応答して、ミーティングの参加者たちがさまざまな意見を出し合った。
私たちは、「学びがどのように進んでいくのか」というイメージをもっている。学校の授業での経験から生まれたイメージであることもあるし、自分が独学で学んだ経験から生まれたイメージであることもある。しかし、私たちが無意識にもっている学びのイメージは、知的障がいのある学習者の学びを捉えるときに、ハードルになることもある。学びの進め方は人それぞれであってよいのだということに気づくとき、学生たちは、知的障がいのある学習者の学びに寄り添うことのおもしろさを発見する。
別の学習者は、SDGsの目標に新たに「恋すること」というオリジナルの目標を掲げ、自分の恋愛経験をとうとうと語った。そうした学びを「間違えている」と思ったり、「無意味だ」と感じたりしていたのでは、知的障がいのある学習者の豊かな学びを引き出していくことは難しい。「間違えている」「無意味だ」と感じてしまうのは、私たちが無意識のうちに「正しい」学びのイメージを持ってしまっているからである。その「思い込み」に気づくことで、私たちは、知的障がいのある学習者の意味世界を了解できるようになっていく。
KUPIに参加している知的障がい者たちの様子を見た今井さんは、村田さんにも、「もっと可能性があるのではないか?」と考えるようになっていった。村田さんは「対人関係が苦手」という理由で、他のスタッフと接点の少ない夕方にだけ働いてもらっていたが、それでは村田さんの成長の機会も、また、他のスタッフの成長の機会も奪ってしまうのではないか?と今井さんは考えた。
そこでまず、今井さんは、村田さんの勤務時間を朝からの勤務に切り替え、他の従業員との接点ができるようにした。すると、他のスタッフたちは村田さんを仲間として歓迎し、村田さんが働きやすい職場づくりの工夫をし始めた。例えば、村田さんが漢字の読み書きが苦手だということがわかると、スタッフたちは率先して、クリニックのマニュアルや備品などにふりがなを貼ってまわった。こうして、スタッフによるナチュラル・サポートがクリニックに定着していったのである。
「村田さんは対人関係が苦手だ」という情報が、危うく、新しい「思い込み」を生み出すところだった。KUPIでの経験が、村田さんの対人関係の苦手さが、周囲の人たちの考えや行動によって変わり得ることに気づくきっかけにもなったと、今井さんは言う。