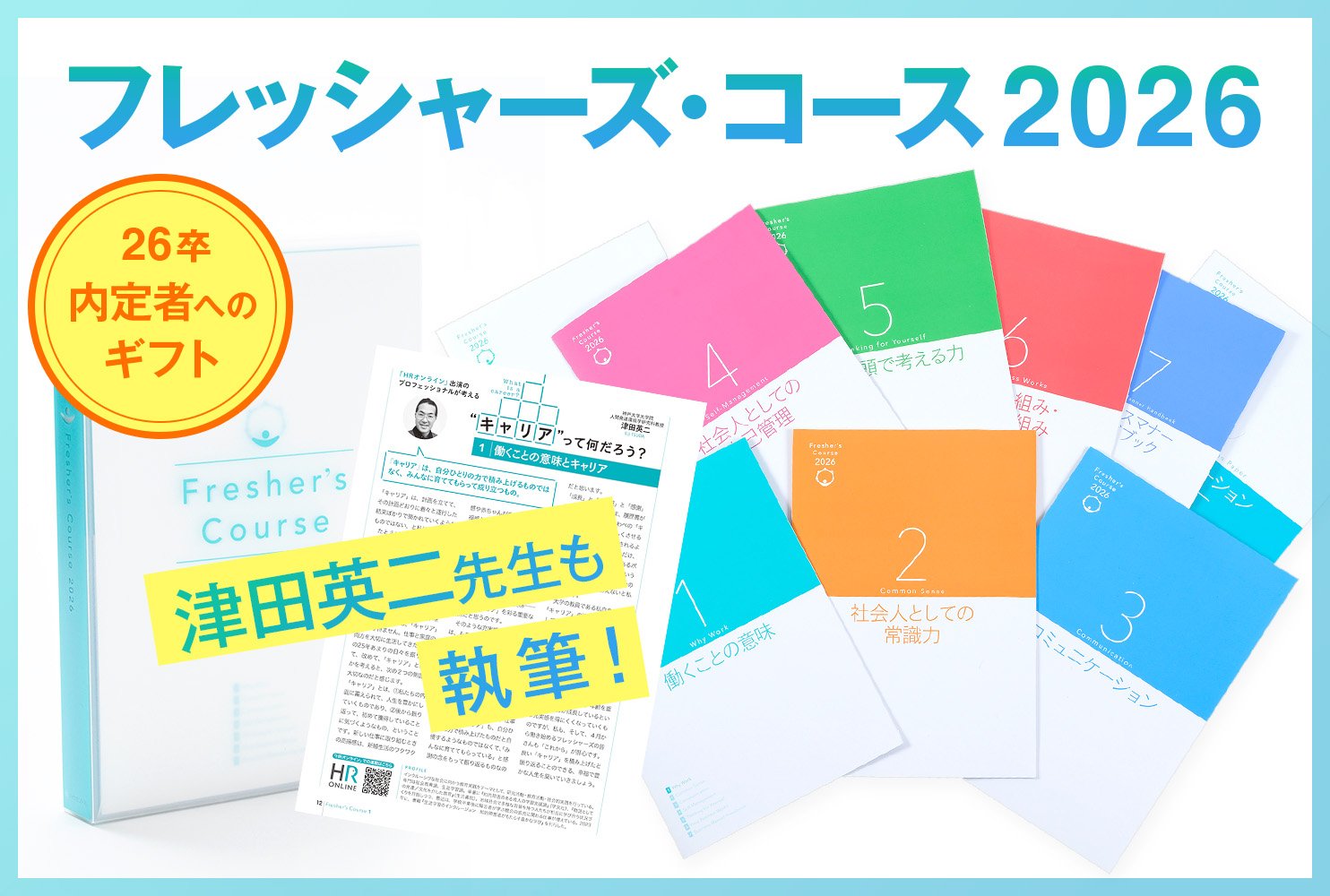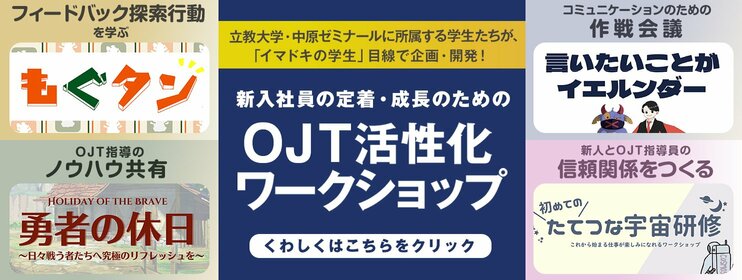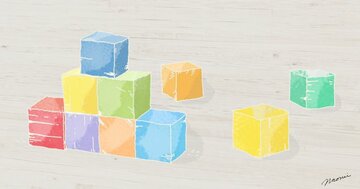「思い込み」に気づき、それを不断に修正していく
「思い込み」は誰にでもある。唱歌「ふるさと」の冒頭、「うさぎ追いし」を「うさぎ美味しい」だと思い込んで子ども時代を過ごした人は、私だけではないはずだ。「思い込み」は笑いの種になるほど、他愛もないこともある。しかし、そうとばかり言えないこともある。
「思い込み」が自分自身の、あるいは他の誰かの不利益をもたらしていることもある。学校の音楽の授業でリコーダーをうまく吹くことができず、自分は「音楽が苦手だ」と思っている人は少なくないようだ。経験に基づく「思い込み」が、音楽を楽しむ機会を制約しているのだとしたら、その人は損をしている。そういった「思い込み」はすぐにでも修正したほうがいい。しかし、経験に根ざしている「思い込み」は、本人からしてみると根拠のある「思い込み」であり、修正が容易でない。
また、かつては「当たり前」だったり、問題にならなかったりしていたことが、別の時間や場所ではうまく当てはまらないということもある。例えば、「街で障がい者を見かけることはない」のが「当たり前」だった時代もあった。その時代には、「障がい者は価値のある仕事ができない」と考えるのが「当たり前」だった。しかし、障がい者の社会参加が「当たり前」になってきた今日、かつての「当たり前」は「思い込み」に変わり、その「思い込み」が、障がい者の社会参加を妨げるようになっている。こうした「思い込み」も、すぐにでも修正したほうがいいのだが、いったん染みついた「当たり前」を更新するのは容易でない。
このように考えると、「思い込み」に気づき、新しい認識に書き換えていくことは、私たちの成長にとって欠かせない学びである。このような学びを、「変容的学習」と呼ぶことがある。通常、私たちは、高みを目指して一歩一歩階段を昇っていくようなイメージで学びを捉えている。このような学びを「形成的学習」と呼んでいる。「変容的学習」は、それとは異なる学びの形で、私たちの成長の奥行きを形作っている。
人はたくさんの他者と出会い、いろいろなできごとを経験することで、うまくいかないことを処理する必要や、考え方を変える必要に迫られる。つまり、経験を積めば積むほど、人は「変容的学習」を迫られ、「思い込み」を修正しながら成長していくのだ。
今井さんにも、会社から与えられたノルマを達成することに命を懸けるようなサラリーマン時代があった。自分の力を生かすことができずに離職していく仲間に、冷たい視線を投げかけたこともあった。もっと高いノルマを達成できるようになりたいという一心で、自分の身体に鞭を打って生きていたのだという。しかし同時に、「自分や仲間たちを傷つけてまでノルマを達成することがそれほど大切なことなのだろうか?」という疑念も、徐々に頭をもたげていった。組織の発展のために自らの生活を犠牲にして働くことが、「社会人として当たり前」だという考えは、間違いとは言えない状況もある。しかし、そのような精神を過剰に身に付けてしまい、自分自身にも、そして、他者に対しても、常に自己犠牲を求めて働くように求め続けていると、知らず知らずのうちに誰かを傷つけることになってしまう。その傷が拡大していくと、「組織のための自己犠牲が正義」だとする考え方は、「思い込み」の側面をもつようになる。
今井さんが自分の働き方に対する考え方に向き合うようになったきっかけは、「組織は何のためにあるのか? 営業は何のためにするのか?」という問いとの出合いだったという。この問いを突きつめていくことで、今井さんは、「組織のために人が働く」という考え方が、「思い込み」だったのではないかと考えるようになっていった。「人は組織のために働くのだから、無理をしてでも、なるべく高い成果を挙げるのは当たり前だ」という考えに支配されていたために、「部下や自分自身を傷つけていたのではないか?」という思いに至ったのだ。こうして、今井さんは、「組織のために人が働く」という認識から、「人のために組織がある」という認識へと変わっていく「変容的学習」を経験した。
今井さんは、「思い込み」を修正する「変容的学習」を経て、「人を大切にする組織」の実現を志すに至った。そして今度は、今井さんが職場に、たくさんの「思い込み」への気づき、そして、「変容的学習」をもたらす役割を担うようになった。その結果として生まれた成果のひとつが、職場のなかで自然と生まれていったナチュラル・サポートである。障がい者雇用の成功に欠かすことのできないナチュラル・サポートは、職場全体で「思い込み」に気づき、それを修正していく努力によって生まれた。
「思い込み」に気づき、それを不断に修正することのできる組織づくりの要点を、今井さんの語りから拾ってみると、次のようなことが大切だとわかる。
まず、自分の考えを正直に話すことのできる条件をつくること、そして、その話した内容に「思い込み」が含まれていることに自ら気づくような対話の場をつくること、さらに、新しい考えに勇気をもって踏み出すことのできる環境をつくること。
企業も大学も含め、あらゆる組織で、このような対話的環境と、その前提にある安心して自分を表現できる環境をつくっていくことが、人と組織の成長が求められている現在、重要性を増している。
挿画/ソノダナオミ