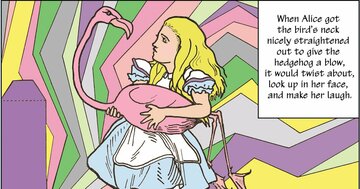名作映画『小さな恋のメロディ』に
隠されたイディオム
〈クラッパム行きのバスの乗客〉the man on the Clapham omnibusは「市井の人」「平均的な人」を意味する。19世紀末に裁判官チャールズ・ボウエン男爵が裁判で用いた表現とされる。
クラッパムはロンドン中心部から南に5キロの地区で、18世紀に富裕層向けの高級住宅地として開発されたが、この成句が成立した頃にはごく平均的な生活水準の人々が住む郊外住宅地であった。20世紀初頭には夏目漱石もここに住んでいたから、日々クラッパム行きのバス(当時は乗合馬車)に乗っていたに違いない――彼が当時のロンドンで「平均的な人」だったかどうかは疑問だが。
クラッパムという地名は「丘の上の農地」に由来する。「丘」を意味する古英語cloppにham(homeの古形。「囲い地」すなわち「農地」の意)が合わさったものである。クラッパムには「平均的な人々が住むところ」の他に「乗換駅」というイメージもある。ヴィクトリアからイングランド南部に向かう幹線と、ウォータールーからイングランド南西部に向かう幹線が交わるのがクラッパム・ジャンクション駅で、17番線まである巨大な乗換駅であり、それだけの線路が(立体交差ではなく)平面で絡み合い交わっている。
長谷川如是閑(編集部注/日本のジャーナリスト、文明批評家、小説家)はエッセイ『倫敦!倫敦?』でこの「猛烈な乗換駅」の様子を「八方から落ち合う近郊の路線が、饂飩屋が転んだように縺れ合っている」と描写する。漱石も『永日小品』所収の「霧」で霧の夜のこの駅を叙述している。ロンドン名物の濃霧の夜には文字通り何も見えないので、線路に爆竹を仕掛けて列車の接近を知らせるのだが、何しろ路線が多く深夜まで頻繁に電車が通るため、1分に一度は爆竹が鳴り響いて眠れなかったらしい。
また、英国では忘れられた作品だが日本では大ヒットした名作映画『小さな恋のメロディ』(1971)の最後の場面で、主人公のダニエルとメロディがトロッコで「駆け落ち」する際、悪友のオーンショーが「忘れるなよ、クラッパム・ジャンクションで乗り換えだ(And don’t forget to change at Clapham Junction!)」と叫んでいるが、この駅の事情を知っていればこれがとても気の利いた台詞であることがわかる。