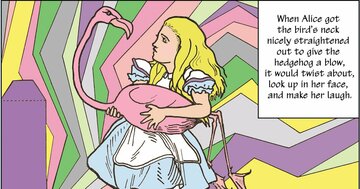なお、〈オムニバス〉とは「すべての人々のための」という意味のラテン語であり、1820年代末に「乗合馬車」の意味でフランス語から英語に借用された。20世紀になると乗合馬車はエンジンの付いた大型自動車になり、〈オムニバス〉は前半が略されて〈バス〉になった。今は英語でも日本語でもバスのことをオムニバスとは言わないが、この慣用句ではあくまでもオムニバスである。
『アリス』の人気キャラも
イディオムから名付けられた!?
『不思議の国のアリス』でお馴染みのイディオム〈チェシャー猫のようにニヤニヤ笑う〉grin like a Cheshire catは、『オクスフォード慣用句辞典』では由来不詳とされている。
これはおそらく18世紀末か19世紀初頭に成立したイディオムで、ルイス・キャロルが『アリス』を書いた当時はよく使われていたらしい。チェシャー猫というのは実在する猫の種ではなく、このイディオムを基にキャロルが創作した架空の猫である。ついでながら、キャロルはオクスフォードの人という印象が強いが、生まれてから11歳まで育ったのはチェシャー州のダーズベリーという小さな村である。
米国のキャロル研究家マーティン・ガードナーは、この慣用句の由来として、チェシャー州のある看板画家が描いた宿屋の看板のライオンが「笑っている猫」にしか見えなかったことと、昔からチーズ製造が盛んなチェシャー州のチーズが笑う猫のような形だったことの2説を紹介している。
ついでながら、チェシャー猫と並ぶ『不思議の国のアリス』の人気キャラクター「気違い帽子屋(the Mad Hatter)」と「三月野兎(the March Hare)」も、イディオムから逆生成されている。
いずれも「気が狂っている」ことを意味するmad as a hatterとmad as a March hareという、やはりキャロルの時代によく用いられた成句から着想されたものである(前者は『不思議の国のアリス』の数年前に出版されたトマス・ヒューズの『トム・ブラウンの学校生活』第2部第3章冒頭にも用例が見られる)。