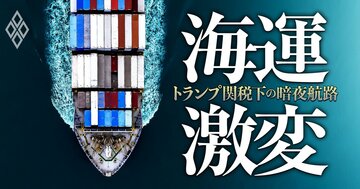まずは目の前の仕事を
しっかりやり遂げてもらう
部下には、目の前で起こっている、やらなければいけないことにまずは注力してもらうことを目指します。
次回も使える考え方や、似たような状況への対処法など、言いたいことは沢山あると思います。しかし、我慢しましょう。
そして、まずは今回の仕事をしっかりやり遂げてもらった上で、その次の機会に「別の具体例を一つだけ」提示します。
ただ、その際に、前回の具体例の話、つまり、実際の作業内容や施策の中身などを思い出させるような話をするのです。
これを何度か繰り返していくと、相手の中に「具体例」が蓄積されていきます。そうした具体例が積み上がってからはじめて「抽象概念」の話を行います。
先ほど述べた理想的な情報の伝え方は、「演繹的に理解を促進する」というお話。抽象概念を伝えた上で、それにひもづいた具体的な情報を渡すというアプローチです。
今回、この記事でお勧めしているのはその逆で、「帰納的な理解の醸成」です。
具体的なことを列挙した上で、その共通項を探しに行くというやり方です。物事を考える際には、帰納的に考えることが実用的ですし、非常に有用です。
私は、多くの人の頭の中は「帰納的に組み立てる」ことに向いているのだと思います。
従って、「勘の悪い部下」の学習を促進する際には、時間をかけて「具体例」を積み上げていく方が良いと思うのです。
情報の引き算を徹底する
「これだけは覚えて帰ってね」
 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
繰り返しになりますが、このテクニックにおいて、一番大事なのは、脱線しないことです。
あれこれ言いたくなりますが、それを我慢して、情報の引き算を徹底的に行います。言いたいことが五つあっても、一つだけに絞り込みます。
相手が「一つだけでも」持って帰る方が良いのです。