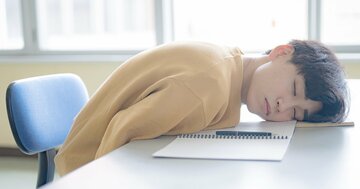写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
東京大学理科3類(医学部)に合格した2人の受験生がいる。東大受験の専門塾「鉄緑会」の出身である2人が、共通してやっていた勉強法とは?※本稿は、東大カルペ・ディエム著編、西岡壱誠監修、じゅそうけん監修『東大理3 合格の秘訣 Vol.40 2025』(笠間書院)の一部を抜粋・編集したものです。
上田祐輝さん(東大寺学園卒)の
合格に足りない50点を埋めたもの
理3を目指すうえで後悔はできないと思い、高1の12月に、鉄緑会に入会しました。当面は、約1年後、高2の2月にある東大同日模試で理1の合格最低点を上回ることを目標に勉強していました。
予想していた通り鉄緑会の授業はハイレベルで、毎週の課題をこなすだけで大変でしたが、熱意溢れる先生と優秀な同級生に恵まれ、振り返ってみると楽しく通っていたように思います。
東進の高2東大本番レベル模試を高1の途中から受験し、理3の判定はD→D→C→B→Aと、右肩上がりでした。
数学では、見開きのノートの左に問題文を貼り、右側には正答を書き、右のページを隠して問題文だけを見ては、考えられるアプローチや問題のポイントとなりそうな部分を問題文の下に書き出してみて、その解法を選ぶ理由や類似した問題をじっくり検討していました。
理科では、難問とされる問題を1問解くたびに、どこが難しい点だったのかを、内容面と時間面の両方から検討して、書き出していました。
これらをストックしておき、ある程度の物理現象や化学の反応操作における「難しい問題」のパターンを頭の中に蓄積していきました。
東大の理科は時間が本当に厳しいので、問題の引き出しを多くもっていて、素早く引き出せるようにすることは大きな強みになると思います。