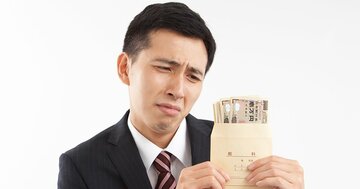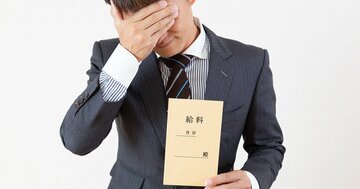アベノミクスを推進した安倍晋三元首相 Photo:Pool/gettyimages
アベノミクスを推進した安倍晋三元首相 Photo:Pool/gettyimages
食料品をはじめあらゆる物価が値上がりするインフレ状況に直面し、我々はいま円安の弊害を嫌というほど実感させられている。だが、ほんの数年前までは「円安批判」がタブー視されるほど、だれもがみな円安を歓迎していた事実を忘れてはならない。たとえ賃金がアップしても物価上昇に追いつかないこの苦境の背景に、人気エコノミスト2人が迫る。※本稿は、河野龍太郎、唐鎌大輔『世界経済の死角』(幻冬舎)の一部を抜粋・編集したものです。
輸出大国の日本にとって
円安は絶対の正義だった
唐鎌大輔(以下、唐鎌):円安と実質賃金の関係について、もう少し周知されるべきだと日々感じています。
実質賃金は3つの要素(労働生産性・労働分配率・交易条件)によって決まります。この中で言えば、圧倒的に交易条件の悪化(交易損失)が実質賃金の足かせになってきたことが分析上、明らかになっています。
交易条件は「輸出物価指数÷輸入物価指数」で算出されます。この悪化をもたらしてきた輸入物価の上昇は、原油に代表される資源価格の上昇に起因している部分が非常に大きかったと考えられます。
しかし、長年にわたり円安を絶対的に正しいものとして崇めてきた日本社会の雰囲気も、大いに関係があると私は考えています。
円安にすれば当然、海外から輸入する商品の値段は上がりますから、交易条件は悪化します。とりわけ2022年以降は資源価格上昇と円安が併存したため、実質賃金という意味では最悪の時期でした。
2022年以降は円安の振れ幅が極めて大きかったため「円安による交易条件悪化。それに伴う実質賃金の低下」という関係は相当程度、世の中に認知された印象があります。
しかし、歴史的に続いた円相場の意図的な低め誘導が交易条件の改善を阻害し、実質賃金の低迷を招いてきた側面は、それほど注目されてこなかった気がします。