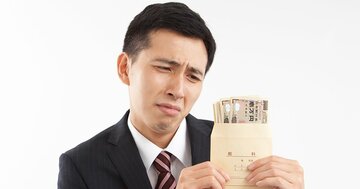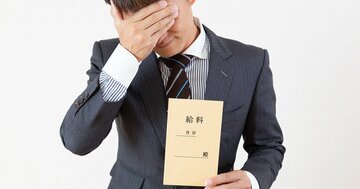コロナ禍が明けた後、本来「リベンジ消費(巣ごもり期間中にたまったお金を一気に使う動き)」が訪れるはずが、それがやってこなかったのは、円安インフレで家計の実質所得が大きく目減りしたためです。
代わりに日本でお金を使ったのは、円安で大きなメリットを受けた外国人でした。
岸田首相が支持率を大きく落としたのも、自民党の「政治とカネ」の問題だけでなく、実は、円安インフレが相当に影響していたというのは、これまでも見た通りです。
当時、為替レートと政権の支持率は、真逆の動きである“逆相関”を見せていました。円安を支持する人たちは、「輸出企業が業績を伸ばし、設備投資が増え、それが実質賃金の上昇につながるまで金融緩和を続けるべきだ」と主張していました。
しかし、私は2000年代末のリーマンショックによる不況が終息した段階で、この考えが誤りだと確信していました。
なぜなら、2000年代以降、日本企業は景気が回復しても、金融緩和でいくら円安になって業績が改善しても、実質賃金を引き上げようとしないことが、すでに明らかだったからです。
この2000年代の経験を踏まえて、リーマンショックの後に景気回復が始まったときには、「賃金が上がるまで金融緩和を続ける」といった根拠のない経済戦略を取るべきではないと、私はアベノミクスが始まる前から主張してきました。
国債大量買い入れ「黒田バズーカ」は
前任者の時代から用意されていた?
唐鎌:リーマンショックから5年後、世界的にも景気が回復基調になる状況で、日本には異次元緩和がやってきましたよね。
河野:黒田前総裁の前の白川方明総裁のときに、異次元緩和の源流のような「包括緩和」が始まるのですが、私は、こんな拡張性の高い制度を導入すると、最初は自制的に運用していても、民主主義の下で極端な政策を志向する為政者が現れて、とんでもない政策になっちゃう恐れがあるから適切ではないと、当時の日銀首脳に提言していた記憶があります。