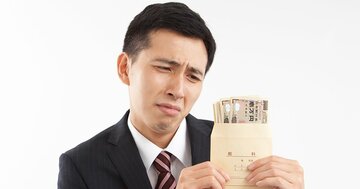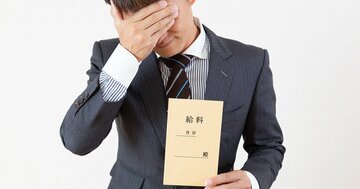円安の弊害を指摘することすら
許されない空気が蔓延していた
河野龍太郎(以下、河野):円安になっても、輸入価格だけでなく輸出価格も上がれば、交易条件は変わらないはずなので、為替レートと交易条件の関係については多少意見が分かれますが、円安と実質賃金の話題は、今日の対談の重要なポイントになりそうですね。
唐鎌:はい。2022年には「悪い円安」というフレーズが新語・流行語大賞の候補に入りました。そのフレーズの妥当性はさておき、それだけ円安の弊害を認知する人が多くなったということでしょう。
過去を振り返れば、円安の弊害に言及するだけで「水を差すな」と言わんばかりに、直情的な批判を受けることも珍しくありませんでした。今もそうした向きは多少残っているように感じますが、「円安のほうが日本経済にとってプラス」と強弁する論陣は少数派になってきたと思います。
しかし、どんな政策にも功罪があるのは当然のことですし、河野さんも私も、その両面をできるだけ客観的に捉えようとしてきた姿勢は、ずっと変わっていないと思います。
河野:私も同じスタンスを続けてきましたが、円安に対する世間の見方は大きく変わってきたと感じますね。
唐鎌:円安批判がタブー視されやすい理由は単純だと思います。円安になると大企業・輸出製造業の業績が改善し、株価が上昇します。株価が上がって損をする人はいませんから、円安を肯定する気運が醸成されやすい面はたぶんにあったと考えています。
河野:「輸出企業が利益を上げているのに、金利を上げて円高にすると、せっかくの景気回復に水を差すことになる」というわけですね。
一方で、円安がすべての家計にとってよい影響を与えるわけではありません。むしろ、円安で輸入品の価格が上がり、家計の実質購買力は抑制されます。
しかし、2021年頃まで、輸出企業の儲けにばかり注目が向かって、日本では家計などへの影響について十分な注意が払われていませんでした。