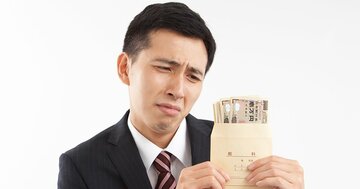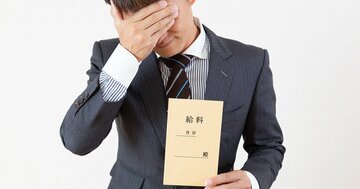金融緩和で円安を狙った
アベノミクスの功罪
唐鎌:2022年以降の円安の理由は1つではないと思いますが、主要国の中央銀行が大幅な利上げに走る中、必死にマイナス金利を堅持しようとした姿勢が影響していたことは否定できません。
結果、金融緩和に伴う通貨安を通じてインフレ圧力が輸入されるという、教科書通りの展開を日本経済はたどっています。河野さんは、アベノミクス以降の日銀の金融政策をどう評価していますか。
河野:アベノミクスにおける金融緩和は、最初から大失敗だったと私は考えています。というか、アベノミクスが開始される前から、2%のインフレ目標を掲げて中央銀行が大規模な資産購入を行うことに対しては、強く批判してきました。
もちろん、金融緩和がすべて悪いとは思っていません。ただし、「いつ始めて、いつ終えるか」は重要です。私は、1990年代末の銀行危機のときにこそ、異次元緩和級の大規模な金融緩和が必要だったと考えています。
実は2000年代初頭に、円安誘導すべきという本を書きました。タイトルもズバリ『円安再生』(東洋経済新報社、2003年刊)で、1ドル170円への円安誘導を主張しました。私自身、元祖円安リフレ派なわけです(笑)。
今回の異次元緩和は最初から間違っていたと主張してきましたが、間違って始めたのはやむを得なかったとしても、まだ、ましなやめ方というか、ましなやめるタイミングがあったはずです。
2%のインフレ目標を柔軟に解釈していれば、2022年春以降は利上げ開始が可能だったはずだということです。
いくら金融緩和で円安をつづけても
労働者の賃金は上がらない
唐鎌:「いつ始め、いつ終えるか」、その両方で日銀は正しいタイミングを選択できなかった、ということですね。
河野:その通りです。スマホ料金などの特殊要因を除けば、2021年11月以降、消費者物価上昇率はすでに2%に達していました。特殊要因を除かなくても、2022年4月以降は2%を超えています。
2022年から、日銀が利上げを開始していれば、おそらく1ドル150円や160円の円安は避けられたと思いますし、家計が円安インフレによって、これほど大きなダメージを被ることもなかったはずです。