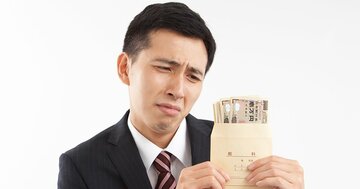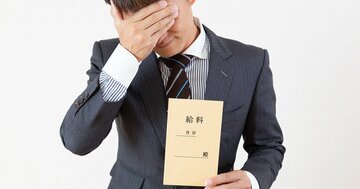日銀内では極限まで長期国債を購入する「プランB」が、白川時代から存在していたのだと思います。それが安倍晋三首相によって黒田東彦氏が総裁に選ばれたときに事務方から提案された――懸念していた通りになったというのが、異次元緩和が始まったときの私の印象です。
本来、景気が回復し、企業業績がよくなれば市場金利が上がり、家計は預金などから利子収入を得られるはずです。また、金利上昇によって、円高になれば輸入品の価格が下がり、生活コストの低下というメリットも期待できます。
しかし、日銀は賃金が上がらないことを理由に、長期間にわたり金利を低く抑え込み、結果的に円安を助長しました。金利を低く抑えたって、賃金が上がらないことはわかっていたはずです。
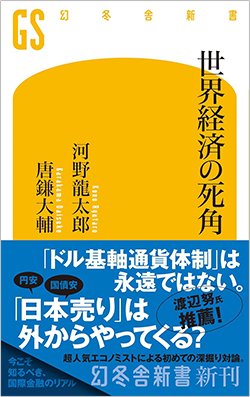 『世界経済の死角』(河野龍太郎、唐鎌大輔、幻冬舎)
『世界経済の死角』(河野龍太郎、唐鎌大輔、幻冬舎)
その後、コロナ禍が終息し、世界中で「リベンジ消費」が活発化しました。2023年春には日本でも同じようにリベンジ消費が現れると期待されていましたが、実際には異次元緩和の継続による円安インフレで輸入物価が急騰し、家計の負担が増え、消費の低迷が続きました。
コロナの巣ごもり期間に積み上がった資金は「強制貯蓄」と呼ばれていて、どこの国もそれがリベンジ消費の原資となりました。しかし、日本だけ、お金を使う前の段階で、物価高によって、膨らんでいた強制貯蓄の実質的な価値がすっかり失われてしまいました。
このように、長年にわたり家計を痛めつけるような政策が続いているのだから、個人消費が低迷を続けるのは当然ですよね。
唐鎌:いざリベンジ消費しようと思ったら、円安インフレで一般物価が押し上げられたため、思ったほどリベンジできなかった……というわけですね。わかりやすい話です。