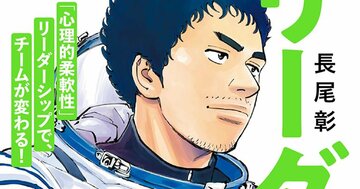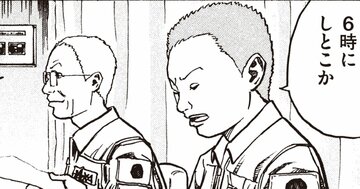それでも、制約という概念を持ち、アンテナを立てておくことは、決して無駄にはなりません。何よりメンバーが制約をポジティブなものとして受け止められるようになるので、やがて、チームに必要な制約とアプローチの手法が見えてくるのではないかなと思います。
制約主導アプローチの事例「個人の制約」
(1)経験年数に応じて、「教わる側」から「教える側」へ
新しいメンバーが入ったら、勤続1年目の人がひとつの業務を教える役目を必ず担うという制度です。たとえ経験が浅くても、「教える立場」になることで、これまで教わっていたことに対する理解が深まります。その結果、「経験値の低さを要因とする自信のなさ」という制約を突破する学習機会になります。
(2)自分の「強み」だけで、チームに貢献する
1日1カ月に1回、自分が得意と思えることだけでチームに貢献する日を設けます。苦手意識が強いせいで、業務への積極的な参加にブレーキがかかっていた人が、自分のリズムで協働を始めるきっかけとなり、能動性や積極性が育まれます。
(3)苦手なことを引き受け合う1日
「自分が苦手なこと」を、あらかじめチーム内で共有し、週に1回、ほかのメンバーにそれを代行してもらいます。「苦手」という個人的な心理的ブロックを共有し合うことで、信頼感と連携意識が高まり、助け合いの精神が自然と育まれます。
制約主導アプローチの事例「環境の制約」
(1)「立ったまま会議」の導入で時間と空間を制約
15分以内の打ち合わせは、立って行うというルールを導入。時間的・身体的な制約を設定することで、集中力と発言の質を高め、連携する力を強化します。
(2)備品の使用を制限する
資料を作成する際に、パソコン(メールを含む)を使用せず、ホワイトボードと紙だけで進めるという制約を設定します。使える道具が限られるので、チーム内で手書きによる情報共有や、対面・口頭での直接的なコミュニケーションが増え、協働の機会が生まれます。
(3)他部署との共有デスク制度毎週1回、他部署の人と共有スペースで作業する日を設けます。同じ部署内のフリーアドレスではなく、あえて別の部署の人たちと空間を共有することで、自然な会話と情報交換が行われ、組織内の「見えない壁」を取り除きます。