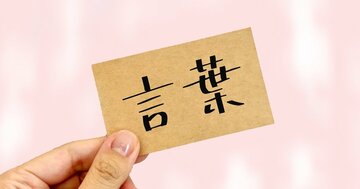だからと言って、人間の創造性もしょせんはAIがやっているパターン認識と変わらないのだと言いたいわけではありません。
重要なのは、創造性そのものを云々するよりも、もっと明確に人間と生成系AIを分かつものがあるということです。
それが知性に裏付けられた意思の有無なのです。
生成系AIは外から「こういうものをつくって」という働きかけがあったときに、それに応じて生成するに過ぎません。コール・アンド・レスポンスのレスポンスが優れているだけで、それは最初のコールがなくては生まれない。
「ニーズに応える」発想では
AI時代に価値を生み出せない
しかし、人間は「こういうものがあったらいいな」「こういうものをつくりたい」という己の想像力や意思に基づいて、自らものを考えたり、生み出したりします。
これこそ、人間の創造性がAIの生成能力と決定的に違うところでしょう。
これは産業の将来性を考えるうえでも、非常に重要なところです。日本の企業や官僚の人たちと話していると、決まって「ニーズ」という言葉が出てくる。
「ニーズに応えるような製品やサービスをつくらなくてはいけない」というわけですね。
しかし、「ニーズに応える」というのは、外からのコールにレスポンスするという課題解決型の発想です。そして、コールにうまくレスポンスすることなら、今では生成系AIがきわめて精度高くできてしまうのです。
必要とされているものをつくるのではなく、自分たちが「こういうものがあったらいいな」と想像して生み出したものを世の中に提案する――これからはますます、ニーズそのものをつくりだすという発想で動かなくては、新しい価値は生み出せないでしょう。
自らのウォントやウィッシュに基づいて何かを世に送り出す。人間がものをつくる意味は、そこにしかなくなっていくと思います。
自分の「ほしい!」を極めると
結果的に売れるものが作れる
私の最初の愛車はホンダのシビックなのですが、あるとき、たまたまシビックのモデルチェンジを設計した方と知り合いになりました。
その方がおっしゃるには、後部の収納スペースの幅が、旧モデルよりも広くなるように設計した、とのこと。なぜかというと、ご自身が釣りを趣味としており、長さのある釣り竿も収納できるようにしたいと思ったからなのだそうです。旧モデルでは竿をコンパクトにしても収納できなかったのだと。