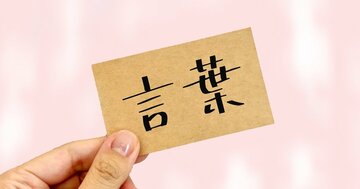この話を聞いて、まさに外のニーズに応える課題解決型ではなく、自分自身の内なるウォント型のものづくりだと思いました。世間に「こういうものがほしい」と言われてつくったわけではなく、自分がそういうものがほしいからつくった。
個人的欲求に応えただけだから世間には受け入れられないと思うかもしれませんが、実は、そういうものこそ売れるのです。
製作者と同じく釣りをする人たちが「釣具が難なく積める。これはいい」と喜ぶだけではありません。収納スペースの奥行きが出たことで、ファミリーが子どものおもちゃをたくさん積み込めるとか、ミュージシャンが楽器などの機材を積み込みやすいとか、人それぞれの内なるニーズが、作り手のウォント型のものづくりに呼び起こされ、満たされるのです。
作り手のウォントが受け手のニーズを喚起する――もっと言えば、作り手と受け手は、そのモノを介して心の対話をしているようなものです。
明文化できない想像力は
AIには真似できない
日本のものづくりの歴史を遡れば、そういう例はたくさんあります。
ソニーのウォークマンなどは文句なしの代表例です。作り手が「家にいるときだけでなく、外出中も音楽を聞けるようになったら……?」と想像してつくった。
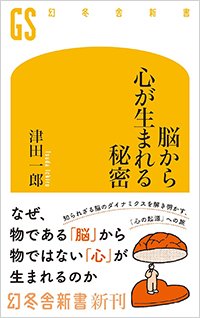 『脳から心が生まれる秘密』(津田一郎、幻冬舎)
『脳から心が生まれる秘密』(津田一郎、幻冬舎)
その時点では世の中にニーズなんてなかったわけですが、出してみたらヒットした。人の思いがこもっているものは、それだけ人に響くものなのです。
ウォントとウィッシュの発生源は想像力です。最初はぼんやりと「こんなふうになったらいいな」というイメージがあり、そこから徐々にほしいものが明確になって、つくりたいものの形が具現化していく。
ニーズは明文化できますが、ウォントやウィッシュを生む想像力はつかみどころがなくて明文化できません。そして明文化できるニーズは知能的なAIにも解決できるけれども、明文化できない想像力は知性のひとつであり、そもそもAIには備わっていない。
そんな想像力に支えられたウォントやウィッシュ型思考、そこから生まれるものづくりは、つまり今のところは人間だけにできることなのです。