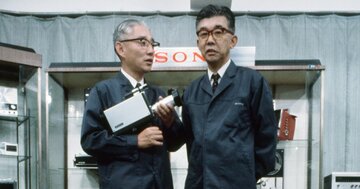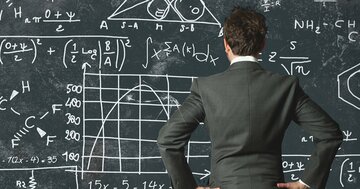そして、それだけの時間や費用をかけても、失敗するケースはどうしてもある。こうした新商品開発の原資を、カイゼンは生み出せる。
カイゼンを進めると
他社と差がつく要因は?
そもそも、他社と全く同じものを他社より安く、もしくは早く作れれば、その分多くの受注と利益を得られるだろう。価格や納期の優位性で勝つためには、カイゼンが欠かせない。
実際、下請け企業に厳しい環境とされる自動車部品製造の世界でも、特別な学歴や技術を持った人材を採用するわけでも、特注品の生産設備を使うわけでもない部品メーカーが、高い利益率を出している事例を取材したことがある。
自動車部品の世界では安定供給のために、特許などが絡んでいるものを除き、2社以上のメーカーに同じ部品を発注する。そもそも、図面や資材をメーカーが用意しているケースも多い。この時点で製品の特殊性もなにもあったものではない。
にもかかわらず、「2社購買、3社購買でも一向にかまわない。他の会社が赤字になるから作れないという価格でも、うちは十分に利益が出る」とその社長はうそぶくのだ。
これこそ、カイゼンが進んだ会社の理想的な姿の1つだといえる。
この会社以外にも、「翌日納品」などを売りにして、多くの製造現場から重宝されているメーカーはたくさんある。他社ができないのに自社だけ即納できるといった体制は、製造や在庫管理方法を地道にカイゼンし続けることでしか実現できない。
また、社内で積み上げたカイゼンのノウハウは横展開がしやすいし、会社の社風や現場の能力・姿勢があってこそ実現できるため、「あの会社はカイゼンで儲かっているらしい」と知られたところで、そう簡単に模倣できない。
カイゼンの成果は
決算書に表れやすい!
ここまで読んでもらえれば、特別な商品・サービスの開発とカイゼンの両方を並行して進めるのが最適解だとお分かりいただけたはずだ。カイゼンを積み重ねることで、売れるときにはより利益を増やし、逆境のときには利益の減少を最低限に食い止める。
カイゼンの成果は決算書に表れやすいため、損益や資金繰りの改善に即効性がある。