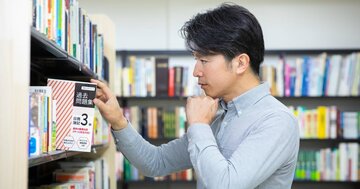人によって生き方もワーク・ライフ・バランスも異なっていい
結局のところ、人が心の安定を保つために大事なのは、「居場所が複数あること」だと思います。家族でも、仕事でも、趣味でも、「ここにいていい」と思える場所が1つしかないと、どうしても苦しくなる。
でも、居場所がいくつかあれば、どこかでうまくいかなくても、他の場所で支えられるのではないでしょうか。それ自体は逃げではなく、むしろ自然で健全なバランスの取り方だと思います。
――「居場所が複数あることが大切」というお話がありました。しかし、現代ではその居場所自体をどう築けばいいのか分からないという人も少ないような気がします。
居場所というのは、最初からどこかにあるものではなく、関わりの中で少しずつつくられていくものだと思います。ある意味では、人はみんな何かに依存しながら生きています。「依存」という言葉に抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、ここでいう依存とは、自分のエネルギーをどこに注ぎ、どこに心を置くかを選ぶということです。
高市首相のワーク・ライフ・バランス発言を巡る騒動に一言感想を言うならば、「価値観の押し付けは望ましくない」と言うこと。「もっと働け」「家庭を優先すべきだ」といった言葉もそうですが、今の社会は他人の基準で人の生き方を測る風潮がまだ根強く残っています。また、SNSなどでいろんな生き方を目にするうちに、「自分もそうしなきゃ」と焦り、他人の基準に引きずられてしまう傾向にもあるように見えます。
でもそれは、本来自分で選ぶべき居場所や依存のかたちを、他人の判断に委ねてしまうということではないでしょうか。
仕事に全力を注ぐ人もいれば、家庭を中心に生きる人もいる。人によって生き方もワーク・ライフ・バランスも、異なっていいと思うのです。そのどちらも、その人の生き方として尊いし、他人がどうこう言うことではありません。強要されたり、干渉されたりすることなく、それぞれが自分のペースで生きられる。
そうした余白を社会の中に残しておくこと。それが、人が安心して暮らせる社会を支える、何よりも大切な要素なのだと思います。