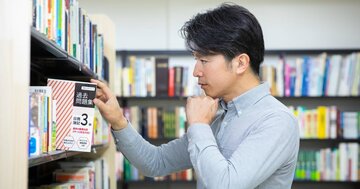支え合いは、「不安」を分かち合うことから始まる
――田内さんの新刊『お金の不安という幻想』の中で、「人と人との関係の中にこそ社会は生まれる」と書かれていました。一方で現代では、人とのつながりが希薄になり、支え合いの感覚を持ちにくくなっているとも感じています。こうした状況で、私たちはその支え合いの感覚を、日常の中でどう取り戻していけるでしょうか。
確かに、今の社会では人とのつながりを持つことが難しくなっています。でも、変な人がいたら嫌だとか、迷惑をかけたくないといった不安が壁になっているだけで、根本的には多くの人が「本当は誰かと関わりたい」と思っているのではないでしょうか。
実際には、ちょっとしたきっかけで人とつながることができると思うのです。私自身も、「こんなことで誰かとつながれるのか」と感じた印象的な経験があります。
数年前、ニュース速報で大きな事件が報じられたときのことです。
初めて入った美容院で髪を切っていたのですが、初対面の美容師さんと「怖いですね」「何が起きているんでしょう」と言葉を交わすと、普段なら会話をしない隣のお客さんまでが「さっきニュースでこう言っていましたよ」と自然に加わってくれた。
あの瞬間、あの場にいた全員が同じ不安を共有していました。不安を口にしたことで、たまたま居合わせた他人とつながることができたのです。
――不安を共有することが、人とのつながりを生むきっかけになるということですね。
そう思います。災害のときもそうですが、「この不安は自分だけではなかった」と気づくだけで、気持ちが落ち着くことがある。不安を言葉にするというのは、単なる弱音ではなく、他人との接点をつくる行為なのだと感じます。
家族も同じです。ぶつかることがあっても、自分の感じた不安を素直に伝えれば、相手も「実は自分もそう思っていた」と応じてくれることがある。それが共感を生み、小さな支え合いにつながる。そういう関係性の積み重ねこそが、社会全体の「支え合い」の原型になるのではないでしょうか。
行政との関わりも同じです。不安を抱えていても、「こんなこと相談しても無駄だ」と思いがちですが、本当に困っている人の声を聞けば、行政側だって「何とかしてあげられないか」と思うはず。大切なのは、不満をぶつけるのではなく、不安を伝えること。怒りや要求ではなく、「ここが不安なんです」と伝えるだけで、受け取る側の姿勢も変わります。一方的に攻め合う関係ではなく、互いに理解し合おうとする関係に変わっていく。そんな小さな対話の積み重ねが、社会の信頼関係を少しずつ取り戻す力になるのだと思います。
そしてもう一つ大事なのは、「共通の目的」を持てること。今は地縁や血縁のコミュニティが薄れ、「自分がいていい場所」が見つけにくい時代です。学校や会社、家庭の中で、つながりを深めるためには共通の目的を意識したことがだ大切だと思います。誰かと同じ方向を見て、小さな目標を共有するだけでも、人は安心できます。
結局のところ、支え合いというのは「不安を共有する」「共通の目的を持つ」といった人と人との関係の中から生まれる。小さな関係を取り戻すことが、人手不足や分断といった社会の課題を解く糸口になるのだと思います。