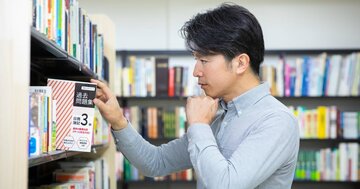肩書やお金よりも人を強くするもの
――田内さんの発信には一貫して、「お金の不安を減らすためにこそ、人とのつながりが大切だ」というメッセージがあります。人とのつながりを軸に、私たちはこれからの時代をどう生きていけばいいでしょうか。
お金というのは、もともと人と人とのつながりを仲介するための道具にすぎません。知らない人同士が取引できるようにするために生まれた仕組みです。
だから、社会の本質はお金ではなく、人と人との関係にあります。信頼や協力があってこそ、お金の仕組みも正しく機能するのです。お金は、つながりのための手段であって、目的ではありません。
――年金制度の先行きや長寿化など、老後を取り巻く不安要素は増えています。かつての村社会や地域の助け合いが薄れたことも、不安を大きくしている要因の一つではないかと感じました。田内さんは、こうした孤立の時代をどのように見ていますか。
老後の不安は、必ずしも金銭的な問題だけではありません。むしろ、「自分がどこにも属していない」という孤立の不安のほうが大きい気がします。日本で男性の孤独死が少なくないのも、居場所が見つけにくい社会構造の表れではないでしょうか。
誰かに頼られたり、誰かを支えたりする関係があれば、多少お金が足りなくても人は生きていけると思います。人は孤立したときに不安を強く感じるものですが、関係の中にいれば不安は自然と和らぎます。
『お金の不安という幻想』でも、「いくらお金があっても、働く人がいなければ暖房も食事も手に入らない」と書きました。お金が社会を支える本質的な力ではないことを伝えたかったからです。
目の前の生活が成り立っているのも、誰かが働いてくれているから。食料が届くのも、電気や水が使えるのも、医療や介護の現場が動いているのも、すべて、誰かの労働があるからこそです。お金があることよりも、人が動ける社会であること、そして誰かと支え合える関係があることのほうが、よほど確かな安心をもたらします。
お金の不安というのは、社会との関係を見失ったときに強くなるもの。本来、社会は分かち合うようにできています。人手不足の今こそ、誰かと協力し、支え合うことの価値が高まっているのではないでしょうか。
たとえば、私の知り合いにも、60代を過ぎても現役で働き続けている方々がいます。特別な資格があるわけでも、体力的に恵まれているわけでもないけれど、でも若い頃から誠実に人と関わり、周囲の人たちとの関係を大切にしてきた人ばかり。その積み重ねが信頼になり、「あの人なら安心して任せられる」と仕事を紹介され続けているのです。
こうした「社会関係資本」こそが、肩書やお金よりも人をずっと強くします。信頼の輪が、仕事にもお金にも、そして心の安定にもつながっていくのです。結局のところ、信頼やつながりがあることで、経済は循環します。