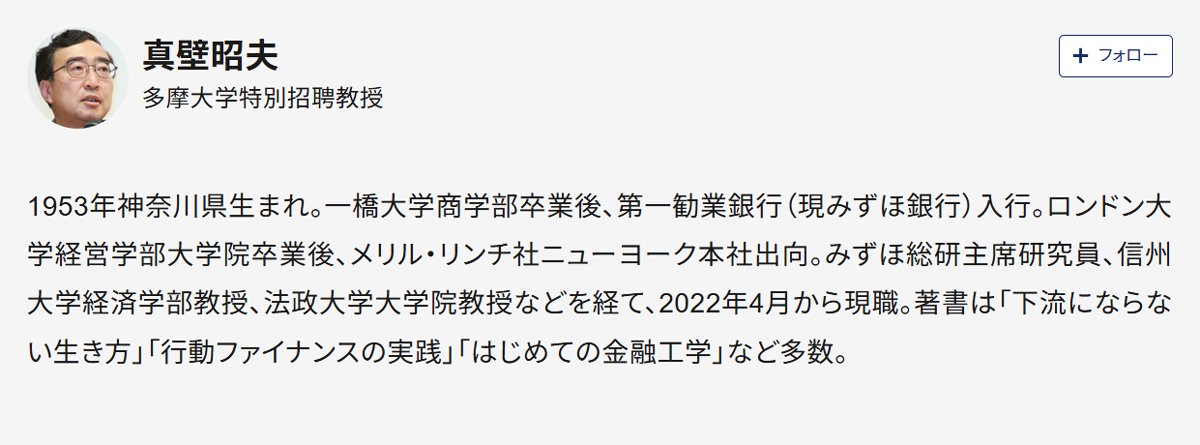鉄鋼、造船、AI、バッテリー、医薬品でも
中国に依存する日米欧の企業
冷戦終結後、中国は経済特区を設けて海外からの直接投資を誘致した。農村部から労働力を供給することで工業化が加速し、世界の工場としての地位を確立してきた。
主要先進国の企業は、中国で低コストの生産を行い、需要が旺盛な市場に高価格で供給する体制を確立した。特に、米国の企業は、高付加価値型のソフトウエア開発に集中的に取り組み、製品の製造は中国や韓国、台湾企業に外注した。こうしてグローバル化が加速し国境のハードルは低下した。
その状況下、中国政府は覇権強化のため、虎視眈々と自国企業の世界シェア拡大に取り組んできた。主に海外企業から製造技術などを強制移転し、産業補助金や工場用地などを安価に供与し、政府主導で国有企業の経営統合などに努めた。
ウイングテックも半導体の生産体制を拡大し、主要な自動車メーカーから需要を取り込んだ。その他にもあらゆる分野――鉄鋼、造船、電動車、AI(人工知能)、半導体、バッテリー、太陽光パネル、液晶ディスプレー、医薬品原材料などで中国に依存する日米欧の企業は増えた。
第2次トランプ政権下で、中国は米国の圧力に対抗してレアアースなどの供給を絞った。シェアの高さを武器に相手国を揺さぶり、譲歩を引き出すことで、今のところ中国政府は対米交渉を優勢に進めている。
トランプ政権は多国間連携を基礎に、対中包囲網を形成することが必要になるだろう。しかし、これまでのトランプ氏の数々の言動から、相手国がすぐに米国になびくとも思えない。
日米欧では当面、サプライチェーンを見直し、友好国や自国内での調達体制の再整備を急ぐ企業が増えるだろう。在庫を積み増す企業も増え、世界的に価格転嫁が進む可能性は高い。ネクスペリア問題は、そうした変化を加速させるきっかけと考えるべきだ。
首脳会談で米国は、中国の補助金や国有企業の経営統合などの問題には踏み込めなかったようだ。米中の対立次第でネクスペリア問題のようなショックが再び発生するリスクは高い。そして、それは大企業の経営のみならず、回り回って物価、雇用、所得環境の悪化など、一般市民の生活にも重大な影響を与えることに注意したい。