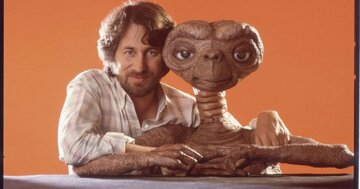しかし敵対的買収はリスクフリーではない。圧倒的大多数のケースにおいて、買収後の新会社の利益は、買収前の2社の利益の合計よりも低くなる。しかし、うまくいけば話は別だ。1999年に、蘭フィリップスが、米チップメーカーVLSIを成功裏に買収、その1年後に、英ボーダフォンが独マンネスマンを買収した案件は、まさに「一石二鳥」のシナリオとなった。
取り込み戦略の基本は幅広く応用できる。アムステルダム市が、地下鉄の新型車両を破壊行為から守るための対策を検討したとき、市会議員のマーク・ファン・デル・ホルストが大胆な提案をした。悪名高い破壊者を招いて、そのうちの1両を解体させれば、破壊行為の最善の抑止力になるだろう、というものだった。
軍事組織もよくこの戦略を使う。ITのセキュリティ強化のためにハッカーを雇ったり、二重スパイとしてスパイの協力を仰いだりしている。警察やシークレットサービスも、泥棒を使って泥棒を捕まえるというかたちで、この戦略を頻繁に使っている。
極右デモの行進も止まる
相手の行動を逆手に取る戦略
ドイツのヴンジーデル村も、この戦略を見事に利用した。ヴンジーデルでは、毎年11月に、ネオナチが村を練り歩いていた。第三帝国(訳注:1933~1945年にナチスが政権を握っていたドイツの公式名称)の副総統だったルドルフ・ヘスが埋葬されていることから、極右デモ隊の巡礼地となっていたのだ。地元住民は何年にもわたって行進をやめさせようと試みるも、うまくいかなかった。
しかし、2014年11月、ついに問題はフリップ思考によって打開された。地域の商工業者が、ナチスの行進をチャリティーウォークに変え、デモ隊がメートル歩くごとに協賛企業がユーロを反ナチス組織EXIT-Germanyに寄付するというイベントにしてしまったのだ。つまり、ネオナチは事実上、自らに反対するデモ行進を行ったことになる。彼らが最終的に集めた反過激派組織への募金は1万ユーロを越えた。