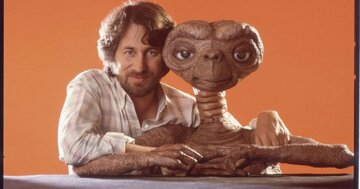敵とは戦うこともできるし、味方につけようとすることもできる。敵に勝てないなら、味方にすればいい。あるいは、オランダ財務省の事例のように、抱き込んでしまえ。
取り込み戦略は、この知恵を利用する。相手を「彼ら」から「私たち」に変えるのだ。サッカークラブはこれをよく心得ており、主要な競争相手の最高の選手たちとしょっちゅう契約を結んでいる。こちらは優秀な選手を1人手に入れ、相手は1人失うという、一石二鳥の効果がある。
敵対せずに
相手の力を活用する
敵の勢力を取り込む行為は、あなたと「敵」との関係性によって、友好的に行うケースから生命を脅かすケースまで、さまざまな状況が考えられる。たとえば、あなたが教師で、授業中の携帯電話の使用をめぐって、生徒と何度か攻防を繰り返していたとしよう。
かなり多くの教師がこの壁にぶち当たっている。学校によっては、生徒が教室に入ってくるときに、携帯を教室の前の箱に入れさせているところもあるが、それは明らかなスタック思考(編集部注/行き詰まった状態や、特定の考え方に固執して柔軟性を失った状態。フリップ思考の対極にある考え方)の例である。生徒の大いなる反感を買うことになるからだ。
そのため、携帯電話を学習ツールとして使わせる教師が増えている。なにしろ、携帯電話はポケットサイズのコンピューターなのだから、そのすべてのパワーを有効活用してはどうか、という考えだ。
コメディアンのサラ・クロースも、似たような友好的なかたちで、敵の取り込みをやってのけた。
彼女がパフォーマンスをしていた建物で、同時にマルディグラ(謝肉祭)を祝うブラスバンドが演奏しており、彼女のパフォーマンスを妨害するほどの大きな音を出していた。そこで彼女はそのグループを招待し、自分の観客のためにも演奏してほしいと頼んだ。バンドは招待を受け、観客は大喜びし、ショーは賑やかなマルディグラ・パーティーに変身した。
敵対的企業買収は、比較的強引な取り込みになる。サッカークラブが他クラブのスター選手と契約するのと同様の戦略的見返りがあるのは明らかだ。敵を乗っ取ることで、きわめて効率的に相手を無害化できる。競合を排除すると同時に、新たな才能と知識を獲得できてしまう。