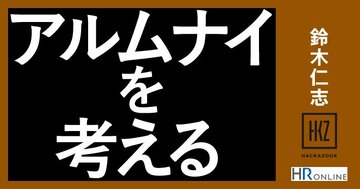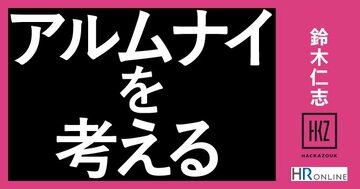「静かな退職」の背後に潜んでいる“すれ違い”
「静かな退職」は、広く捉えれば、従業員のモチベーションやワークエンゲージメントの低さといえる。日本は、米国のギャラップ社による「従業員エンゲージメント」調査において、長年、世界の下位レベルにランクされ、「ワークエンゲージメント」の概念と測定法を開発したオランダ・ユトレヒト大学の調査によると、他国に比べて日本だけが突出してスコアが低く、研究者は「何かの間違いではないか?と疑った」というエピソードもある。
門馬 現在、多くの企業で構造的な人手不足が深刻化しており、従業員のモチベーションやワークエンゲージメントを通して、労働生産性をいかに高めるかが大きな経営課題になっています。
そのソリューションは千差万別で、仮説に基づいて、施策や検証を行(おこな)い、その結果をもとに、また仮説を立てて取り組むことを繰り返すしかありません。注意しなければならないのが、私たちの調査結果にも表れている“社員と企業の認識ギャップ”です。企業・人事がいろいろな施策や検証を行(おこな)ってもなかなか結果が出ない場合、背後には、意識の“すれ違い”が潜んでいることを知っておきたいです。
“すれ違い”の要因として、人事部門の人的パワーにおける余裕のなさと課題分析力の不足もありそうだ。
門馬 例えば、「即戦力として中途採用した人材がすぐに辞めてしまう」というケースにおいて、企業・人事は「即戦力として採用したのだから、すぐに活躍してくれると思っていた」のに対し、社員は「解像度の高い情報をもらわないと、自分の経験やスキルをどう生かせばいいのか分からない」と考えていたりします。
こうした“すれ違い”の解消のために、当社は、支援先に対して、採用プロセスやオンボーディングプログラムの見直し、ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を再定義し、社内に浸透させるプロジェクトの提案などを行(おこな)っています。