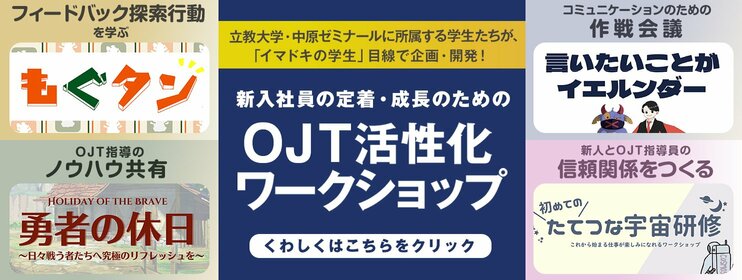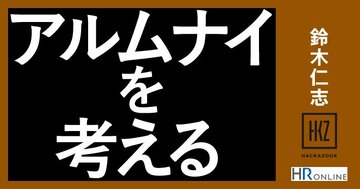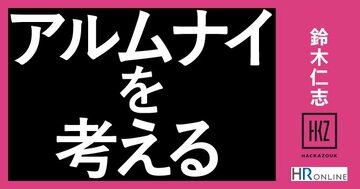「静かな退職」に経営層や人事部はどう向き合うか
企業・人事が「静かな退職」と向き合うにあたり、前提とするべきが、社員の価値観や働き方の多様性だ。年齢・性別はもちろん、育児や介護、病気治療……さまざまな事情を抱える人がいて、人事担当者や管理職は、それぞれの声に耳を傾ける必要がある。
また、会社や仕事への過度なコミットメントを避けて、定められた範囲の職務をこなしていく「静かな退職」は、キャリアと私生活を両立させるための合理的な選択肢のひとつとも考えられ、従業員の「キャリア自律」の実践でもあると、企業・人事が理解することも大切ではないか。
門馬 私の知り合いのビジネスパーソンは、外資系企業に勤務しているのですが、パフォーマンスさえ上げれば、勤務時間や場所を柔軟に調整できることに満足しています。そして、会社のパーパスに共感はしていますが、「一心同体になって頑張るつもりまではない」と言います。このように、ワークとの両立で日々のライフを優先したいタイプの方は増えていくでしょう。
では、企業・人事は「静かな退職」にどう向き合えばいいか?――日々、私は人事の方と話をしてますが、これはなかなか難しい問題です。人材不足のなか、生産性を上げるために、「静かな退職」に向き合うことはとても重要なのですが、解決策につながる出口の在り方は各社各様で、決定的な答えはありません。「静かな退職」の理由が、人事施策の場合もあれば、個々の職場のなかにある場合も散見します。コミュニケーションの有無、人的配置、目標設定や評価の仕組み、上司との信頼関係……個社それぞれの解のために、まずは、「静かな退職」の理由を見つけること。具体的なアクションとしては、組織・個人両方への働きかけが効果的です。人事が従業員の声に耳を傾けつつ、上司・同僚にも必要なサポートが提供できるよう、私たちも、支援先と並走しています。
モチベーションやワークエンゲージメントの低さや「静かな退職」の広がりは、企業の旧態依然とした仕組みや職場環境が影響しているのだ。経営層や人事部門は、まず、そのことを把握したい。
門馬 仕組みの見直しや職場環境の改善のためには、外部の“プロ人材”(*4)の活用が有効的です。例えば、先ほどお話しした「転職者がすぐに辞めてしまうケース」は、社内の人事担当者には言いにくいことでも、外部のプロ人材なら聞き出せたりもします。
企業にとっていちばん重要なのは、いかに企業価値を高めるか、です。そのために欠かせないのが、働く人たちの成長や幸福感。「この会社で働くことが、自分の成長につながる」という実感をもたらすことが、「静かな退職」が増えるなかで、経営層や人事部門の役割だと思います。
*4 HRオンライン「人事領域の“プロ人材”が、組織の生産性を高めるために必要とされる理由」参照