まずは本人に事実確認。不正受給の場合は?
カタリーナ「まずは本人に、投稿の経緯を確認して。療養中に社会とつながろうとする行動は、回復過程では、実はよくあることなの。悪意がなければ、注意と再発防止を検討したいところね」
橋田「健康保険組合には?」
カタリーナ「事実確認をした上で、正直に相談してみて。比較的軽微な作業や単発の活動で、療養を妨げない程度であれば、直ちに労務不能を否定するとは限らないけれど、判断するのは保険者である健保組合だから」
橋田「もし、不正受給とみなされた場合はどうなるんですか? そもそも、本当は深刻な病状じゃないのに、大げさに言い立てて医者に診断書を書いてもらう人もいるとか、聞いたことがあります」
カタリーナ「そういった、よからぬ話もあるようね。不正受給と認定されると、受け取った給付金を原則返還することになるわ。仮に、会社や医師が虚偽の記載をして給付金を受け取った場合、事業主や医師は受け取った本人と連帯して徴収金の納付を命じられることもある。悪質な場合は、詐欺罪として刑事告発されることだってあるのよ。断じてやってはいけないことだわ」
橋田「そうなんですか。会社もちゃんと対応しないといけませんね」
精神疾患による傷病手当金の受給が大幅に増加
後日、本人からヒアリングを行った、と橋田からカタリーナに報告があった。稲垣まりえの説明によると、医師から指先を動かすと気分転換になると言われ、趣味であったハンドメイド作品を作ったところ、妹から出品を勧められ、つい投稿してしまったということだった。本人も深く反省している様子で、療養の一環とは考えられるが、SNSへの投稿など休職中に誤解を招く行動は控えるように、厳重注意したという。
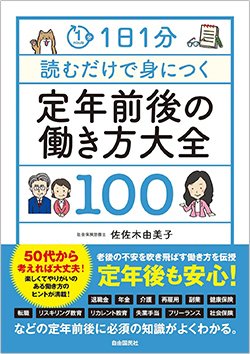 『1日1分読むだけで身につく定年前後の働き方大全100』(自由国民社)佐佐木由美子 著
『1日1分読むだけで身につく定年前後の働き方大全100』(自由国民社)佐佐木由美子 著
橋田「それにしても最近、若手社員がメンタル不調で休職するケースが多くて。こちらもちょっとナーバスになっていたんですよ」
カタリーナ「直近の協会けんぽの給付状況をみても、精神疾患による支給件数は前年度から17%増えて7万件を超えているの。20~30代は精神疾患による理由が圧倒的に多く、年齢階級別にみると女性は20代後半の支給件数が一番高くなっているわ」
橋田「そうなんですか、うちの会社だけじゃないんですね。いやぁ、すぐに処分なんて言わなくてよかった」
カタリーナ「そうね。制度は線引きのためにあるけれど、その線の内側にある、人の回復まで見てあげられるのが職場の力よ」
●傷病手当金の支給要件のひとつに、「療養のため労務に服することができない」ことがある(健康保険法第99条1項)。偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。この場合、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医若しくは主治の医師が保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金の納付を命ずることができる(健康保険法第58条)。
●全国健康保険協会管掌健康保険の「現金給付受給者状況調査報告」(令和6年度)によると、「傷病手当金」の受給の原因となった傷病別に件数の構成割合では「精神及び行動の障害」が 39.15%で最も高い。男女別にみると、男性では 35.69%、女性では 42.68%となっている。また、年齢階級別にすべての傷病の支給状況をみると、50~54 歳が 12.29%で最も高いが、女性のみの支給状況では「25~29歳」が13.75%で一番割合が高い。
※本稿は一般企業にみられる相談事例を基にしたフィクションです。法律に基づく判断などについては、個々のケースによるため、各労働局など公的機関や専門家にご相談のうえ対応ください。
(社会保険労務士 佐佐木由美子)







