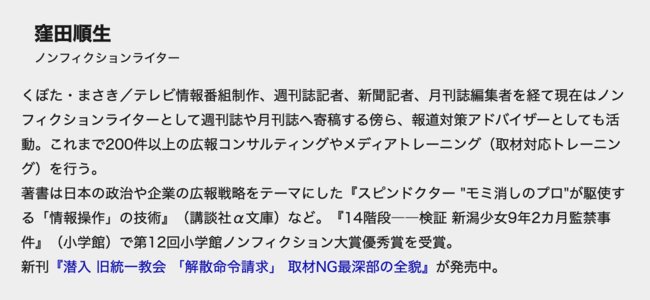その佐藤を人気作家にした「富士に題す」(1930年 大日本雄弁会講談社)という大衆小説がある。これは日露戦争時の新聞記者が主人公で、「日比谷焼き討ち事件」のシーンが登場する。ご存じのように、これは帝国海軍がロシアのバルチック艦隊を撃破後に、結ばれた講和条約に反対をした数万人規模の暴動だ。
「国賊め!」と叫んで役所や新聞社を襲撃する民衆に殴られた主人公は、その足で新聞社の社長のもとに行って退職を告げて、こんな「マスコミ批判」をする。
「今日の暴動の如きは君等が扇動したのだ、さうだ、君等だ、東京の諸新聞だ、何のために煽動したかといふに人気取のためだ、一枚でも新聞を多く売らうといふためだ、愚民の愚になる事を知つてその愚に媚び、愚に乗じて読者の歓心を得る様の記事を書く、そこに国家もなければ社会もない、新聞は商品となつてしまつた」(633ページ)
実はこの時代も日本の新聞は「売れる」という理由で、勇ましい論調を毎日書き立て、戦果も誇張していた。それに煽られて「好戦的」になっていた人々が「戦争継続」を求めて暴徒化したのだ。しかし、実際は日本もこの戦争でかなりの犠牲者が出ていて、戦争を続ける余力はなかった。そういう現実に目を背け、ロシアを徹底的に叩きのめせと勇ましいことばかりを主張する人々を主人公は「愚民」と呼んでいる。
100年以上前の出来事だが、このような事態は普通に令和でも繰り返すと筆者は考えている。今、メディアを見渡しても、YouTuberを見ても、とにかく「中国にナメられるな」と勇ましいことを言うと「数字」が取れる傾向がある。そうなると、二匹目のドジョウを狙って、どんどん似た論調、さらに過激な論調があふれていく。
煽っている側は「金のため」と割り切っても、煽られた側は真に受けるので、メディアを上回る過激さ、メディア側が引くほど好戦的になっていく。そこまで世論が暴走したら誰も止められない。政治家もメディアも「世論に迎合」するしかない。
「富士に題す」には、「10年後の日本」を予言したような主人公の危機感が記されている。現代の日本人も考えさせられる「諫言」なので、これをもって本稿のまとめとしたい。
「今に見ろ、愚民の御機嫌取をして居ると愚民が増長する、利己主義が流行る。露国の様に虚無主義や無政府主義が入り込む、誰か狂瀾を既倒に回し得るか、さうなると…滅亡だ…日本は…日本はどうなる、馬鹿ッ」(634ページ)