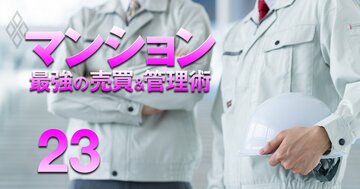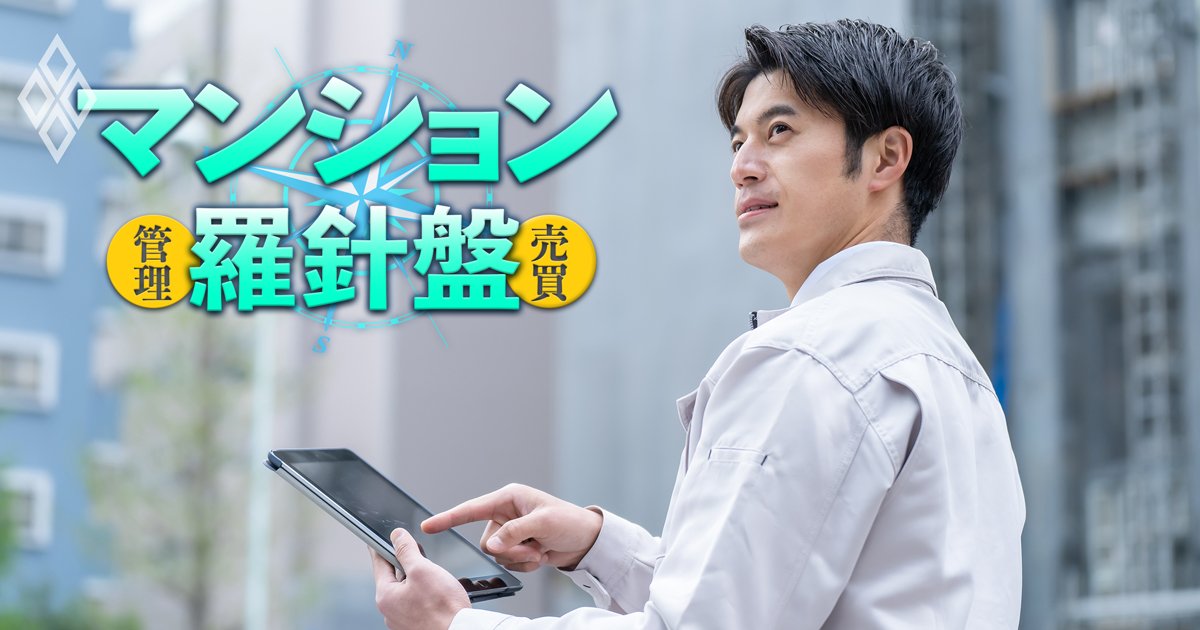 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
急速に普及が進むマンションの外部管理者方式。区分所有者の代わりに管理業務を外部に丸投げできる制度だが、メリットとリスクはどこにあるのか。連載『マンション羅針盤』の第5回では、実践的な活用方法も含めてマンション管理士が解説する。(フルニール代表・マンション管理士 中村優介)
管理は本来「買うものではなく所有者が自ら作るもの」だった
本当の意味で「買える」のが外部管理者方式
「マンションは管理を買え」。マンションを購入した、あるいは購入を検討したことがある方ならこの言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。マンション購入時に、物件の選択条件として優先されがちな立地や間取りなどばかり見ずに、管理状態をしっかり見極めることこそが大切だ、という意味ですね。だいぶ定着してきた感がありますが、実はこれは管理業界に長く籍を置く者からすると、違和感を拭えない格言でした。
というのも、我が国のマンション管理は、多くの場合、そのマンションの区分所有者で構成される管理組合が自分事として意思決定を行うものだからです。さらに、国交省の標準管理規約に倣って執行機関として「理事会」を組織し、その決定に従い管理会社が管理実務を担うことにより成り立っています。つまり、購入者である区分所有者自らが主体的に管理する、というのが我が国のマンション管理の原則なのです。
にもかかわらず、管理を「買う」というのはどうもお客様感覚のニュアンスがあり、個人的には少々違和感がありました。
ところが、近年分譲されるマンションでは、従来の理事会方式ではなく、管理会社等が自ら管理者となる「外部管理者方式」の普及が進んでいます。国土交通省調査によると、2023年時点で管理者業務を「受託している」もしくは「今後受託を検討している」と回答した会社は167社となり、2020年の126社から約3割増加しています。先の格言の文字通りの、「管理を買う」時代が到来しているのです。
今回は、この急速に普及が進む外部管理者方式について取り上げます。マンションオーナーにとってのメリットとリスク、そして管理業務を受託する会社の選び方まで、実践的な内容をお話ししましょう。外部管理者方式は実はリスクに対する誤解も多く、さらにマンションの状況によっては利用できない場合もあります。次ページから詳しく見ていきましょう。