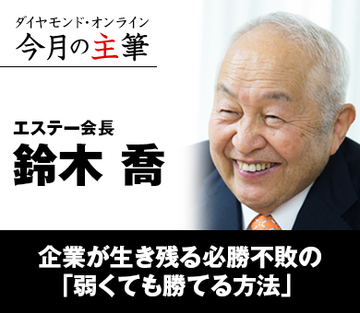エステー
経営理念にある「社会に対する奉仕(SERVICE)と信頼(TRUST)を信条とし、製品については最高(SUPERTOP)を求めること」より、SとTの頭文字を取って「エステー(ST)」と命名した。
関連するキーワード
三菱ケミカルホールディングス 富士フイルムホールディングス 住友化学 三井化学 信越化学工業 花王 旭化成 小林製薬 資生堂関連特集
関連ニュース
20代の投資初心者が「ついやってしまう」落とし穴、 老後に貯金がゼロになる人の特徴とは
大来 俊
新NISA導入の影響で、20代やZ世代の投資意欲が高まっています。一方で、知的好奇心が高まりやすい20代だからこそハマりやすい「落とし穴」があるのです。

「そんなの、アリ?」達人のポートフォリオをコピペできる投資ツールが凄すぎた。
大来 俊
新NISAの導入で20代の投資意欲が高まっています。実際に、証券会社や金融事業者もこれから収入も増えて将来的にメインターゲットになる「Z世代」に向けて新ツールの開発に力を入れています。その一部を取材しました。

家庭の「食用油廃棄問題」を解決する「サビにくいオイル」を生んだ、日清オイリオの“すごい技術”とは
佐田佐知子
近年の食品製造業界では、加工食品の賞味期限を延ばすため、製造工程の見直しのほか、賞味期限と納品に関する業界内の商慣行を改める動きがある。食品ロスを大幅に減少させた各社の「すごい技術」を取材した。

年収が高い化学メーカーランキング2023【トップ5】3位富士フイルム、1位は?
ダイヤモンド編集部,柳澤里佳
今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い化学メーカーランキング2023最新版」を作成した。対象は上場企業で、単体の従業員数が50人未満の会社は除外している。対象期間は2022年5月期~23年4月期。

年収が高い化学メーカーランキング2023【190社完全版】「紅麹問題」で揺れる小林製薬は何位?
ダイヤモンド編集部,柳澤里佳
今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い化学メーカーランキング2023最新版」を作成した。対象は上場企業で、単体の従業員数が50人未満の会社は除外している。対象期間は2022年5月期~23年4月期。

エーザイとエステー「世襲3代目」経営者の後継者選びで決定的な違い
医薬経済ONLINE
エーザイとエステーはどちらも創業家一族が経営を率いてきた。その3代目による後継者選びには大きな差異があるようだ。

第38回
ホラ吹きの名人でありパワハラの最先端!? エステー鈴木会長が語る社長の条件と合議制の罠
朝倉祐介
強烈なリーダーシップを発揮する経営者であり、「消臭ポット」や「消臭力」、「脱臭炭」、「米唐番」といったヒット商品を続々投入したチーフ・イノベーターでもあるエステーの鈴木喬代表執行役会長兼取締役会議長と、『ファイナンス思考 日本を蝕む病と、再生の戦略論』著者の朝倉祐介さんによる対談の後編です。鈴木流のホラの吹き方から商品開発の裏側、後継者の育成まで、話題が多岐にわたって大いに盛り上がりました。

第37回
エステー鈴木会長はなぜ退屈なサラリーマン時代20年を経て苛烈リストラを断行できたのか?
朝倉祐介
1998年から日用品メーカーのエステーを率いて「消臭ポット」や「消臭力」、「脱臭炭」、「米唐番」などのヒット商品を連発してきた鈴木喬取締役会議長兼代表執行役会長は、『ファイナンス思考 日本を蝕む病と、再生の戦略論』著者の朝倉祐介さんがかねてから面談を切望していた人物。ついに今回の対談でその夢が実現し、鈴木会長が貫いてきたリーダーとしての鉄則についてうかがいました。

最終回
「良いものを作れば売れる」は開発者の驕りにすぎない
鈴木 喬
中小・中堅企業が生き残る必勝不敗の経営がある、というエステーの鈴木喬会長。そうした発想と自信は、どのような経験から育まれたのだろうか。発想の源泉を聞いた。

第3回
社長と経営者は違う。その差はなにか
鈴木 喬
齢80を過ぎて「社長と経営者は違う」とつくづく思う。「社長」「経営者」と同じ存在を言っているようだが、内実はまったく別物で、社長であることをよしとする人と、経営者になろうとする人は明らかに違う。経営者とは、やはり社長のもう一つ上なのではないかと思うのだ。

第2回
イノベーションはハッタリから生まれるのだ
鈴木 喬
90年代後半、業績が悪化するなかで社長に就任するやリストラと同時に商品開発に大なたを振るい、自ら企画した数々のヒット商品を生み出した。その背景にあった思いや新しいものを生み出すためのイノベーションに対する考え方とはどのようなものだったのか。

第1回
企業が生き残る必勝不敗の「弱くても勝てる方法」
鈴木 喬
「消臭力」や「脱臭炭」「ムシューダ」などのユニークな商品を連発するエステー。その開発と販売をリードしてきたのが鈴木喬会長だ。P&Gや花王などの巨人たちが割拠する日用品業界で独自のプレゼンスを発揮できている理由はどこにあるのか。直面する経営課題にどのよに向き合ってきたのか。