
「できそうだ」と「いいな」を増やす、ビジネスバンクの起業家支援
宇都雅史
前回に引き続き、ビジネスバンクの浜口社長にご登場いただきます。同社が掲げる企業理念を実現すべく、2つのコトバを掲げて日本にないサービスを立…
2010.2.24

宇都雅史
前回に引き続き、ビジネスバンクの浜口社長にご登場いただきます。同社が掲げる企業理念を実現すべく、2つのコトバを掲げて日本にないサービスを立…
2010.2.24

2005年に経営の第一線より退いてから、グローバル規模での企業文化の確立や、国際社会貢献活動などで、今も世界中を飛び回っている。なぜ、その…
2010.2.24
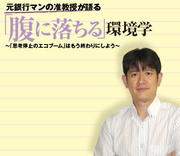
見山謙一郎
日本企業の優等生であるトヨタ自動車が、リコール問題に揺れています。「トヨタほどの企業がなぜ?」と考えてしまいますが、優等生ゆえの「守り」の…
2010.2.23

高城幸司
みなさんの職場でも既婚者と独身者が混在していると思います。両者の考え方や生活リズムの違いは、普段の仕事や飲み会などのあらゆる場面で表れます…
2010.2.22

上田惇生
知識労働者には、いつになっても終わりが無い。文句は言ってもいつまでも働きたい。とはいえ、30のときには心躍った仕事も、50ともなれば退屈す…
2010.2.22

片山和也
営業活動における最大の成功要因は「商品知識を身に付けること」と「人に好かれること」です。では、マネジャーがそうした営業マンを育てるには、ど…
2010.2.19
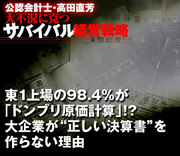
高田直芳
本連載では、これまで数多くの上場企業を取り上げてきた。しかしその東証1部上場の母集団のほとんどが、いわゆる「ドンブリ原価計算」なのではない…
2010.2.19
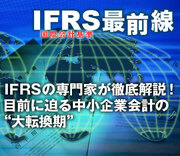
IFRS(国際会計基準)の適用が刻々と迫る現在、中小企業の経営者たちは不安を抱えている。大手企業さえも苦心しているIFRSの導入は、中小企…
2010.2.18

2009年の住宅着工戸数が45年ぶりに80万戸を下回るなど、逆風が吹き続けている。景気回復に向けて、住宅エコポイント制度が始まったが、どれ…
2010.2.17
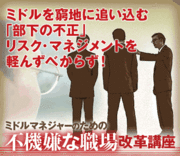
高橋克徳,重光直之
部下が深刻な不正を働いていることが発覚したら──。考えただけでも恐ろしい話です。ミドルマネジャーも「知らなかった」では済まされません。不機…
2010.2.17
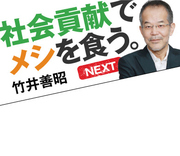
竹井善昭
いま、社会貢献やエコをテーマにした合コン、婚活イベントが増えている。森林で間伐体験ができる「森合コン」をはじめ、男女の出会いを「社会貢献」…
2010.2.16

かつて『若者はなぜ3年で辞めるのか』という新書が話題となったが、就職氷河期の今、「3年で辞める」若者は減少したかもしれない。しかし、入社2…
2010.2.16

上田惇生
好むと好まざるとにかかわらず、経営者は、共に働く人たちの範となることが求められる。さらには、社会を構成するあらゆる人たち、やがて社会の担い…
2010.2.15

田辺和夫前社長(現会長)からの突然のバトンタッチ。「仕事はなにも変わらないので、特段、違和感はない」と話すが、今後の経営方針や戦略について…
2010.2.10
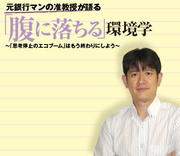
見山謙一郎
デフレ経済の真っただ中、究極の値下げとも言うべき「高速道路の一部無料化」が発表されました。無料やタダと聞くと何だか得をしたような気がします…
2010.2.9

高城幸司
大卒社員と高卒社員は、たとえ世代が近くても、お互いに壁をつくって距離ができてしまう――。そういった話をよく耳にします。しかし、そんな学生時…
2010.2.8

上田惇生
マネジメントとは、まぎれもなく、産業社会における主導的な存在である。マネジメントが主導的な機関として出現したこと自体が、人類史上、画期的な…
2010.2.8
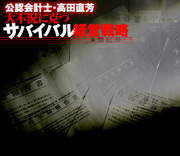
高田直芳
景気のよい「平時」であれば、PER(株価収益率)などの指標も安定しているが、不況時には株価指標としての役割が崩壊してしまう。今回は、話題の…
2010.2.5

本間正人
自分の職場はダメ上司ばかり――。しかし、上司の悪口ばかり言っていては、何の解決にもなりません。どんな上司であれ、いかにうまく「操縦」するか…
2010.2.4

「最新の設備に替えやすい」「メンテナンスなどの対応が不要(または容易)」――。そうしたメリットを理由に、多くの企業が利用している設備投資方…
2010.2.4