
泉谷閑示
第19回
現在の社会では、何につけても効率が優先され、通勤時間などでも寸暇を惜しんで知識を身につけることが奨励されるような風潮があります。私たちの生きる時間についても、常に「有意義」に過ごすべきであるという強迫観念を生みだしてしまいました。「うつ」の治療に欠かせない「何もせずに」療養するという際にも、罪悪感や焦燥感を抱かせる原因になっています。今回は、この「有意義」という病に取りつかれてしまった私たち現代人と「うつ」の関係について考えてみたいと思います。
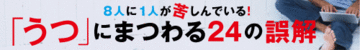
第18回
日本人の大好きな精神論の1つに「逃げてはならない」という考え方があります。 しかし、今日の多様化した時代を生きる私たちの内部では、このような旧来の精神論と「自分らしく生きたい」という自然な欲求とがしばしば不調和を起こし、さまざまな苦悩を引き起こすようになってきています。「うつ」状態に陥る人が増えている背景としても、この問題の存在は無視できません。
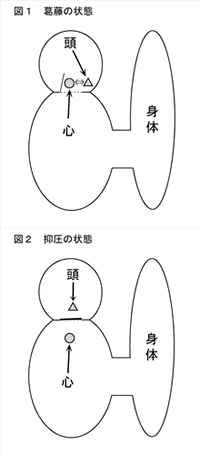
第17回
「そんなに家に閉じこもってばかりいると余計に気分がふさいじゃうでしょ。少しは外に出て気晴らししてみたら?」―「うつ」状態で療養をしていると「ちょっとは身体を動かさないと!」というアドバイスを周りから受けることがよくあるようです。しかし患者さんにとっては、かなりの負担に感じてしまう場合が少なくありません。そこで今回は、「うつ」の人にとって、外出することや運動することがどのように感じられるのか考えてみましょう。
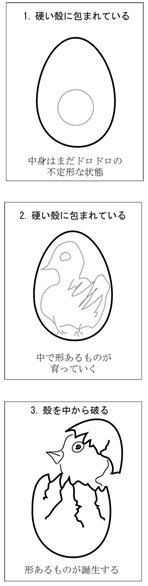
第16回
人間は本来、好奇心のかたまりのような生き物です。「うつ」が本格的に悪化しますと、人は「何もできない」状態に陥ってしまいます。たとえ療養に入っても、はじめのうちは「動けない」自分を責めながら「身体」だけを休ませるような過ごし方になりがちです。この自責の気持ちを緩和できるかどうかが、治療初期における大きな課題です。
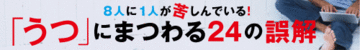
第15回
「うつ」で療養中の人に対して、ご家族など周囲の人から「どう接したらよいのでしょうか?」「何か注意すべきことはありますか?」といった質問を受けることがよくあります。周囲の方たちにとってみれば、「うつ」の状態の心理は理解しがたいものでしょうから、接し方について戸惑ってしまうのも無理はありません。「励ましてはならない」など単発のマニュアルに従っても、表面的なものに終わってしまうことが多いようです。表面的でない接し方にはどんなことが大切なのか、考えてみましょう。
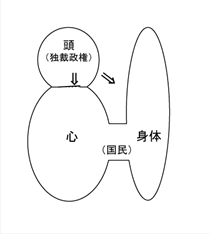
第14回
「うつ」で療養されていた方が職場復帰する際に、段階的な復帰プログラムが用いられることが多いようです。しかし実際には、常にこのアプローチがうまくいくとは限らず、挫折してしまうケースも少なくありません。
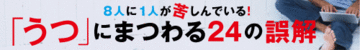
第13回
一般的に現代人は、何らかの病気にかかると、「闘って克服すべきだ」と考える傾向があります。今回は、「病を克服せねば」という考え方が、回復を妨げてしまう側面をもっていることについて考えたいと思います。
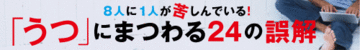
第12回
「うつ」の状態が起こる要因の1つとして、もともとの性格がどうであったのかという問題があります。このように病気が生まれる土壌となる性格を専門的には、「病前性格」と呼びます。今回は、「うつ」に陥りやすい性格とはどんなものなのか、また、そのような性格は変えることができるのか、というテーマについて考えてみたいと思います。近年では、従来型とは異なる新しいタイプの「うつ」も増えてきています。“遊びには行けても会社には行けない”のように一見怠けているかのように見えてしまうタイプです。この新しいタイプの「うつ」においては、性格傾向についてどのような特徴があるのでしょうか。
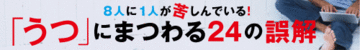
第11回
自殺は「うつ」における最大のリスクであり、社会問題にもなっています。非常に重いテーマではありますが、「うつ」を考える上で、決して避けて通れないこの問題について、今回は真正面から考えてみたいと思います。

第10回
うつ治療において薬物療法が主流の今日ですが、患者さん自身でも「クスリに頼っている」とある種の後ろめたさを感じている方が少なくありません。そこで今回は抗うつ薬の効用と限界について考えてみたいと思います。
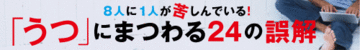
第9回
ウツで休職中の方が、数ヵ月経つと症状が改善し「早く職場復帰したい」と強く思うようになることがよくあります。しかし、実際に復職したとしても長続きせず、再び休まざるを得なくなるケースも少なくありません。
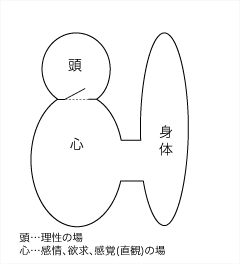
第8回
「うつ」の経過中、単に落ち込むだけでなく、イライラや怒りっぽさが現れてくることがあります。大抵の場合は「情動が不安定になった」として、悪化の兆候と捉えられてしまうことが多いようです。
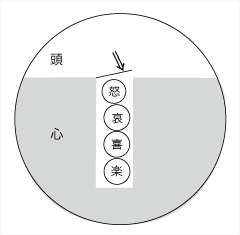
第7回
「うつ」状態になると、朝の起床が徐々に困難になってきます。そのため、次第に遅刻や出社不能などの問題も生じやすくなってきます。気づくと、夕方起きて明け方寝るという「昼夜逆転」現象が起こることも珍しくありません。むしろ、そうならないほうが珍しいと言ってもよいでしょう。 一般的に、療養においては「規則正しい生活」を心がけることが大切だと専門家も含めて考えていますし、私も以前はそれを鵜呑みにしていたのですが、その後多くの臨床経験を重ねるうちに、必ずしもそれにとらわれる必要はないのではないかと考えるようになってきたのです。私はいつ頃からか、起こってくる「症状」にも何らかの「意義」があるのではないか、と考えてみるようになりました。
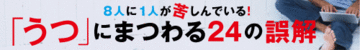
第6回
ウツ病で休職中なのに旅行に行っていることを同僚から「仮病だ」と批判されたE子さん。しかし本当に仮病なのでしょうか――。今回はE子さん側に視点を移し、彼女の中で何が起こっていたのかを考えてみましょう。

第5回
出版社で課長職にあるTさんの部下E子さんは、「うつ病」で半年前から休職中です。E子さんの休職は「うつ病のため、自宅療養を要す」という医師の診断書が提出されての正式なものではあるのですが、上司であるTさんは内心、「E子さんは本当にうつ病なのだろうか?」と疑問を抱いています。部下たちのこんなやり取りも、Tさんの耳に入って来ています。「結局、彼女は大変な仕事はしたくないってことなんでしょ」「あれはきっと、最近よく言われてる『偽うつ』なんじゃない?」「まあ、仮病の一種だよな。だって、聞いた話じゃ自宅療養中なのに、旅行とか行ったりして、楽しく遊んでるらしいぜ」 このように、うつ病で休職中にもかかわらず、旅行には行っているというケースがあります。こういう人は「仮病ではないのか?」と誤解されることも少なくありません。しかし私は、充分にあり得ることだと考えています。
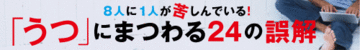
第4回
「うつは心の風邪」という表現は、うつに対する偏見や恐怖心を払拭し、早期発見と気軽な受診を促すことに役立っています。しかし、「風邪」という喩えには、様々な誤解を生んでしまう一面もあるのです。

第3回
遅刻癖のなかった人が、ある時期から遅刻や無断欠勤を繰り返すようになった場合、その人が「ウツ」状態である可能性が考えられます。いくら気をつけようと思っても、結局遅刻を繰り返してしまう。それは決して責任感が足りないのではなく、むしろそんな自分に自己嫌悪してしまっているのです。「あるべき自己」と「ある自己」という言葉を使って心理状態を整理してみると、遅刻してしまう状態の人は、自己イメージが「あるべき自己」一色になってしまっていて、「ある自己」が見えなくなってしまっているのだと言えるでしょう。そこに、「自己管理すべき」とか「責任感が足りない」といったフレーズは、「頭」の「あるべき」の方ばかりを強化するような言葉ですから、まったく逆効果にしかならないのは明らかなことなのです。
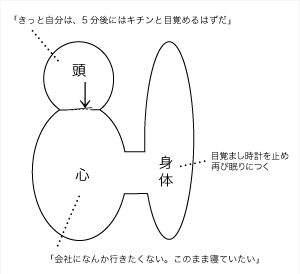
第2回
「仮面うつ病」という病名があります。どこかで聞いたことがあるかもしれませんが、これはmasked depressionの訳語で、「隠されたうつ病」という意味です。つまり、身体症状だけが前面に現れている状態なので、「うつ」であるとは全然自覚されずに、身体の病気と捉えられてしまう病態を指します。ですから、「仮面うつ病」の場合は、本人も身体疾患だと思っているので内科などを受診することが多いのです。精神的な自覚症状が本人にないのですから、内科医も「うつ」が隠れていることを見過ごして、内科的治療だけを続けてしまうことも少なくありません。
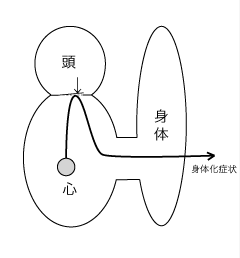
第1回
今年4月に新聞等でも報道されましたが、ファイザー株式会社が12歳以上対象の調査を行なった結果、8人に1人、つまり12%もの人が「うつ病」か「うつ状態」にあると考えられるという報告がありました。この数字が示していることは、もはや「うつ」というものが対岸の火事ではなく、どんな人にとっても避けて通れない身近な問題になってきているということです。そこで「心の弱い奴がうつになる」「病は気から。強い精神力があれば大丈夫」こんな考えを持っている人はいまでも決して少なくありません。しかし、それは誤解です。「うつ」は心が弱い人がかかるわけではないのです。
