
真壁昭夫
第95回
地価の下落が続くものの、一部では復活の兆しも見え始めた不動産市場。だが、“まだら模様”の市場が本格回復を始めるまでには、まだ時間がかかる。不動産の本当の価値を決めるのは、「理論値」ではないからだ。
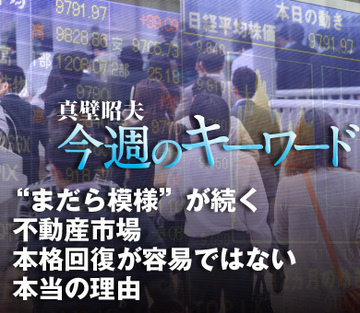
第94回
世界的な大不況を経て、世界最大の成長国に躍り出た中国には、日系企業が殺到している。彼らの多くは、すでに顕著な「中国依存症」に陥っている。しかし中国には、チャンスと同時に想像以上のリスクも転がっている。
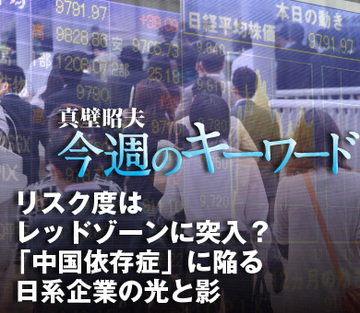
第93回
民主党政権が発足すると、景気が再び悪化するのではないか――。現在巷には、こんな不安が広まっている。不安の焦点は、「バラ撒き」とも揶揄される景気対策だ。民主党は、本当に景気の「二番底」を招くのだろうか。
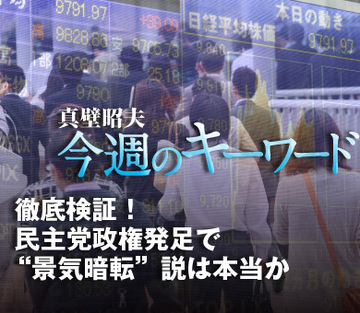
第92回
環境に適応できずに滅んだ恐竜のように、不況下で喘ぐ先進国企業を尻目に、躍進目覚しいのが韓国企業だ。最近までバブル崩壊に悩んでいた彼らは、いったいどんな「突破力」を身につけたのか?
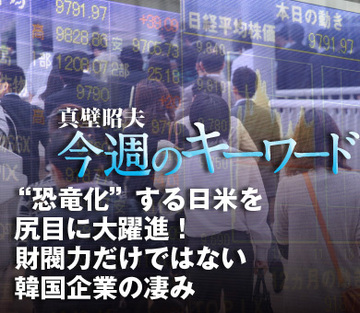
第91回
日本、米国、欧州諸国では、軒並み景気の「早期回復期待」が高まっている。だが、現在の一時的な回復基調は、「雇用なき景気回復」に過ぎない。カネを使って需要を創出しているだけでは、いつか破綻がやって来る。
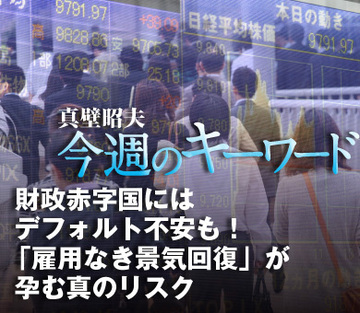
第90回
最近、マイクロソフト、グーグル、ヤフーといった「IT業界の巨人たち」の動きが加速している。クラウド時代の勝者を目指し、なりふり構わずお互いの得意分野に乗り込む「仁義なき戦い」の明と暗を斬る。
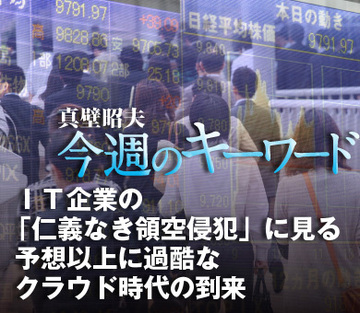
第89回
ここに来て、主要企業の業績が軒並み改善傾向に転じており、市場はそれを好感している。だが、手放しで喜んでばかりもいられない。「真の業績回復までには程遠い」と言わざるを得ない多くの不安要因があるからだ。
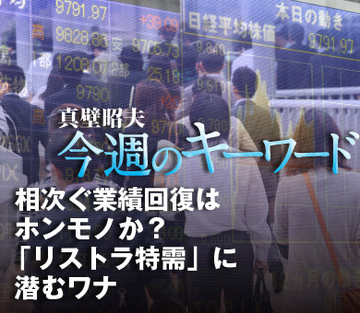
第88回
7月下旬、米国と中国による「米中戦略・経済対話」が初めて開催された。それは、事実上の「G2会議」の様相を呈していると囁かれている。では、過去に例を見ない米中の急接近は、日本にどのような影響を与えるのか?
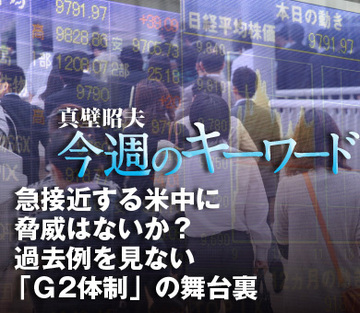
第87回
キリンとサントリー、NECエレクトロニクスとルネサス・テクノロジーなど、大企業同士の経営統合が相次いで発表されている。「強い企業」の登場は経済の“光”となるが、その反面、“影”の部分も見過ごせない。
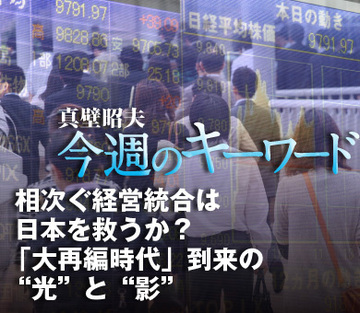
第86回
6月の米国雇用統計が低調だったことから、景気回復期待が再び後退し始めた。世界経済を牽引する米国経済の先行きには、倒してはならないいくつものハードルが立ちはだかる。果たして景気の“二番底”は来るのか?

第85回
経営破綻したGMの優良資産が、政府らが出資する新生GMに譲渡されることが承認された。GMの再建計画は、意外なほどスムーズに進んでいる。だがその裏には、米国政府を揺るがしかねない不安が潜んでいる。
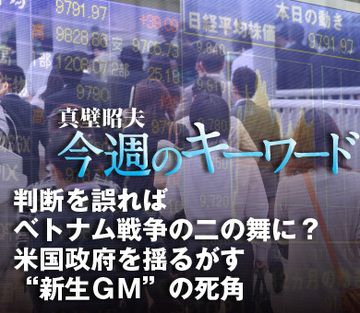
第84回
一時回復基調に乗ったかに見えた株式市場が、再び様子見を続けている。景気回復への期待が剥落し始めた可能性が高いが、いまだ不安が残る米国において市場関係者があまりにも楽観的なのは、気になるところだ。
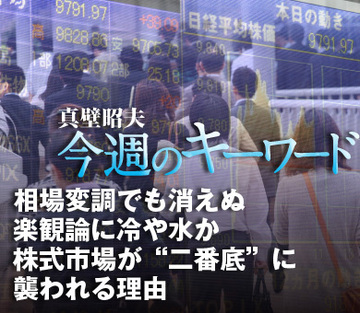
第83回
輸入制限や国内製品の優先購入など、最近、世界でにわかに“保護主義”の気運が高まっている。これは、世界的な経済紛争を招いた1930年代の大恐慌後と同じ現象だ。世界は戦後自由貿易の転換点に立っているのか?

第82回
最近、株式・商品相場が堅調な動きを続けているが、“盛り上げ役”の投機筋は依然として慎重な投資姿勢を崩さない。現場で関係者の話を聞くと、実は彼らの多くが世界経済の行方をかなり不安視していることがわかった。

第81回
世界的な「景気回復期待」が、株価や商品価格、米国債利回りなどを押し上げ始めた。だが市場には、依然不安要素が多い。今後、期待と現実の間に大きなギャップが生じれば、基軸通貨ドルの信用は足許から崩れ去りかねない。

第80回
事前調整によるGMの破綻により、最大のイベントリスクが去ったマーケットは、堅調に動き始めた。だが、これで本当に危機は去ったのか? 実はその裏には、米国の信用力を急落させかなねい難題が山積している。

第79回
ミサイル発射や核実験を行ない、孤立色を強めている北朝鮮。米国のオバマ政権でさえ、万策尽きた感がある。「わかっていそうでわかっていなかった」北朝鮮の地政学的意味を考えながら、現状の厳しさを考察しよう。

第78回
3月期決算で大幅減益や赤字に陥った企業を中心に、これまで日本経済の屋台骨を支えて来た主力事業から撤退する動きが広がっている。このようなトレンドは、実は“日本力”の拡大再生産を促すチャンスにもなり得る。

第77回
「審査結果が甘すぎるのではないか?」米国主要銀行の財務体質を精査した「ストレステスト」の結果については、このような批判が依然として絶えない。そこでこの際、批判の理由と問題の背景を徹底解剖してみよう。

第76回
一時“真っ暗闇”だった景況感には、ここへ来て、少しずつではあるが明るさが出始めている。今回、世界的な景気急落の元凶となった米国については、最近の経済指標を見る限り、下落スピードがだいぶ緩和されており、一時期の景気底割れ懸念はかなり解消している。問題は、こうした“不況下の株高”がどこまで続くかだ。
