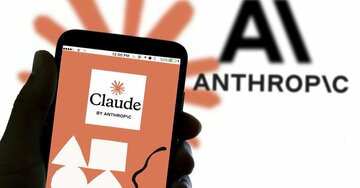かつてウォークマンの大ヒットで、「世界の文化を変えた」と言われたソニー。そんな同社の苦戦が続いているのは、ご存知の通りだ。
その現状は、まさに惨々たるもの。今年3月期の連結業績予想は大幅に下方修正され、昨年10月時点で見込んでいた営業利益2000億円の黒字から、2600億円の赤字に陥る見通しだ。
同社の業績悪化の背景には、世界的な景気後退によって、薄型テレビやデジタルカメラを中心に、主力製品の需要が急速に落ち込んだことに加えて、円高進行による多額の為替差損が発生した影響がある。
それに伴い、同社は国内工場を集約し、数千人規模の人員削減を進めるという。
だが、憂慮すべきは、今回のソニーの苦戦は「単に業績が悪化した」という現象だけに留まりそうもないことである。それはまさに、「“モノ作り大国”=日本」を代表する大手メーカーの“中長期的な存在感の後退”という問題が、顕在化しているとも考えられるのだ。
元々ソニーは、わが国で最初にテープレコーダーを開発するような、高い技術力を基盤とする企業だった。その経緯を振り返ると、同社の技術力は疑う余地もなく群を抜いていたことがわかる。
快進撃のきっかけとなったのは、1950年代半ばにソニーの商標を使ってトランジスターラジオを米国などで販売したことにより、世界市場で名を成したことだ。
その後58年に社名をソニーに改めた同社は、60年に世界で最初にトランジスターテレビを製作し、68年にはわが国最初の「トリニトロン方式」のカラーテレビを開発。その頃から、ソニーの名は世界で通用するブランドに成長して行った。
そんな同社のブランド力を決定づけたのは、70年代後半の“ウォークマン”の大ヒットだった。さらに、80~90年代を通じて事業を積極的に多角化して行き、今やエレキ事業のみならず、保険や銀行などの金融分野、映画や音楽などのエンターテインメント分野でも絶大な存在感を持つ巨大企業へと成長したのである。
ところが、このように半世紀に渡って順風満帆に拡大基調を辿ってきたソニーの経営が、2000年代初頭以降、どうも上手く行っていない。