
上杉 隆
第120回
3月26日、鳩山首相の記者会見がオープン化された。これまで記者クラブの壁によって参加を認められなかった、フリーランス、ネット、海外メディア、雑誌の記者の一部が参加し、質問をすることも可能だった。

第119回
3月23日、民主党とメディアによる壮大な空騒ぎが終わった。生方幸夫民主党副幹事長の「解任」騒動は、案の定、元の木阿弥のまま、何ひとつ変わらず、党に混乱の痕だけを残して収束した。
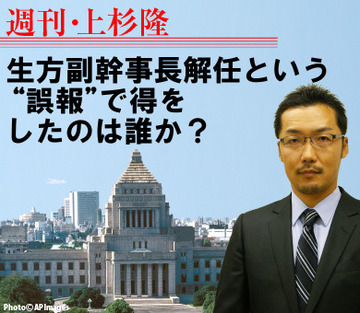
第118回
鳩山邦夫元総務大臣が離党した。前2回、秘書として支えた離党劇は傍らにいた筆者としても十分に理解できるものであったが、今回については、正直なところ、鳩山氏が何を目指しているのかさっぱりわからないのだ。
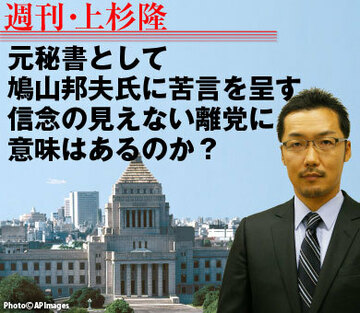
第117回
「密約」を不存在とし続けた過去の自民党政権はどう言い訳をするのだろうか。問題は、一方の当事者である米国が「密約」の存在を認めたにもかかわらず、その事実を隠蔽し続けた近年の日本政府の不誠実な対応にある。
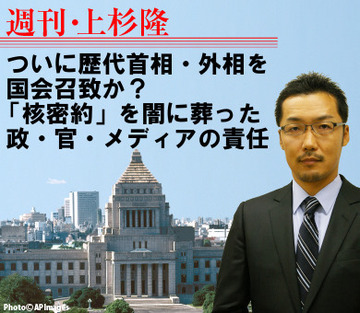
第116回
3月1日、総務省ICTにおける国民の権利保障フォーラムが開催された。構成員でもある筆者は、怒りの退席を行なった。理由は、言論の自由を話し合うはずのこの会合で言論封殺とも受け取れる指示があったからだ。

第115回
先週末、次のような記事が外務省記者クラブを揺るがせた。【岡田外相が閣議後の取材を拒否へ 外務省記者クラブへ通告へ】。最初に筆者の立場を明確にしておこう。筆者は、今回の岡田大臣の決断を完全に支持する。
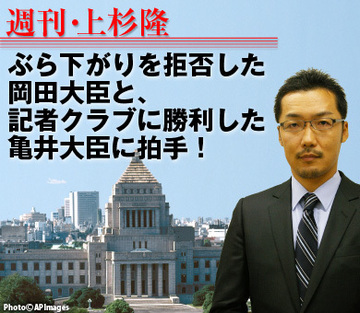
第114回
初の党首討論で谷垣総裁は鳩山首相の「脱税」を追及した。しかし自民党議員の多くがこの問題になると、口をつぐんでいる事実はなんとも不思議だ。とくに歴代の総裁たちが、沈黙を守っているのは不可思議だ。

第113回
大久保秘書逮捕されてからの10ヵ月間、記者クラブメディアは検察からの情報ばかりに拠って、あたかも小沢幹事長が逮捕されるかのような報道を繰り返してきた。だが、結果は小沢幹事長の不起訴であった。

第112回
ハイチの大地震が発生して3週間が過ぎようとしている。こうした動きの中、日本政府の反応は鈍い。地震対策先進国としての日本には多くの期待がかかっている。だが、ハイチの人々の声は日本国内ではあまり響いていない。
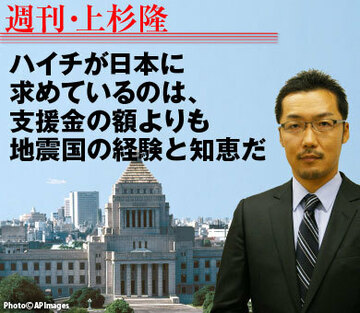
第111回
「週刊朝日」に今週も書いた。タイトルは「検察の卑劣」。国家権力である検察の卑劣さと、そこに寄生する記者クラブの不健全さをリポートした。すでに筆者のツイッターには先週号以上の反響が寄せられている。

第110回
今週の「週刊朝日」に書いた原稿「検察の狂気」への反応の大きさに驚いている。タイトルは編集部のつけたものであり、筆者の意図は単純な検察批判にはない。むしろ、批判の矛先は記者クラブメディアにある。

第109回
いま、大臣記者会見が面白い。これまで政界関係者か政治記者、あるいはよほどの政治好きでない限り関心を持つことのなかった政治家の記者会見。ところがその記者会見に人気が集まっているという。

第108回
元旦より鳩山首相がツイッターを始めた。ソーシャルネットメディアの存在に無関心ではいられなくなったようだ。情報過疎になる首相官邸に、国民からのつぶやきが直接届くのは決して無意味なことではない。

第107回
発足当時70%前後あった内閣支持率は、100日間ですべて50%前後まで下落した。前3政権、とりわけ安倍内閣のそれと同じような右肩下がりのグラフを示している。その例に従えば、より支持を失うのはこれからだ。

第106回
総務大臣の諮問機関である第1回「ICT権利保障等フォーラム」が始まった。ジャーナリストとしての立場での参加に悩んだが、結局、自らの業界のルール作りに傍観者ではいられない。

第105回
鳩山首相は「COP15」でオバマ大統領との会談を目指し、普天間に関する日本の方針を示すという。日米会談自体のアレンジも確定したわけではないという。いったいこの場当たり的な対応はなんなのであろうか。

第104回
先週、筆者は中国で開かれたオメガミッションヒルズワールドカップを取材した。1984年に初めてゴルフコースのできた中国は、わずか四半世紀の間に巨大なマーケットに変貌しようとしている。

第103回
民主党が陳情窓口を党に一本化することを決めた。産経新聞によれば、小沢幹事長に権限が集中し、党全体の支配を許し、最終的にすべての利権を独占するとしている。だが、果たして本当にそうなのだろうか。

第102回
きのう(11月17日)、行政刷新会議の事業仕分けの前半が終了した。新聞・テレビ等ではそれ程高い評価を得ていないようだが、全5日間を取材した筆者の率直な感想を述べれば、十分効果的な取り組みだったと思う。

第101回
きょう(11月11日)、行政刷新会議のワーキングチームによる事業仕分けがスタートした。希望者は誰でも傍聴が可能だ。初日のきょうは激しい雨にもかかわらず、早速入り口には行列ができた。
