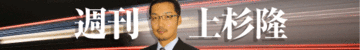上杉 隆
第80回
自民党は世襲制限導入の見送りを決めた。世襲の新人候補の立候補制限は、次の次の総選挙に持ち越されることになった。これにより、小泉純一郎元首相の次男・進次郎氏の公認も了承されることになるだろう。

第79回
たった今(5月27日午後4時)、麻生首相と鳩山代表による初の党首討論が終わった。筆者は、討論の行なわれた参議院内にいながら、言い難い虚脱感に包まれている。その理由は麻生首相の側にある。
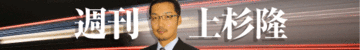
第78回
「日本型インフルエンザ」が大流行している。別名「マスコミ感冒」。先々週、筆者が今後の日本国内のパニックを予測して勝手に名付けたものだ。案の定、今週、そのインフルエンザは日本列島をパニックに陥れている。
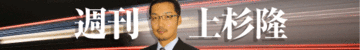
第77回
小沢代表は自らの辞任によって強烈なボールを麻生首相に投げ返し、攻守逆転に成功した。ところがである。せっかくのそうした戦術も、翌日には完全に無意味なものとなった。その理由は、代表選のスケジュール設定にある。
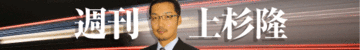
第76回
ダイヤモンド・オンラインの読者ならばすでにご存知だろう。これまでも筆者は、麻生首相が解散を決意するには、3つの前提条件が揃うことが必要だと繰り返し述べてきた。
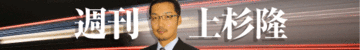
第75回
『諸君!』5月号の巻頭鼎談は出色であった。保守の意味、その歴史的な役割、真の保守とはを遠慮なく論じている。とりわけ櫻井よしこ氏と櫻田淳氏の「保守論争」は読む者を興奮させるものであった。
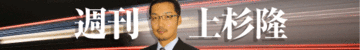
第74回
再び、大連立の「亡霊」が蘇ってきたようだ。大連立騒動の「フィクサー」となって中心的役割を演じたのが渡辺恒雄・読売新聞主筆や中曽根康弘元首相であった。4月10日講演会で渡辺氏は自らの政治的欲求を告白した。
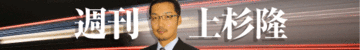
第73回
〈ゴルフは米国に渡って悪くなり、日本に行って最悪になった〉これは英国のゴルファーたちが秘かに囁いている言葉である。ゴルフ競技に対する米国人の振る舞い、日本人の無理解がこうした評判を作りだしたのだろう。
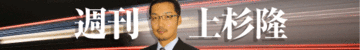
第72回
昨日、自民党の勉強会に呼ばれた。内容は、世襲制度の禁止について、筆者に話をしてくれというもの。二世政治家が少なくない自民党でのこうした動きは、これまでにはなかったと記憶している。
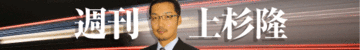
第71回
3月24日は、日本の政治ジャーナリズムにとっては記念すべき日となった。この夜、公設秘書の起訴を受けて、小沢一郎民主党代表が記者会見を行なった。3月3日の逮捕以来、4週連続の会見となる。
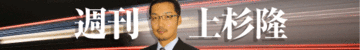
第70回
ワールドベースボールクラシック(WBC)が盛り上がっている。しかし小学校6年間、寝食を忘れるほどの野球少年だった筆者は、どうしても興奮できない。その原因のひとつは興ざめな組み合わせルールにある。
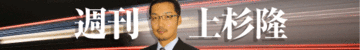
第69回
漆間巌・内閣官房副長官のオフレコ懇談が話題になっている。今回論じるのは、漆間氏の発言そのものではなく、彼を取り巻く記者クラブメディアのオフレコ懇談への対応の酷さだ。
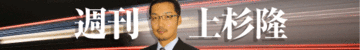
第68回
きのう(3月3日)、民主党の小沢一郎代表の会計責任者の公設第一秘書が逮捕された。小沢氏には、公党の代表として、説明責任が生じると同時に、進んで捜査に協力し、自らの疑いを晴らす義務も生じる。
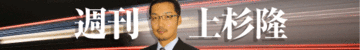
第67回
日米首脳会談が終わった。またしても日本政府は「片想い外交」で悦に入っているようだ。なぜ日本の首相がホワイトハウスに呼びつけられたことが、そんなにも誇らしいのだろうか、まったく理解ができない。
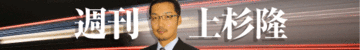
第66回
中川昭一財務・金融大臣が辞任した。未曾有の金融危機を受けてのローマG7で、前代未聞の「醜態」を演じることになったのだ。それが、日本の国益と信頼を著しく毀損するものになったことは疑いようがない。
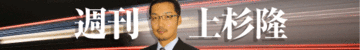
第65回
昨年末から、石川遼を追い続けている。埼玉、茨城、東京と、彼の現れる場所には可能な限り駆けつけるようにした。そして、きのう(2月10日)も、栃木県・鬼怒川高原でのスキー合宿に、彼の姿を追いかけた。
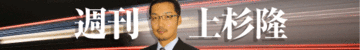
第64回
衆議院予算委員会が開かれている。麻生政権にとっては、通常国会での初めての本格的な論戦のスタートとなる。とかく政策論争がないとマスコミに批判されがちの国会審議だが、果たして本当にそうなのか?
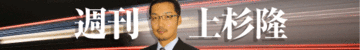
第63回
二次補正予算の成立によって、ようやく争点となっていた定額給付金も法制化された。だが、執行するにはまだ関連法案の成立が必要だ。仮に、野党が国会で抵抗すれば、その分だけ支給は遅れるだろう。
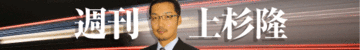
第62回
バラク・オバマ大統領が正式に誕生した。1月20日、ワシントンでは大統領就任式が開かれ、200万人とも言われる聴衆が詰め掛けた。その人数が一箇所に集まり、ひとりの男のスピーチに耳を傾けたのだ。
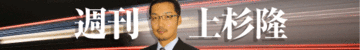
第61回
前回のコラムについて、多くの反応があった。寄せられた反論については、それなりに納得できるものもあれば、まったくの的外れのものもある。誠実な指摘に対しては、筆者なりの回答を試みたいと思う。