
深田晶恵
第7回
老後資金が3000万円あっても毎月使える金額は6万6000円!?
「下流老人」になる分かれ目はどこか? 消費税増税、社会保険の負担増、教育費の高騰などで貯金が少ない40代、50代。今の日本人の平均寿命は83歳で、60歳定年から平均で23年もある。老後年収200万円で20年以上安心して暮らすためには、老後のお金の現状を知っておくべきである。

第6回
国や自治体の制度を知らないと下流老人になりやすい
「下流老人」になる分かれ目はどこか? 消費税増税、社会保険の負担増、教育費の高騰などで貯金が少ない40代、50代。今の日本人の平均寿命は83歳で、60歳定年から平均で23年もある。老後年収200万円で20年以上安心して暮らすためには、老後のお金の現状を知っておくべきである。
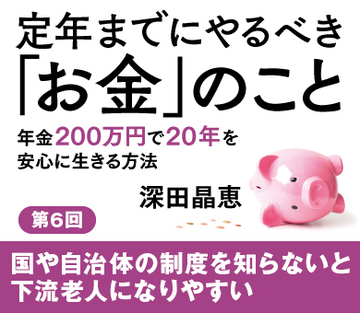
第5回
手取りの年金収入が、16年で32万円も減!
消費税増税、社会保険の負担増、教育費の高騰などで貯金が少ない40代、50代。「何とかなるだろう」では生き残れない。今の日本人の平均寿命83歳で、60歳定年から平均で23年もある。老後年収200万円で20年以上安心して暮らすためには、老後のお金の現状を知っておくべきである。40~50代の貯金が不足するのはなぜか?その原因を探る!
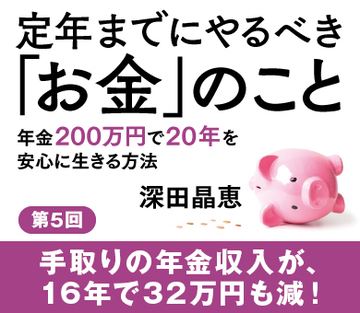
第4回
今の40、50代、定年後の生活は、500万円以上ダウンする!
消費税増税、社会保険の負担増、教育費の高騰などで貯金が少ない40代、50代。今の日本人の平均寿命83歳で、60歳定年から平均で23年もあるのをご存じだろうか。貯金が少ないこの世代こそ、老後のお金の現状を知って、今から対策を講じなければ、悲惨な老後になってしまう。40~50代の貯金が不足するのはなぜか?その原因を探る!

第38回
前回は熊本地震で被災された方や離れて住む家族の方たち向けに、「現金引き出し」「住宅ローン返済」「り災証明書」の3つについてお伝えしました。今回は、「クレジットカードの支払い」と「加入保険の請求手続き」についてお伝えします。

第3回
今の40~50代が抱えるお金が貯まらない「三重苦」
消費税増税、社会保険の負担増、教育費の高騰などで貯金が少ない40代、50代。今の日本人の平均寿命83歳で、60歳定年から平均で23年もあるのをご存じだろうか。貯金が少ないこの世代こそ、老後のお金の現状を知って、今から対策を講じなければ、悲惨な老後になってしまう。40~50代の貯金が不足するのはなぜか?その原因を探る!

第2回
定年後、年金200万円で20年以上暮らせる貯金があるか?
日本人の平均寿命83歳。60歳定年から平均で23年もあるのをご存じだろうか。消費税増税、社会保険の負担増、教育費の高騰などで貯金が少ない40代、50代。この世代こそ、老後のお金の現状を知って対策を講じなければ、悲惨な老後になってしまう!

第1回
老後はなんとかなる、と思ったあなたは「下流老人予備軍」
日本人の平均寿命83歳。60歳定年から平均で23年もあるのをご存じだろうか。消費税増税、社会保険の負担増、教育費の高騰などで貯金が少ない40代、50代。この世代こそ、老後のお金の現状を知って対策を講じなければ、悲惨な老後になってしまう!

第37回
熊本地震の被災者とご家族が、地震発生間もない今、最低限知っておきたい「身近なお金のこと」は3点。「現金引き出し」「住宅ローン返済」「り災証明書」です。

第36回
奨学金を利用する家庭が増えている。ある調査によると大学生の51.3%が奨学金を受給しているというが、奨学金といっても「貸与型」なら、返済義務のある借金だ。教育ローンなら「親が借りて、親が返すもの」だが、奨学金は「子どもが借りて、本人が返すもの」だ。

第35回
日銀の「マイナス金利導入」の影響を受けて住宅ローン金利が一段と下がっている。すでに住宅ローンを組んでいるなら、「ローンの借り換え」もしくは「金利交渉」で利息軽減を狙いたい。

第34回
確定申告のシーズンだ。医療費控除にまつわる「ありがちな思い込み・誤解」をまとめてみたので、昨年医療費が結構掛かかったと思う人はぜひご一読を。

第33回
日銀のマイナス金利政策の影響で、住宅ローン金利が史上最低水準を更新している。いま新規にローンを組んだり、住宅ローンの見直しをするなら、どの金利タイプを選ぶべきか。

第32回
「マイナス金利導入」の発表以降、新聞や雑誌等の記者から「住宅ローン金利はどうなりますか」という取材を多く受けるのだが、意外なことに金融や経済担当の記者でも住宅ローン金利の決まり方をご存じない人が少なくなかった。

第31回
毎年1月に「今年の手取り年収」を属性ごとに試算するのが私の恒例行事となっている。手取り年収とは、額面の年収(各種手当て込みの額)から所得税、住民税、社会保険料を差し引いた金額のこと。「可処分所得」とも言う。

第31回
結婚後の貯蓄は、夫婦それぞれ「自分の名義の口座」で貯めるのが原則だ。『夫婦のお金』として、いずれか一方の口座に片寄せして貯める方法は、いくつか弊害が発生するのでやめたほうがいい。

第30回
小学生の子どもが自転車事故を起こし、親が約1億円の損害賠償を命じられる事件があった。これ以降「自転車保険」が注目を集めているが、実は知らないうちに賠償リスクに備える保険に加入しているケースも多い。

第29回
前回、「貯蓄目標額を決めたとしても、不測の出費が発生することもある」と書いた。今回は、医療費はどの程度まで予測でき、不測の出費にはどんなものがあるのかを考えてみたい。

第28回
今回は「簡易キャッシュフロー表」を使って、「毎年○万円貯蓄していくと、60歳時点ではいくら老後資金が貯まっているのか」を試算してみよう。もし今の貯金のペースでは老後資金が貯まらない、と知ったら背筋がヒヤッとするはずだ。

第27回
今回は、定年後も続く住宅ローンが持つリスクについて考えてみたい。住宅ローンを持つ読者の方、次の質問に即答できるだろうか。(1)住宅ローンを完済する年齢はわかりますか?(2)60歳時の住宅ローン残高を知っていますか?
