
楠木 新
こんな学生を採用したら一発アウト!入社後「使えない!」と言われないために面接官が見るべきこと
「生き方や感情は顔つきに表れる」という楠木新さん。著述家として多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第4回は、顔から始まる第一印象について、企業内で起きている実情にアプローチします。

2024年度上半期に「ダイヤモンド・オンライン」で会員読者の反響が大きかった人気記事ベスト1をお届けします! 第1位はこちらの記事です。
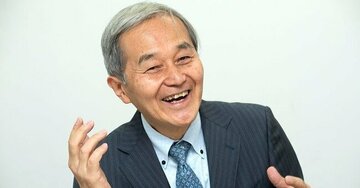
3
今日の面接うまくいった!と思ってもなかなか採用されない人の「顔」の共通点とは?
「生き方や感情は顔つきに表れる」という楠木新さん。著述家として多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。連載『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第3回は、人々の「顔」が持つ役割・機能について、独自の分析を試みます。

2024年度上半期に「ダイヤモンド・オンライン」で会員読者の反響が大きかった人気記事ベスト10をお届けします! 第8位はこちらの記事です。

2
顔を見れば一発で分かる!入社してから活躍する人がやっている「神習慣」
「生き方や感情は顔つきに現れる」という楠木新さん。著述家として多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第2回は、採用面接における「顔」の役割が、時代とともにどう変わってきたかをみていきます。これからの就活で大切な「シンプルで原始的」なこととは?

1
採用面接で面接官に「信頼される顔」と「信頼されない顔」の決定的な違い
「生き方や感情は顔つきに表れる」という楠木新さん。著述家として多くの人を取材し、さまざまな「顔」に接してきた経験から、いつしか「顔の研究」がライフワークになったと言います。『豊かな人生を送る「いい顔」の作り方』第1回は、楠木さんが企業で採用責任者を務めていた時代にさかのぼって「採用面接」における顔の役割を考察します。

2024年上半期に「ダイヤモンド・オンライン」で会員読者の反響が大きかった人気記事ベスト10をお届けします!第1位はこちらの記事です。(記事初出時の公開日:2024年6月10日)
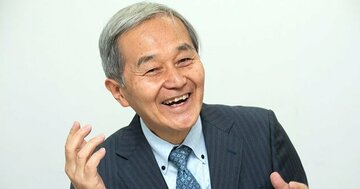
定年前後の500人以上にインタビューを重ねてきた楠木新さん。老後も「人に恵まれる人」と「孤立する人」では、顔を見れば一発でわかる決定的な「差」があるという。ジャーナリストの笹井恵里子さんが話を聞いた。

楠木新さんが定年前後の500人以上にインタビューをして判明した「老後に後悔したこと」のワースト3とは。ジャーナリストの笹井恵里子さんが話を聞いた。

定年前後の500人以上にインタビューを続けてきた楠木新さん。豊かな時間の使い方をする人もいれば、「このまま死ぬのは、やりきれない」と吐露する人もいたと言います。後悔する人の共通点とは何か、ジャーナリストの笹井恵里子さんが取材しました。

【『定年後』の著者・楠木新さんに聞く】定年後に備えて「もう一人の自分」を持つコツ
定年後も自分らしく生きるために、早いうちから「もう一人の自分」を発動させることを提唱するのは、25万部超のベストセラー『定年後 - 50歳からの生き方、終わり方』などの著書がある楠木新さん。果たして自分にそんなことが可能だろうか?「もう一人の自分」を見つけるコツについて、楠木さんの著書『定年準備 - 人生後半戦の助走と実践』より一部をご紹介する。

「定年後」は50歳から始まっている! と考えるべき理由【『定年後』の著者・楠木新さんに聞く】
忙しく働く現役世代の生活から一転、定年後にゆるやかな時間が流れるようになると、最初のうちこそ解放感を楽しめても、だんだん退屈になったり焦燥感が募ってきたりする。今のうちから定年生活をシミュレーションしてみてほしい。本記事では、定年した500名に取材してきた著述家、楠木新さんの25万部超のベストセラー『定年後 - 50歳からの生き方、終わり方』や『定年準備 - 人生後半戦の助走と実践』より一部をご紹介する。

春は人事の季節。社員は「栄転」「転勤」「出向」など、同僚や自分の異動の話でもちきりとなる。もちろん「左遷」で割を食ったと不満を持つ社員も出てしまう。左遷とは何か?なぜ左遷だと感じるのか?かつて大規模人事異動を担当した経験と、日本型雇用の特徴から読み解いてみよう。

老後の生活資金に不安を持つ人は少なくない。『定年後のお金』を上梓した楠木新氏は、老後の不安とお金の間には直接関係がないのではないかと問題提起した。今回は、証券会社の財産シミュレーションを受けた体験からさらに踏み込んで、老後のお金と不安についてのエッセンスを紹介する。

「人生100年時代」といわれるなか、老後の生活費への不安は大きい。昨年の金融審議会の報告書で「老後資金には2000万円が必要」という試算が公表され、大きなニュースになった。定年後に必要となるお金は今からどのように準備をしておけばいいのか。家計の管理方法や見直し、資産運用の基本的な考え方を学ぶ一方、本当にやりたいことに出費して人生を楽しむための生き方についても考えよう。

第10回
定年退職後に、何をすればいいか、何を張り合いにして生きればいいかがわからない、という人は少なくない。そんな時、「子どもの頃、好きだったこと」や「なりたかったもの」を思い出すと、展望が開けるかもしれない。

第9回
定年退職後、会社や組織、そして家族のために生きてきた日々をいったん終えると、あとはゴールを意識して自分らしく生きることができる毎日となる。自分は、自分の人生の主人公である。当たり前のようだが、現役時にはなかなか持ちえなかった意識を取り戻すチャンスであるともいえるのだ。

第8回
「定年後」の生活は、必ずしも事前に思い描いたようには運ばない。試行錯誤をしながらも、最後に戻るところは、「誰かの役に立つこと」、「自らの家族のところの戻ること」。2本の米国映画を題材に、あるべき定年後を考えてみよう。

第7回
定年後、人はどこで何をするのか。新たな仕事や、これといって趣味を持たない人は、どうやって時間をやり過ごすのか。フィールドワークを通して、定年退職者が多く集う場所がわかった。そして、そこにいる多くの人がみな「一人ぼっち」だった。

第6回
定年後、自由な時間を楽しめる人は幸せである。多くは、自由な時間を持て余し、やるべき何かを模索し始める。では、どのようなかたちで、社会とつながることができるだろうか。
