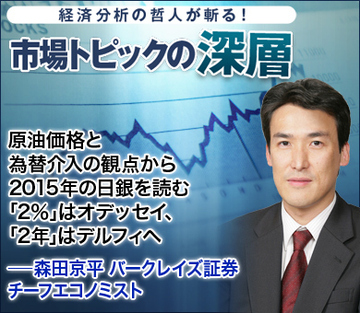高田 創
第210回
マイナス金利が止まらず、世界的に金利が未曾有の水準になっている。こうした状況の背景としては、底流を流れる状況にも目を向ける必要がある。それは、世界全体のバランスシート調整による構造要因である。

第208回
最近、伊勢志摩サミットを展望し、財政出動への期待が高まっている。そのなかでは、ドイツの反対をいかに抑えるかがカギを握っている。伊勢志摩サミットで日本はドイツを説得できるかも大きな課題だ。

第206回
円高不安の日本。米国は強い意志をもってドル安に向けた調整を行っている。アベノミクス開始以来の中期的な円安トレンドの転換は、まさしく「達磨さんが転んだ」の鬼の役目を果たす米国サイドの影響によるものだ。日本にとって試練の1年となる。

第203回
3月後半といえば、金融機関や企業が次年度の計画を策定する時期。今年はマイナス金利下、つまり「金利水没」という、前例のない局面だ。こうした状況下での資産運用は、「LED戦略」で行くしかない。

第200回
マイナス金利導入後、株安・円高と日銀の思惑とは逆に振れた要因には、米国経済の減速不安がある。世界での牽引役が不在のなか、マイナス金利政策は投資先消滅、通貨戦争と信用収縮のスパイラル化という危険性を持つ。

第197回
これまで筆者は、新興国の減速と先進国の回復という2016年の基本シナリオを抱いてきた。だがここにきて新たなリスクシナリオ“世界連鎖不況”の不安が浮上した。危機回避のために世界はどう対処すべきか。そして日本はどう動くのか。

第194回
世界の金利が「水没」するなか、利上げで米国に「運用難民」が押し寄せることになるだろう。一方、米国経済が減速することは許されない。今回の利上げは、誰もが体験したこともない遅いペースになり、金利上昇も限られるのではないか。

第188回
日本は1990年代のバブル崩壊後、バランスシート調整に20年かかった。2007年以降、欧米で同様のことが生じ、調整に10年単位を要している。今度は中国がこれに直面しているのではないか。だとすれば全治には5年近くはかかるだろう。

第185回
今回の市場の調整は、金融市場だけでなく中国の実体経済不安も含むために、その深刻度は重い。新興国から先進国への牽引役の交代という「端境期」で、今後も市場変動をある程度覚悟する必要がある。シートベルト着用サインの点灯だ。

第182回
足元の市場は大揺れだが、米国利上げは近づいている。市場参加者が利上げにおびえるのは過去の体験によるが、1970年より前と後で利上げに対する市場の反応は大きく異なる。現状は、大半の市場参加者が未体験の70年以前に類似する。

第179回
日本で1980年代以降の利上げ局面は3回しかなく、それぞれ債券市場のショックが前触れだった。今年から来年に向けた債券市場の重要なテーマは、市場が先取りして生じ得る変動の予兆を捉えることにある。

第176回
日銀の大量買い入れにより、国債の「官製相場」が続くなか、財政規律への不安は残存するものの、日本国債の暴落不安を生じさせる「悪い金利上昇」は生じにくくなった。今後の課題は、不可避的に生じ得る「良い金利上昇」にいかに向き合うかだ。

第175回
5月決定会合における日銀の景気判断の上方修正、6月10日の為替に対する黒田総裁の発言などを勘案すると、今後日銀が「量的」な追加緩和を行う可能性は低いと見られる。その代わりに日銀が向かうのは、「質的」な追加緩和だと筆者は見ている。

第173回
自国通貨安が経常収支を改善させ、自国通貨高が経常収支のマイナス要因であるとすれば、今日の環境は、経常黒字国の黒字をますます拡大させ、経常赤字をますます拡大させる不均衡拡大である。その状況をつくり出したのが、各国の「金利水没」までもたらす金融緩和だ。
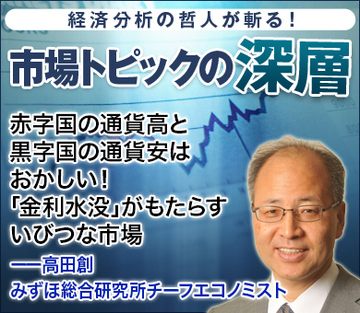
第171回
毎年6月に「日本再興戦略」が更新され、安倍政権の成長戦略が描き直される。ただ、当初抱いていた期待感の大きさと比べると、かなり色褪せてしまった感は否めない。改革を加速する突破口である「国家戦略特区」の運用状況について振り返りたい。

4月に日経平均株価が、15年ぶりに一時的ながら2万円を回復したことが話題になった。現在の株価は「バブル状態」にあるのだろうか。それとも、まだ回復の途上にあるのか。世界における日本株の相対的な立ち位置を考えながら、株価の水準を考察する。

第167回
今日の異例な世界経済の状況を象徴する2大現象は、原油価格暴落と世界の金利「水没」という状況だ。先進国の需給ギャップは2、足元に至るまで大幅なマイナスを抱えている。各国は財政拡大を含め、各国が独自に需要をつくり上げることはできるか。

第164回
日本経済は、2014年10~12月期のGDPが3四半期ぶりのプラス成長になり、2015年にかけて予想以上に見通しが改善しやすい状況だ。しかし世界経済は足踏み状態で、米国の回復に過度に依存する状況が続く。世界が頼りにする米国の「不確実性」とは何か。
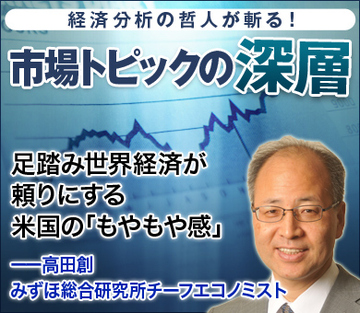
第161回
スイス中銀のマイナス金利策、ECBの量的緩和策が実施され、日本を含む世界中に「金利水没マップ」が広がっている。今後も水没地域が拡大する可能性は高いが、それは債券市場の死を意味する。金融機関は、新たな運用機会を創出できるのか。
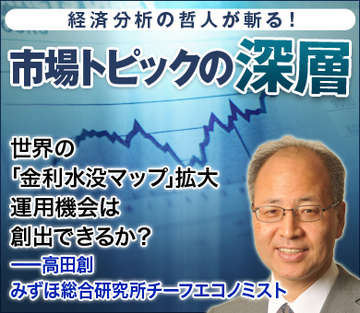
第160回
日銀が量的・質的金融緩和を始めて、間もなく2年が経つなか、原油価格の下落には歯止めがかからない。日銀の物価見通しについては、前提となる原油価格や為替の水準は公表されていない。2014、15年度のコアCPI見通しの下方修正は必至と見られるが、日銀はどう動くのか。