ダイヤモンド社出版編集部
GPT時代の変革を支えるデータマネジメント〈PR〉
ChatGPTを公開されてから約2年半が経つ。登場当初の「会話ができるAI」という驚きは、「業務を担うAI」へと改められ、文書やプログラムの作成、データ解析、意思決定支援など、多様な業務に活用されている。もはやAI技術の活用が、企業の競争力と持続的な成長に不可欠であることは自明である。とりわけ注視すべきは、AI技術の革新が加速度的に進んでいる点だ。すでに現代版産業革命の只中におり、ここ数年ほどの間に、先行企業と様子見を決め込んだ企業との間で、埋めがたい差が生まれる可能性が高い。ホワイトカラーの仕事や求められるスキルセットも、今後大きく塗り替えられていくはずだ。書籍『GPT時代の企業革新』」では、こうした現場をふまえて、Ridgelinez株式会社の野村昌弘氏を中心とする執筆陣が、GPTをはじめとするAI技術の進展および企業への導入にあたり、人の役割や組織形態、ビジネスモデル、経営戦略をどのように変革していくかについて詳述している。本連載の第3回では、AIの進化に不可欠であり、イノベーションのカギともなる新たなデータマネジメントについて読み解く。
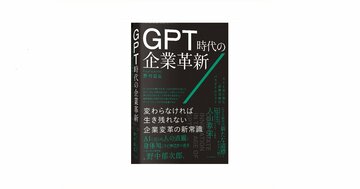
AIシステムが再定義する人間の役割と組織の形〈PR〉
ChatGPTを公開されてから約2年半が経つ。登場当初の「会話ができるAI」という驚きは、「業務を担うAI」へと改められ、文書やプログラムの作成、データ解析、意思決定支援など、多様な業務に活用されている。もはやAI技術の活用が、企業の競争力と持続的な成長に不可欠であることは自明である。とりわけ注視すべきは、AI技術の革新が加速度的に進んでいる点だ。すでに現代版産業革命の只中におり、ここ数年ほどの間に、先行企業と様子見を決め込んだ企業との間で、埋めがたい差が生まれる可能性が高い。ホワイトカラーの仕事や求められるスキルセットも、今後大きく塗り替えられていくはずだ。書籍『GPT時代の企業革新』」では、こうした現場をふまえて、Ridgelinez株式会社の野村昌弘氏を中心とする執筆陣が、GPTをはじめとするAI技術の進展および企業への導入にあたり、人の役割や組織形態、ビジネスモデル、経営戦略をどのように変革していくかについて詳述している
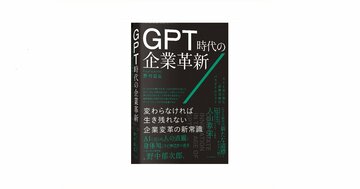
GPTが変える仕事と組織の未来〈PR〉
ChatGPTの登場は、専門的なスキルを習得していなくても幅広い領域で利用可能という点で生成AIの世界に劇的な変化をもたらした。生成AIの登場で多くの職種で仕事の進め方が大きく変わり、その影響力は産業革命にも匹敵すると考えられている。ホワイトカラーを含めたすべての職業がその役割を大きく変え、組織の形態も変わることになる。
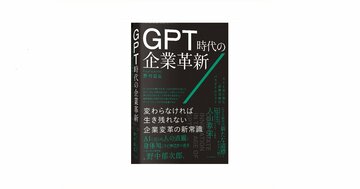
証券会社会長が教える「欧州の富裕層が米国債で資産運用する」理由〈PR〉
物価はこの2年ほどで急激に上がっているが、給与も年金も物価の上昇には追い付かない。金融機関に託しても1%にも満たない利率が続いている。では、どうすればいいか――。『資産防衛なら預金よりも米国債を買いなさい!』にヒントが書かれている。

ヒト・モノ・カネ・情報に次ぐ第5の経営資源「コミュニティ」とは
欧米を中心にこれまで当然とされてきた株主資本主義に代わって、「ステークホルダー資本主義」が広がりつつある。そこで注目されるのが、多様なステークホルダーとの接合点としての「コミュニティ」である。ヒト・モノ・カネ・情報に次ぐ第5の経営資源ともされるコミュニティとはどのようなものなのか。企業経営にどのように生かしていけばよいのか。2023年4月に発刊された『パワー・オブ・チェンジ』(ダイヤモンド社)で第3章のリードを担当したモニター デロイト、ディレクターの檀野正博氏と、同シニアマネジャーの井上発人氏の言葉から、その概要を紹介する。
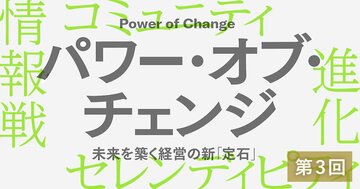
第2回
企業が自己変容を繰り返すために求められる「進化の素」
先行きが見通せない大転換の時代にあって、企業・組織も自己変革が求められている。しかし、それは言葉で言うほど簡単なことではない。2023年4月に発刊された『パワー・オブ・チェンジ』(ダイヤモンド社)では、既存の組織が自己変容を繰り返すための思考の軸を示し、その最深部に埋め込むべき「変革を駆動するカルチャー」として、3つの「進化の素」を紹介している。同書で第2章のリードを担当したデロイト トーマツ コンサルティング執行役員/パートナーの宮丸正人氏の言葉から、その概略を説明する。
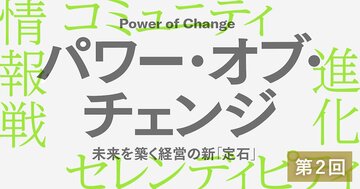
第1回
かつてない大きな変化に“踊らされている”状況からいかに脱却するか
「VUCAの時代」といわれて久しい。VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取ったものだが、この言葉が流行っているのは、企業や経営者が先を見通せずに苦しんでいる証左だ。結果として、かつてない大きな変化を前に呆然と立ちすくみ、対応に追われるばかりになっているのではないか。企業として生き残るには、変化を先取りする、あるいはみずから変化を起こしていくことが求められる。しかしその前に、現実に起きている変化の実像を正しくとらえる必要がある。そのためには何をなすべきか。2023年4月に発刊された『パワー・オブ・チェンジ』(ダイヤモンド社)で第1章リードを担当したデロイト トーマツ コンサルティング執行役員/パートナーの邉見伸弘氏の言葉から、そのヒントを探る。
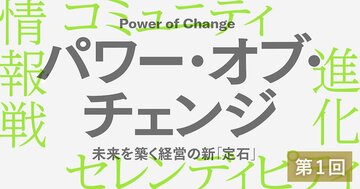
一度は「終わった人」になったのかと思われたトランプだが、ジャーナリストの横田増生氏は「米国でのトランプ人気は決して衰えたとは言えない。場合によっては、2024年の大統領選で返り咲く可能性もある」と指摘する。

第5回
企業経営にサステナビリティの視点を組み込むために、何から着手すればよいのか
企業経営において、SDGsに代表される「サステナビリティ」に大きな注目が集まっている。そこでよく聞かれるのが、「片手間ではなく、サステナビリティを本業に組み込むべき」という主張だ。しかし、これまで意識してこなかったものをいきなり経営の本流に持ち込むのは容易ではない。その実現のために重要な視点となるのが、本連載の第2回、第3回でも取り上げた「パーパス」だ。パーパスの視点からサステナビリティ経営をどのように実現していけばよいのか、最近発刊された『パワー・オブ・トラスト』(ダイヤモンド社)から引用して紹介する。

第4回
グローバルレベルでの不確実性の高まりに、サプライチェーンはどのように再構築するべきなのか
今年2月24日に始まったロシア軍によるウクライナ侵攻は、いまだ終息の気配が見えない。「まさか21世紀にもなって、このような戦争が起こるなんて」と驚いた人も少なくないだろう。経済的な視点では、グローバルに広がっていたサプライチェーンが大きな混乱状態に陥ってしまっている。しかし、今回のような突発的な有事というのは、近年世界中で高まっている“不確実性”の一側面にすぎない。グローバルレベルで起きている変化に対応するために、サプライチェーンはどのように再構築するべきなのか。最近発刊された『パワー・オブ・トラスト』(ダイヤモンド社)から引用して紹介する。

第3回
大企業のイノベーションがなぜうまくいかないのか。「パーパス」視点で考えてわかったこと
これまでに経験したことのないような大きな変化に直面し、企業経営はどのように対応していけばよいのか。その解決策を「信頼(トラスト)」を軸に読み解いていく本企画。連載第2回では、最近注目されている「パーパス」の本質とメリットについて解説した。従来の「ミッション」「ビジョン」「バリュー」との最大の違いは、他ではない自社が存在する理由を突き詰めており、それが変革の礎になりうるということだ。第3回では、この変革の手法について、『パワー・オブ・トラスト』(ダイヤモンド社)から引用して紹介する。

第2回
新たな時代に突入する企業経営。そこで「パーパス」はどのような意味をもってくるのか
最近「パーパス(purpose)」という言葉をよく見かけないだろうか。2000年代前半から欧州企業などで語られ始め、日本でもここ数年パーパスを題材にした書籍が多数刊行されている。国内メディアでパーパスを取り上げた記事掲載数を見ても、19年以降急激に増加傾向であり、パーパスブームともいえる。このパーパスとは何なのだろうか。パーパスを策定することで企業にはどのようなメリットがあるのか。その背景にある時代の流れと合わせて、最近発刊された『パワー・オブ・トラスト』(ダイヤモンド社)から引用して紹介する。

第1回
【事例:逗子市デマンド型乗合タクシーサービス】人も街も年老いていく。持続可能な事業モデルをどう構築するか
コロナ禍を引き合いに出すまでもなく、世界はこれまでに体験したことのないよう大きな変化に直面している。企業は、そうした変化に対応して事業の在り方を変えていくことが求められている。日本国内に限っていえば、もう一つの変化・傾向が見逃せない。1990年代から指摘されている「少子高齢化」の問題だ。近年のさまざまな変化と相まって、その内実はより複雑になってきている。ここでは、それに伴い表出した課題の解決に取り組んでいる逗子市の事例を、最近発刊された『パワー・オブ・トラスト』(ダイヤモンド社)から引用して紹介する。

斜陽産業の家業を継げ、と言われたらどうするか。創業60年の実家、南福岡自動車学校の事業承継と経営の立て直しをした経験をまとめた『スーツを脱げ、タイツを着ろ!』(ダイヤモンド社)を上梓した江上喜朗氏と、ヒルズ族から監獄行きを経験し、現在も実業家として手腕を発揮する堀江貴文氏との対談をお送りする。
