
関 辰一
中国では、顕在化していない不良債権(潜在不良債権)が増加している。中国全体の潜在不良債権を試算すると、2022年央で19.7兆元(約400兆円)と、GDPの16.9%に相当する。一方、中国政府が公表する不良債権統計では、2022年央の商業銀行の不良債権は3.0兆元(約61兆円)にすぎない。業種別の上場企業・潜在不良債権額から、不良債権が発生した理由を考察し、三選を果たした習近平国家主席のもと、今後の中国不良債権額の行方を見据える。

中国では、地方政府の債務が大幅に増加している。中でも問題視されているのが、地方政府が抱える「隠れ債務」だ。隠れ債務を考慮すると、多くの地域で債務比率は警戒ラインに達しているとみられる。地方の隠れ債務の実態は、中国政府(国)ですら全容を把握しきれていないとされる。中国地方政府が抱える隠れ債務の実態や政府による隠れ債務への対応方針を明快に解説する。

1~3月期の中国実質GDPは、上海市をはじめ多くの都市で経済活動が厳しく制限されたことから、前期比年率+5.3%と前期から鈍化した。しかし5月以降、多くの都市で活動制限の緩和が進み、景気下押し圧力は和らいでいる。最新の経済指標から中国景気の現状を整理し、今後の中国経済が持ち直しに向かう背景を解説する。最後に中国景気の重石となりかねない「3つのリスク」を詳述する。

中国のゼロコロナ政策は、新型コロナウイルスの感染が収束するまで継続するとみられる。ゼロコロナ政策による中国内の工場の稼働停止や港湾の処理能力低下といった供給面の影響だけでなく、消費活動の低迷といった需要面の影響にも注意する必要がある。政府は今年の成長率目標を「5.5%前後」に設定したものの、ゼロコロナ政策を続けるなかでは目標達成は難しいと考えられる。

中国の7-9月期・実質GDPは、前期比年率+0.8%と前期の+4.9%から大幅に減速した。成長率が鈍化した背景には、電力や半導体の不足に加え、新型コロナ対応のための行動制限の強化などがあげられる。中国経済のエコノミストが、中国景気が減速した要因を整理し、今後の見通しや景気下振れリスクを大胆に指摘する。

中国大手不動産の恒大集団が資金繰り難から経営危機に直面するなど、中国の不動産市場への警戒感が強まっている。主要70都市の新築住宅平均価格は上昇ペースが鈍化しており、価格が下落に転じた都市の数も増えている。中国出身のエコノミストが、不動産市場に対する懸念が強まった背景を整理するとともに、中国不動産市場が深刻な調整を回避できる4つの理由を明快に提示する。

中国の2021 年4~6 月期の実質GDPは、前期比年率+5.3%と前期の同+1.6%から加速した。春先以降、新型コロナの感染者数が低水準となり、政府が活動制限を緩和したため、中国経済は堅調さを取り戻している。足元の中国経済の様子を個人消費、固定資産投資など需要項目別に整理し、今年と来年の中国GDP成長率を大胆に見通す。

中国で「バイデン政権の対中通商政策:見通しと提言」と題したオンライン・シンポジウムが開催された。本シンポジウムにて中国現地のエコノミストたちは、米中間での過度な対立は米国の利益も阻害すると指摘するなど、本シンポジウムの内容は中国現地の有識者・当局者の考えを考察するうえで有用な情報が多く含まれている。シンポジウムの内容を明快に整理するとともに、中国現地の有識者・当局者の考えに潜む危うさを鋭く指摘する。

中国の2020年10~12月期の実質GDP成長率は、前年同期比+6.5%と、5%程度とみられる潜在成長率を上回る高成長となった。中国の国有企業は、コロナ禍から早期の景気回復を狙う政府の意向を受け、設備投資を急ピッチで拡大している。輸出も大方の想定以上のペースで伸びており、高級車や不動産では過熱感が強い。今後の中国経済を家計部門と企業部門から考察し、過熱感すらある中国景気の今年の成長率を占う。

中国の重要会議「5中全会」が10月29日に閉幕した。ここで議論された2021~35年の政策運営方針は、長期的な中国経済の行方を左右するが、難解な言い回しも数多く、5中全会で示された方針を読み解くことは難しい。中国経済ウォッチャーの第一人者が、5中全会の期間中に公表された様々な文献や発言を総括し、習近平が目指す中長期の中国経済の姿や、中国の「新」発展モデルの内容を考察する。
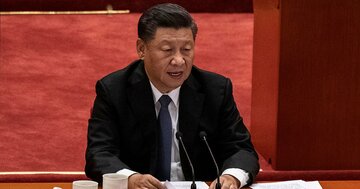
コロナ禍を経て世界に先駆け経済活動を再開した中国では、政府主導で景気回復が続いている。ただしそのペースは、夏場までの急回復から鈍化する見込みだ。その原因を個人消費、企業投資、金融政策の3つの観点から考察し、今年後半の中国景気の行方を探る。

中国の次期(第14次)5カ年計画(2021~2025年)の草案は、中央委員会第5回全体会議(5中全会)で10月に発表される見込みである。中国を取り巻く環境が大きく変化するなか、習近平政権が次期計画において、どのような方針を打ち出すかが注目される。前回(2016~2020年)計画で示された「産業の高度化」「一帯一路」「共産党の指導強化」の3つのポイントを中心に、次期計画で示されるであろう方針案を考察する。

中国人民銀行は、デジタル人民元の試験運用を中国の5地域で進めていることを明らかにした。今後も実験は続くだろう。ただ、中央銀行が発行するデジタル通貨を全国に展開することは容易ではない。セキュリティ、金融仲介機能に配慮が求められる。当局の発表や各種報道から、デジタル人民元の姿を浮き彫りにし、デジタル人民元の今後の注目点を紹介する。

中国の1~3月期の実質GDPは、前期比年率▲34%(前年同期比では▲6.8%)と大幅に減少した。中国の実質GDPが前年比マイナスとなったのは、四半期ベースでの統計が始まった1992年以降、初めてである。中国経済はV字回復できるのだろうか。中国政府が実施する経済対策などから、今後の景気の行方を見通す。

デジタル人民元の発行に向けた動きは着実に進んでいる。中国人民銀行は1月、「法定デジタル通貨の全体的な設計、規格の標準化、影響の研究、複数機関による調査実験が基本的に完了した」と公表した。デジタル人民元の発行はそう遠くなく、早ければ年内にもデジタル人民元は発行される見込みである。中国政府がデジタル人民元を発行する狙いを解説する。

中国経済は、米国との貿易摩擦が重石となる一方、政府による景気対策が下支えとなり6%台の成長を続けている。しかしながら、中国経済が抱える深刻な構造問題も見落としてはならない。所得格差や環境汚染も大きな問題だが、筆者が最も注目しているのは、2つの大きな構造問題である。それらを俯瞰し、解決策を考察する。

実質GDP成長率が前年比+6.0%まで鈍化するなど、中国景気の減速感が強まっている。しかし、米中貿易摩擦による景気への影響は、当初懸念されたほど大きなダメージにはなっていないようだ。足元では景気底入れの動きも見え始めている。そんななか、中国政府は昨年から矢継ぎ早に景気対策を講じているものの、いずれも小粒だ。景気対策は本格化するのだろうか。

米中間の関税をめぐる制裁と報復の応酬が再開しそうだ。加えて、米国政府は中国を「為替操作国」に認定し、先行き対中関税を最大45%まで上げる要件を整えた。米トランプ政権の関税引き上げは、世界経済にとってマイナス要因であることには間違いない。しかしながら筆者は、米国の動きが中国経済や世界経済に大きな悪影響を及ぼすことはないとみている。

米中通商協議は7月29日、上海で再開されることになったが、これは必ずしも米中新冷戦の終わりを意味しない。米中覇権争いには、中国の経済成長、中国政府による積極的な外交政策、安全保障面において中国が米国にとって大きな脅威となっている、といった背景がある。こうした背景が今後、大きく変わることは考えにくく、米中の覇権争いは始まったばかりと言える。いずれ米中間で制裁と報復の応酬が再開するリスクは払拭できない。

中国景気は、輸出、投資、消費のいずれも増勢が鈍化しており、とりわけ地方経済が厳しい状況に陥っている。デレバレッジ政策を背景にインフラ投資が見直されており、インフラ投資の依存度が高い地域は深刻な不況に陥っている。政府が景気対策に本腰を入れる一方、米トランプ政権の追加関税発動の不安もある中国経済は、これからどうなるのか。
