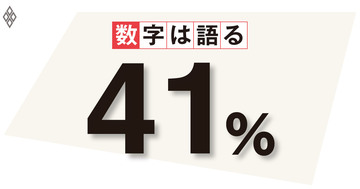須田美矢子
日本銀行は2%の物価安定目標の達成を見通せずにいるが、目標の変更は考えていない。2%はグローバルスタンダードであり、それを目指すことが長い目で見た為替レートの安定に資するから、というのだ。その背景には購買力平価説がある。

日米欧の金融緩和・低金利が長引く中、リスク資産にバブル的な過熱が見られる。これが金融システムを不安定化させると経済物価に大きな影響が及ぶ。金融政策運営では、金融緩和・低金利の長期化がもたらす副作用に留意が必要だ。

最新の日本銀行の物価見通しは2023年度でも1%で、目標の2%には程遠く、ゼロ%以下の政策金利が今後もかなり続きそうだ。低金利の長期化は、金融システムや金融市場を不安定化させる可能性があり、それを通じた経済物価への悪影響には留意が必要だ。

主要中央銀行はこれまで消費者物価上昇率2%の目標未達に苦しんできた。だがここにきて、米国では、大型財政支出が決まり、コロナワクチンの接種が進む中、市場のインフレ予想が急伸し、FRB(米連邦準備制度理事会)の想定よりも金融引き締めが早まるとの見方が増えた。

米ドルは昨年、新型コロナウイルス感染症の拡大で市場がリスク回避的になり、4月に実効為替レートで見て統計公表(1994年)以来の最高値を付けた。

日本銀行の金融システムレポートには、金融活動の過熱による金融面の不均衡を早期に把握するためのヒートマップがある。10月号ではマネーストックM2成長率の項目に赤が点灯した。ただ、M2の最近の顕著な伸びは、給付金や実質無利子融資など、新型コロナ禍対策の結果であり、この赤はバブル期のような金融活動の過熱感を表すものではないとの評価だ。とはいえ、この急増は無視できない。

米連邦公開市場委員会(FOMC)は、2%の物価目標未達の下、議論を重ねた結果、物価目標2%の設定時(2012年1月)に採用した声明を今年8月に大きく見直した。物価については、長期インフレ予想を2%に留め置く重要性は変わらずだが、物価の実績値のそれへの影響を重視し、(過去の未達分を含め)一定期間で平均2%のインフレの実現を目指すことにした。

新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言の解除を経て、日本経済は最悪期を脱したようだ。ただ、日本銀行の見通しによると、コロナ危機前の水準に戻るのに2年はかかる。コア消費者物価(生鮮食品を除く総合指数)は、今年度下落の後に上昇に転じるが、来年度はわずか0.3%だ。下振れリスクが大きいので、デフレ(2年連続物価下落)の可能性を排除できない。

新型コロナウイルス感染症拡大による経済活動の停止は運転資金など資金需要を急増させた。

新型コロナ感染症の世界的な大流行の下、企業は生産停止に追い込まれ、人々は感染リスクに加え、マスクなどの物不足、収入消失や失業懸念もあり、不安感を強めている。

政策当局者の「円高のみ容認しない」姿勢が引き起こすリスク
昨年のドル円レートは112円台と104円台の間を上下し、その差7.78円はこれまでで最小となった。日米欧の中央銀行は年内の政策金利の変更を示唆しておらず、市場では、今年のドル円レートも安定的で狭い範囲となるとの見方が多い。

いずれ問題を引き起こす、「オーバーシュート型コミットメント」の再考を
金融政策の限界論が内外で高まる中、物価目標の達成・維持への信認は低下しており、米欧の中央銀行は金融政策の見直しに取り組み始めた。日本銀行は2016年9月に枠組みを変えたが、その一つの柱である「オーバーシュート型コミットメント(消費者物価上昇率の実績値が安定的に物価目標を超えるまで、通貨供給量の拡大を継続)」に、市場関係者などから再考を促す声が上がっている。

物価上昇率2%、到達時期を示さない日銀の姿勢に問題あり
日本銀行は、2016年1月のマイナス金利導入後、中長期的な予想物価上昇率が弱含む中、「総括的な検証」を経て、同年9月に長短金利操作付き量的・質的金融緩和を採用した。予想物価上昇率を引き上げる新たな方策も決めたが、中長期的な予想物価上昇率の高まりは後ずれし、横ばい圏内のままだ。

国際経済による下振れリスク、過剰な保険は行き過ぎる緩和を招く恐れも
注目の9月の金融政策は、ユーロ圏・米国は追加緩和、日本は現状維持だったが、経済物価の情勢判断には共通点が相当見られた。雇用・消費は良いが、世界経済の減速や貿易摩擦の影響で輸出・生産は弱めで、物価は目標に届かず、貿易政策とそれを巡る不確実性による下振れリスクが大きいといった点だ。

生活設計を考える金融リテラシーがないと将来不安は軽減しない
アベノミクスの下、実質家計消費の伸びは2018年度までの6年間で2.1%でしかないが、この背景には日本の成長力が弱く、社会保障制度の将来像が示されず、将来不安が拭えないことがある。それには、金融リテラシーの不足も影響していると思われる。

経済活動への効果が薄い異次元金融緩和財政政策との連携は継続
黒田東彦・日本銀行総裁は、6月20日の記者会見で、「物価目標に向けたモメンタムが損なわれるようなことがあれば、ちゅうちょなく追加緩和を検討する」と述べた。米国やユーロ圏でも、貿易摩擦など国際経済を巡る不確実性を背景に、緩和バイアスを急速に強めており、それに呼応した動きといえる。だが、日銀には、もはや効果のある追加緩和策はほとんど残っていない。

労働力率の低下で生産性向上が課題規制の抜本的見直しも必要
人手不足と長く好況が続いたにもかかわらず、賃金や物価に加速感は見られない。政府は「デフレではない状況」とはいうが、デフレ脱却宣言には至っていない。というのは、「再びデフレに戻る見込みがない」との判断が必要なためだ。

中央銀行の物価目標に国民は関心が持てず予想インフレが上がらない
日本銀行が異次元緩和に乗り出して6年たつが、物価目標の到達までまだ遠い。見込み違いの要因は、物価は上がらないのが当たり前とする国民の物価の捉え方を、日銀の物価目標への期限付きのコミットで変えられるとみたことにある。