永吉泰貴
#6
1990年代末にMBO(経営陣による企業買収)を実施し、再上場後も貴金属めっきの高い技術力で存在感を放つ日本高純度化学。しかし今、その経営を長年支配した渡辺雅夫取締役相談役こそが業績低迷の最大要因だとして、投資ファンドのひびき・パース・アドバイザーズが渡辺氏の人間関係までを追及する異例の公開キャンペーンに踏み切ることが分かった。ダルトン・インベストメンツ東京子会社の元社長であるファンド代表を直撃し、フジテレビの“日枝帝国”とよく似た権力構造の実態を激白する。

金利上昇を追い風に、2025年3月期の銀行業界では収益回復がいっそう鮮明になった。そんな中で注目を集める指標の一つが、経営効率を示す経費率だ。そこで、メガバンクから地銀、第二地銀まで全103行を対象に最新の経費率を集計。前年からの改善や悪化も可視化し、ベスト&ワースト1位の銀行を明らかにする。

新興のスモールキャップPEファンド、マラトンキャピタルパートナーズが、外資系大手に匹敵する異例の高報酬制度を導入していることがダイヤモンド編集部の取材で分かった。マラトンの職位別給与レンジを実額で初公開するとともに、潤沢なキャリー(成功報酬)を生む仕組みと、現場メンバーに手厚く還元される配分制度の全容を明かす。
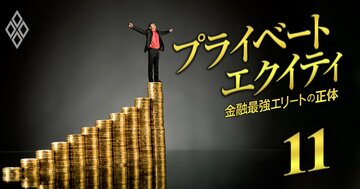
#5
株主総会で経営陣の命運を左右するのは、業績や取締役構成だけではない。不祥事に対する機関投資家の視線が、かつてなく厳しさを増している。そこで機関投資家によって不祥事認定された上場企業を集計し、ランキングを作成。不祥事の内容と認定数の多さから、不祥事認定されやすい5つのパターンが浮かび上がった。

#15
裁量が大きく、高報酬で知られるプライベートエクイティ(PE)ファンド。そんな華やかなイメージの一方で、週5日の地方出張や“席の空き”次第で決まる昇進など、意外な現実もある。匿名座談会・後編では、現役社員がリアルな年収水準、起業やCFO(最高財務責任者)転身などキャリアの悩み、実力主義に見えて実は運要素の大きい昇進構造を率直に語る。
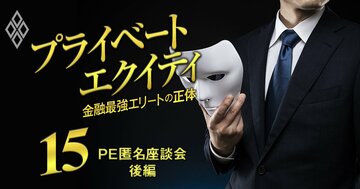
#14
プライベートエクイティ(PE)ファンドの仕事は、企業を買って終わりではない。むしろ、ミッド・スモールキャップファンドにとっての本当の勝負は、その後の企業変革にある。匿名座談会・中編では、現役PEファンド社員たちが中小企業の現場で信頼を築く過程と、そこで直面する失敗や試行錯誤の日々を赤裸々に語る。
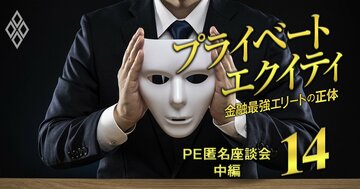
#13
狭き門故に働く人の数が限られ、実態が見えにくいプライベートエクイティ(PE)業界。だが今、コンサルティングや総合商社人材の多くが現実的に目指しているのは、就職難易度が高いラージキャップよりも、中小企業に投資するミッド・スモール(中小型)キャップのファンドだ。なぜ彼らは、あえて泥くさい現場に飛び込むのか――。現役PEプレーヤーたちが、その選択の背景と、知られざる必須スキルを語る。
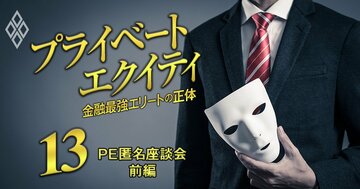
3メガバンクが、2025年3月期決算で軒並み最高益を更新した。国内の金利上昇で本業が復活し、政策保有株式の売却も利益を大きく押し上げた形だ。しかし米トランプ大統領の関税措置がもたらした為替・株式市場の混乱により、各行は26年3月期の業績見通しを急きょ引き下げる異例の事態に。絶好調の裏で高まる先行き不透明感とリスクを詳報する。

4月24日、群馬銀行と第四北越フィナンシャルグループが経営統合の基本合意を発表した。従来の“救済型”とは一線を画す、“成長”を志向した異例の地銀再編である。業績が堅調で地元シェアの大きな地銀同士がなぜ越境統合に踏み切ったのか。その内幕と狙いに迫る。

#12
中小企業との資本提携やM&Aに特化し、2021年に設立された新興ファンド、マラトンキャピタルパートナーズ。総額113億円の1号ファンドに続き、2号ファンドでは340億円もの資金調達に成功。創業からわずか4年で急成長を遂げている。だが一方で、同社の投資手法に業界内では、中小企業を安く買いたたく“転売ビジネス”との批判もくすぶる。小野俊法代表に、一部批判に対する見解と今後の展望を聞いた。

#11
新興のスモールキャップPEファンド、マラトンキャピタルパートナーズが、外資系大手に匹敵する異例の高報酬制度を導入していることがダイヤモンド編集部の取材で分かった。マラトンの職位別給与レンジを実額で初公開するとともに、潤沢なキャリー(成功報酬)を生む仕組みと、現場メンバーに手厚く還元される配分制度の全容を明かす。
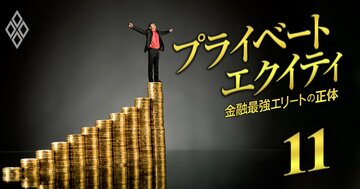
4月14日、金融セクターに特化した投資ファンド、ありあけキャピタルが、滋賀銀行株を大量保有していることが明らかになった。千葉銀行と千葉興業銀行の統合協議を後押しし、地銀再編の“仕掛け人”として注目を集める同ファンドが、次に照準を定めたのが滋賀銀行だ。その真意はどこにあるのか。大量保有の判明後、田中克典代表や周辺関係者への取材を通じて、狙いの核心に迫る。

地銀再編の動きが加速する中、同一県内での合併として一足早く注目されたのが、5カ月前の福井銀行の決断だ。2024年11月、福邦銀行との合併に際し、行名を「福井銀行」に一本化すると発表。26年5月には「福邦銀行」の名が姿を消す。なぜその決断が可能だったのか。福邦銀行側の反発はなかったのか。長谷川英一頭取に、合併や行名一本化の合理性、福邦銀行を説得した経緯について聞いた。

#7
プライベートエクイティ(PE)ファンドのIPO(新規株式公開)銘柄は投資家から敬遠されがちだが、その株価パフォーマンスは一様ではない。そこで、2015年以降に上場したPE銘柄を分析し、株価騰落率のワーストランキングを作成した。その結果、株価パフォーマンスの明暗がくっきりと分かれ、上場後の企業成長に対する姿勢の違いが浮き彫りとなった。

3月28日、千葉銀行が千葉興業銀行の株式19.9%取得を公表した。両行は将来的な経営統合を視野に協議を進める。この流れをけん引したのが、投資ファンド「ありあけキャピタル」だ。同社が22年に千葉興銀への投資を開始し、このタイミングで千葉銀行に株式を売却した背景は何か。田中克典代表が問題意識を持っていた千葉興銀の課題や、1年3カ月前に千葉興銀に提示した改革案、今年3月に株式売却に至った経緯について詳述する。

2024年の株主総会で株主賛成率を急回復させたのが、京都銀行を傘下に持つ京都フィナンシャルグループ(FG)の土井伸宏社長だ。だが、株主賛成率の大幅アップには、機関投資家による杜撰(ずさん)な投票も影響した疑いがあることがダイヤモンド編集部の取材で判明した。決算資料の数字さえも確認せずに取締役選任の賛否を判断する、機関投資家の怠慢ぶりを詳報する。

#20
PBRが低く割安な傾向にあるのが、不動産含み益を多く抱える不動産リッチ企業だ。実は、不動産含み益を反映した修正PBRを算出すると、見た目のPBRよりも割安であることが分かる。卸売業界の80社を対象に、不動産含み益を反映した修正PBRが低い上場企業ランキングをお届けする。

#18
PBRが低く割安な傾向にあるのが、不動産含み益を多く抱える不動産リッチ企業だ。実は、不動産含み益を反映した修正PBRを算出すると、見た目のPBRよりも割安であることが分かる。鉄鋼・非鉄・エネルギー資源業界の24社を対象に、不動産含み益を反映した修正PBRが低い上場企業ランキングをお届けする。
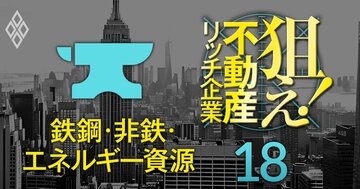
2月18日、りそなホールディングス(HD)のPBR(株価純資産倍率)が1倍を上回った。銀行株は低PBR銘柄の代表格だが、りそなHDは2024年11月14日、PBR1倍超に浮上。25年2月21日時点で、みずほフィナンシャルグループと三井住友フィナンシャルグループのPBRを超えた。りそなHDの南昌宏社長を直撃し、PBRについての考え、根底にある経営戦略や業績、今後の地域金融機関との提携策について聞いた。

#16
PBRが低く割安な傾向にあるのが、不動産含み益を多く抱える不動産リッチ企業だ。実は、不動産含み益を反映した修正PBRを算出すると、見た目のPBRよりも割安であることが分かる。電機・精密業界の38社を対象に、不動産含み益を反映した修正PBRが低い上場企業ランキングをお届けする。
