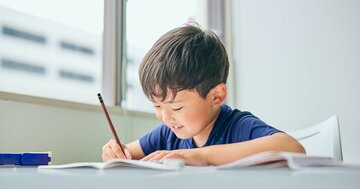川村秀憲
生成AIのせいで「子どもが自力で宿題をしなくなる」と恐れる大人に欠けている視点
人工知能(AI)の研究者であり、北海道大学大学院 情報科学研究院の教授を務める川村秀憲氏の書籍『10年後のハローワーク』(アスコム)から、要点を一部抜粋してお届けします。今回のテーマは「教育の未来」。親や教師の中には、ChatGPTなどの生成AIが普及することで、「子どもが自力で宿題をしなくなる」「出力結果のコピペなど、ズルをするようになる」と危惧する人もいるでしょう。そうした人たちに欠けている視点とは――。

外食業界で「AI・ロボットに代替される店員」と「しぶとく生き残る店員」の決定的な違い
人工知能(AI)の研究者であり、北海道大学大学院 情報科学研究院の教授を務める川村秀憲氏の書籍『10年後のハローワーク』(アスコム)から、要点を一部抜粋してお届けします。今回のテーマは、飲食業界をはじめとする「接客業の未来」。外食産業の現場では、注文をタブレットやスマホで行ったり、配膳をロボットが担ったりするケースが増えてきました。そうした中で、今後も生き残れるのは、どんな人材なのでしょうか――。

「公務員」はAIに仕事を奪われる?それとも生き残る?AI研究者の意外な予測結果とは
人工知能(AI)の研究者であり、北海道大学大学院 情報科学研究院の教授を務める川村秀憲氏の書籍『10年後のハローワーク』(アスコム)から、要点を一部抜粋してお届けします。今回のテーマは「公務員の未来」。「行政手続きのデジタル化」などの領域において、日本は他の先進国に遅れを取っています。旧態依然としたイメージが根強い公務員ですが、その仕事の在り方は今後どう変わっていくのでしょうか――。

「パン屋さん」「お花屋さん」になりたい子どもが、ビジネスで“将来有望”と言えるワケ
人工知能(AI)の研究者であり、北海道大学大学院 情報科学研究院の教授を務める川村秀憲氏の書籍『10年後のハローワーク』(アスコム)から、要点を一部抜粋してお届けします。今回のテーマは「サービス業の未来」。子どもの頃に「将来はパン屋さんになりたい」「お花屋さんになりたい」と思っても、時とともに夢が変わっていく人も多いでしょう。ですが川村氏は、そうした仕事はAI時代の到来後も淘汰されず、引き続き価値を発揮すると予測します。その理由とは――。

金融・保険業界の仕事は「AIに代替される」可能性大!AI研究者が警鐘を鳴らす理由とは
人工知能(AI)の研究者であり、北海道大学大学院 情報科学研究院の教授を務める川村秀憲氏の書籍『10年後のハローワーク』(アスコム)から、要点を一部抜粋してお届けします。今回のテーマは「金融・保険業界の未来」。これらの業界は安定しているイメージがあり、就職・転職における人気度も高いものの、川村氏は「AIによる代替が起こる」と警鐘を鳴らします。その理由とは――。

「商社マン」はAI時代が到来しても生き残る!AI研究者が太鼓判を押す納得の理由
人工知能(AI)の研究者であり、北海道大学大学院 情報科学研究院の教授を務める川村秀憲氏の書籍『10年後のハローワーク』(アスコム)から、要点を一部抜粋してお届けします。今回のテーマは「商社マンの未来」。世界のあちこちからモノを調達し、あちこちに販売して利益を得る「商社」の働き方は、AI・ロボットの活用がさらに進む10年後にどうなっているのでしょうか――。

コンサル会社で「AIに淘汰される人・生き残る人」の決定的な差、10年以内になくなる通過儀礼とは?
人工知能(AI)の研究者であり、北海道大学大学院 情報科学研究院の教授を務める川村秀憲氏の書籍『10年後のハローワーク』(アスコム)から、要点を一部抜粋してお届けします。今回のテーマは「コンサルティング会社の未来」。顧客企業の経営やIT活用などを支援することで、高給を得ているコンサルの仕事は、AI・ロボットの活用がさらに進む10年後にどうなっているのでしょうか――。

製造現場で働く「ブルーカラー社員」はAI・ロボットに仕事を奪われる?研究者の予測結果は…
人工知能(AI)の研究者であり、北海道大学大学院 情報科学研究院の教授を務める川村秀憲氏の書籍『10年後のハローワーク』(アスコム)から、要点を一部抜粋してお届けします。今回のテーマは「ブルーカラーの未来」。組立作業員や溶接工など、メーカーの工場で製造に携わっている人々は、AI・ロボットの活用がさらに進む10年後にどうなっているのでしょうか――。

「いい大学・会社に入りなさい」と教えられ、素直に勉強した子は10年後どうなる?【AI研究者が予測】
人工知能(AI)の研究者であり、北海道大学大学院 情報科学研究院の教授を務める川村秀憲氏の書籍『10年後のハローワーク』(アスコム)から、要点を一部抜粋してお届けします。今回のテーマは「10年後の子どもたち」。従来型の価値観のもと、親から「しっかり勉強して、いい大学、いい会社に入りなさい」と教えられた子は、10年後にどうなっているのでしょうか――。