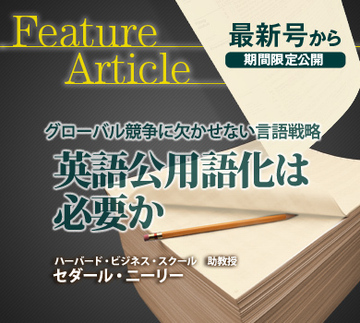幸福計算からGDPへ
この問題に関する説明は、イギリスの哲学者ジェレミー・ベンサムから始まる。彼は1781年、「行為」がどの程度の幸せを生むかによって、その行為の有用性を評価するという、「功利の哲学」をまとめ上げた。当時は啓蒙主義の時代で、思想家たちは宗教に基づく規範を合理的で科学的な意思決定と生活の指針へと置き換えることを目指していた。
ベンサムは、12の苦痛(感覚の苦痛、不適応による苦痛など)と14の喜び(友好の喜び、富の喜びなど)を比較することで、あらゆる行為について、ある種の幸福計算を行うことを提唱した。
功利という基本的アイデアは高く評価されたものの、ベンサムのアプローチはあまり評価されなかった。喜びと苦痛を1人ひとり比較できるように計算するのは、あまりに困難で煩雑であったためである。
功利の概念を最も熱心に採用していた経済学者たちは、これに代えて、人間のニーズと願望を目に見える形で表現するという方法に注目するようになった。それは「どれほどのお金を支払う意思があるか」である。
この取り組みは1930年代、厚生経済学を純粋に数学的な用語で説明するという、経済学者ポール・サミュエルソンの試みによって頂点に達した。これとほぼ時を同じくして、アメリカの2人の経済学者サイモン・クズネッツとイギリスのリチャード・ストーンが、GNPとGDPの基となる国民経済計算の体系を構築しつつあった。
彼らはそれほど功利に関心があったわけではなく、財政危機と戦争のさなかにおける、政策決定者による国民経済の管理に役立てることが主な目的であった。
しかし、これは単純明快な測定指標であり、支出パターンがすべてを明らかにするという経済学者の信念に加え、高まる経済学者の影響力と権威が相まって、大きな影響力を及ぼした。40年代には、IMF(国際通貨基金)と世界銀行が新設され、それらによって経済成長の主要指標としてGNPが採用され、年を経るなかで「成功」と「幸福」という、より深い含意を持つようになった。
短期的な経済変動の測定という当初の目的に関しては、近い将来、GDPが別のものに取って代わられるとは考えられない。むしろその地位をより確固たるものとするかもしれない。アメリカのFRB(連邦準備制度理事会)や各国の中央銀行では、危機の時期にはインフレ率よりもGDP成長率に注目すべきではないかという議論が広く行われているほどである。
しかし、短期的な上昇や下降という問題の先へ進むと、話は複雑さを増す。ロバート・ケネディは68年の大統領選挙戦の際の遊説で、こう述べている。
「わが国のGNPは(中略)大気汚染やタバコの広告、幹線道路から死体を取り除くための救急車を計算に入れています。自宅の扉や監獄を破られないための特殊な鍵を計算に入れています。伐採された杉林や、都市が無秩序に拡大することで失われた貴重な自然を計算に入れています。(中略)しかし、我々の子どもたちの健康や教育の質、遊びの楽しさは含まれません」
当時、ケネディの批判はほとんど注目されなかった。その後になって有名になったが、それは当然そうなるべきものであった。GDPに対する主要な批判のほぼすべてを簡潔に言い表しているからである。
その批判は、以下の3つの大きな要点から成る。
1. GDPはそれ自体欠陥のある指標である。
2. 持続可能性や持続性を考慮に入れていない。
3. 進歩と発展の測定には別の指標のほうが優れている場合がある。
以下に、これらのポイントを詳しく見ていこう。