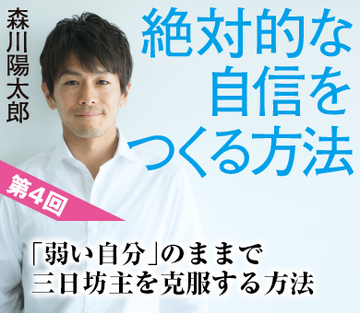『松下幸之助 きみならできる、必ずできる』
『松下幸之助 きみならできる、必ずできる』米倉誠一郎著(ミネルヴァ書房/2400円)
松下幸之助と言えば、“昭和の大経営者”である。平成元年に94歳で逝ったときには、一つの時代が終わったと感じられたものだ。その幸之助翁を、平成の終わりに振り返るとどのように見えるのか。
よく知られている通り、幸之助翁は学歴がなく、身体が弱く、家が貧しかった。ちょうど100年前の1918年に大阪で松下電気器具製作所(現パナソニック)を創業したが、今では想像できない苦労もあった。それでも、自らの経験から学び、生きた経営理論に展開することができる人だった。
俗に言えば、“叩(たた)き上げの経営者”だが、そんな存在が希少になった当世では、深々と「お辞儀をする幸之助」の写真(本書9ページ)がなんと美しく見えることか。
著者の米倉誠一郎氏は、古い時代の成功譚を今風に解説してくれる。新製品を多く生み出したわけではない。“マネシタ電器”と揶揄(やゆ)されても、消費者が望む製品を送り出してきた。プロダクト・アウトではなく、マーケット・インであった。プロセス・イノベーションによって、新しい市場を開拓するのが同社のお家芸だった。
幸之助翁は、部下を叱り、おだてるのがうまかった。そもそも、出来たての会社に最初から優秀な人材が集まるはずもない。本書の副題も、部下に大事を託した際の「殺し文句」の一つである。
旧松下電器産業の特色とされた事業部制は、経営判断の迅速化や外部取引コストの削減よりも経営者の育成に主眼が置かれていた。叩き上げと学卒者をバランスよく使い、育てる会社であった。
後年、幸之助翁は“経営の神様”と持ち上げられてからの人生が長かった。故に、従来の研究では「水道哲学(すいどうてつがく)」などの精神面や、社会貢献事業などが強調された。しかるに人間・松下幸之助は多くの矛盾を抱えていた。引退後の経営への関与は、褒められたものではなかったし、本書には愛人が存在したことも描かれている。
棺(かん)を蓋(おお)いて事定まる。一時代を経て、初めて浮かび上がる真実もあるということか。時代が遠くなってからこそ、学べる点があるとも言える。その問題意識は、明治から昭和初期の経営者群像を活写した米倉氏の近著『イノベーターたちの日本史』(東洋経済新報社)にも共通している。
今年は創業100周年。グローバル総合家電企業のパナソニックは、いろんな意味で創業者を乗り越えるべき時期であろう。今後は、自動車部品など企業向けニーズを増やすというが、消費者向けニーズを巧みに捉えてきたDNAにも、期待したいところである。
(選・評/双日総合研究所チーフエコノミスト 吉崎達彦)