
江崎グリコの社訓は、創業者・江崎利一(1882年12月23日~1980年2月2日)が残した「七訓──創意工夫、積極果敢、不屈邁進、質実剛健、勤倹力行、協同一致、奉仕一貫」である。
その中でも「創意工夫」は、江崎の起業精神と成功を表す最も適当な言葉といえるだろう。
1954年12月3日号に掲載された、江崎本人による「グリコで成功するまで」という手記からも、「人と違うことをやる」「とことん考え抜く」といった姿勢がいかに大事かが伝わってくる。
自宅近く、有明海の浜辺のカキの加工小屋で、カキの煮汁を捨てている姿を目にした江崎は、「カキにはグリコーゲンが多く含まれている」という薬業界紙の記事を思い出す。薬種業を営んでいたからこその着想だが、その煮汁を譲り受けて、グリコーゲンを取り出す研究に取り組む。
苦労の末、滋養強壮に効くカキエキスの抽出に成功すると、江崎氏はそれを病人のための「薬」としてではなく、健康な人の「お菓子」として売り出すことを決める。「治療より予防」に目を向けた結果だという。
商品化についてのさまざまな工夫もすでに有名だ。先行する森永製菓のキャラメルに対抗し、目立つ赤い箱に、陸上選手のゴールシーンをモチーフにしたデザイン、森永の「滋養豊富 風味絶佳」とは一線を画す「一粒300メートル」という奇抜なキャッチコピー、「おまけ」のミニ玩具……などなど。記事の中でも江崎は「広告の効果を重視していた。そのためには、心理学の本まで勉強していた」と語っている。
販売戦略も大胆だ。当時“本業”としていたワインの瓶詰め販売で得た資金を投入して、いきなり大阪に進出。「石は高い所から低い所に転がせばいい」とばかりに、名門の三越百貨店に掛け合って店頭に置いてもらった。この三越に商品が並んだ1922年2月11日は、江崎グリコの創立記念日に制定されている。
東京進出については、これからというときに戦争が始まって、お菓子は統制品となってしまい、工場も空襲で焼けてしまった。大阪工場、東京工場が再建されたのは1951年で、この記事が掲載されたのはそれから3年目のこと。その後も、多くの創意工夫に満ちた商品を世に送り出していった。(敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)
カキの煮汁から取った栄養剤
病人でなく健康人を相手に
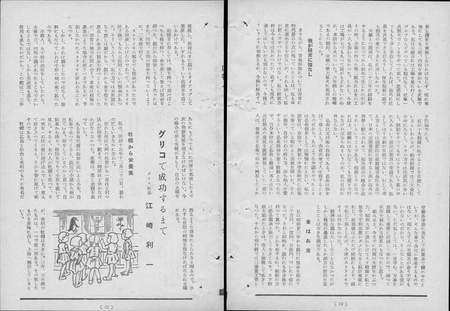 1954年12月3日号より
1954年12月3日号より
私は、明治15(1882)年12月23日、暮れの忙しいさなかに生まれた。
生まれた所は九州の佐賀から一里ほど引っ込んだ田舎で、駅まで2時間ほど歩かなければならなかった。家業は、薬と食糧を扱っていた。
ある日、有明湾の海岸に近い所を自転車で走ってくると、浜辺の小屋から煙が出ている。何をしているのかと思って、自転車から降り、堤防を下りて小屋をのぞいてみた。すると、女の人がカキを割って、その身を一石くらいの釜に投げ込んでいた。煮えて浮き上がってくると、それを簀(すのこ)に広げて乾(ほ)すのである。
カキは広島と仙台と有明のものが有名だが、有明のカキは大きい。3年、5年たったものは、一つで皿いっぱいある。その乾したものを長崎に出し、上海へ輸出しているという。
有明地方は、大都会がないので、3割くらいしか売れず、残りは全部輸出されていたのである。
その話を聞いているうちに、ある考えが浮かんだ。
前に家で取っている薬業の新聞で、牡蠣にグリコーゲンがあるという記事を見た覚えがあった。よし、これを利用すれば、面白いことができそうだ──。早速、捨てられるはずのカキの煮汁を、九州の大学の知り合いに分析してもらったところ、グリコーゲンが34%含まれていることが分かった。当時、三共から売り出していたグリコナー錠は40%であった。このグリコーゲンは精力のもとである。それに微量の銅も入っている。これは絶好の栄養剤になる。しかも廃棄物利用だ。これはいける──と思った。
早速栄養剤として売るつもりで準備を始めた。ところが、大学のある医者が言うには、
「栄養剤というものは病人を対象として売るものだ。ところが100人のうち、病人はせいぜい20人、あとの80人は健康な人間ばかりだ。同じ栄養物を売り出すなら、病人相手でなく、健康人を相手に商売すべきだ。薬でなく、それを食べていれば病気にかからない、というものを作った方がよい」
なるほどと思った私は、つくだ煮から、振りかけ粉まで研究し、結局、お菓子に落ち着いた。







