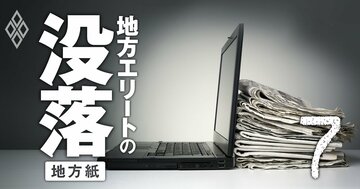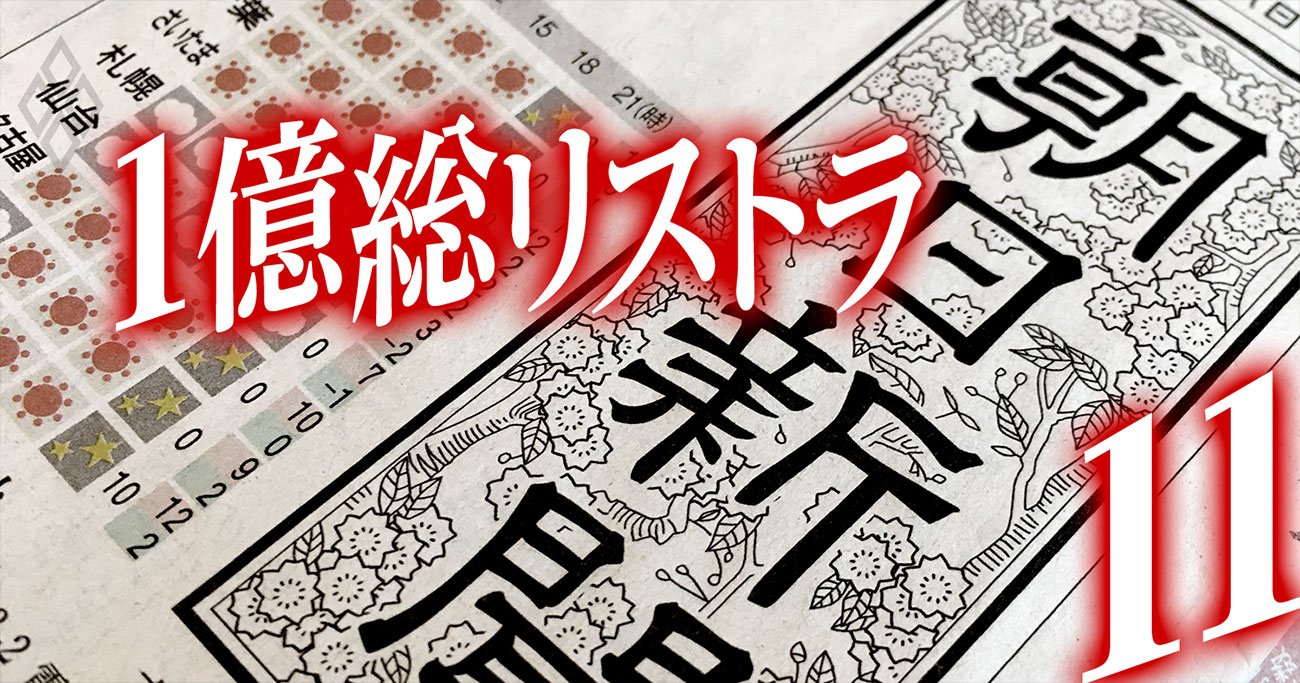 Photo by Masataka Tuchimoto
Photo by Masataka Tuchimoto
リーディングペーパーを自称する「朝日新聞」が1月、100人以上の応募を目標に希望退職者を募集した。「産経新聞」「毎日新聞」、共同通信などでも人員整理が加速している。特集『1億総リストラ』(全14回)の#11は、大手メディアの内情をリポートする。(ダイヤモンド編集部 土本匡孝)
産経、毎日、共同通信そして朝日
大手メディアに人員整理の波
「朝日新聞」は2020年度(21年3月期)上半期決算で419億円もの純損失を計上し、渡辺雅隆社長が引責辞任を表明した。
そして21年1月、希望退職者の募集を開始。目標は100人以上の応募で、45歳以上を対象に3月22日まで受け付けた。これも含めて23年度までに計300人規模で募るようだ。
朝日以外にも、「産経新聞」と「毎日新聞」が19年に、それぞれ希望退職者を募集した。共同通信でも20年、自然減や採用抑制で今後正職員を300人規模で減らす方針が明らかになった。メディアで人員整理の波が止まらない理由は明白だ。