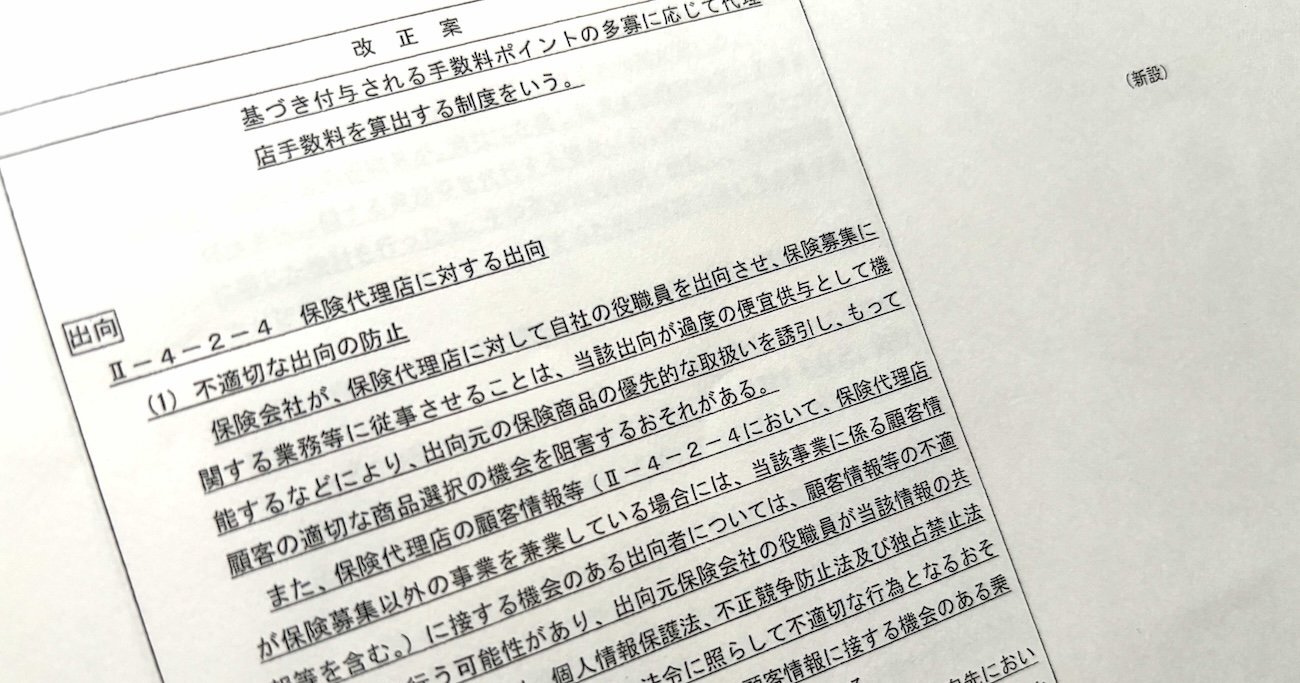Photo:Diamond
Photo:Diamond
東京五輪だけが「聖域」扱いされる違和感
「オリパラってやっぱりサイコー!」
「パンケーキ首相、反対派の声に屈することなく開催してくれてありがとう!」
そんな「オリンピック大成功」からの解散総選挙で勝利、そして自民党総裁選も無投票再選…という菅義偉首相が描いていた「続投シナリオ」がここにきて狂ってしまった。
まず、東京都に「リバウンド」の兆しが見えてきた。報道によれば、4回目の緊急事態宣言が発出する方針だという。ただ、それ以上に菅政権にとって大打撃なのは、先週末の東京都議会議選で、自民党が事実上の「惨敗」をしてしまったことだろう。
負けた理由はさまざまあるが、東京五輪に結びつける声も少なくない。慌てふためいた政府は、これまで頑なに「有観客」にこだわってきたのに、急に国民に媚びるように「無観客」を匂わせ始めた。
この「平和の祭典」とやらは、中国共産党の記念式典や、北朝鮮の軍事パレードと同じ性格の、「政権の支持率アップを目指す政治イベント」に過ぎなかった、という事実をあらためて浮き彫りにした形だ。
という話をすると、「開催に向けて一致団結をしなくてはいけない大事の時に、おかしな言いがかりをつけるな!この反日左翼め」と激昂される方もいるかもしれない。
というのも、安倍晋三前首相の月刊誌『Hanada』での発言があったからだ。安倍氏は、東京五輪に反対しているのは、野党や朝日新聞など、「一部から反日的ではないかと批判されている人たち」であって、「極めて政治的な意図」だと指摘した。これに対して「よく言ってくれた!」と拍手喝采している方もかなりいらっしゃるのだ。
断っておくが、筆者には特に政治的なイデオロギーはない。しかし、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」など各地で大規模イベントが中止に追い込まれている中で、東京五輪だけが「聖域」扱いされることには違和感しかない。
「アスリートは4年に一度に人生のすべてを懸けている」というが、アーティストも役者も人生のすべてを懸けてステージに臨んでいる。もっと言えば、五輪のために我慢を強いられている飲食業の人たちも、一世一代の夢を懸けて自分の店を経営しているのだ。
「五輪優遇」というと、それはIOCガー、経済的損失ガー、ともっともらしい言い訳を並べる人もいる。しかし、政府の成長戦略会議のメンバーでもあるデービッド・アトキンソン氏は、「朝日新聞」(6月22日)のインタビューで「五輪の経済効果や、中止した場合の損失が、1兆円だろうが5兆円だろうが、大した影響はありません」と述べている。たかだか1カ月弱のスポーツイベントで得られる経済効果など、日本のGDP全体の中で微々たるものだ。「五輪ができないと日本はおしまいだ」みたいな終末論が叫ばれる理由がわからない。
そのような「違和感」の中で特に筆者がモヤモヤしてしまうのは、「無観客だと世界に示しがつかない」というものだ。