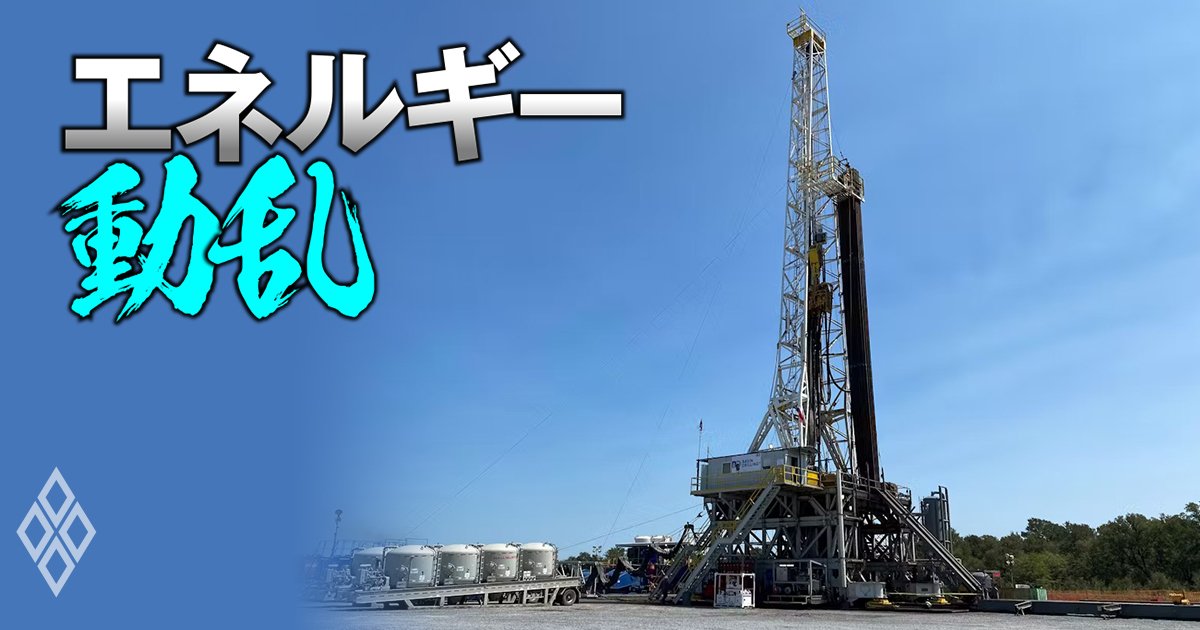大泉洋、柳楽優弥がW主演、劇団ひとりが脚本・監督の『浅草キッド』。ビートたけしの同名の自伝を元にしている。日本のネットフリックスが制作した最新のオリジナル作品で、12月9日から世界配信されている Photo:NETFLIX
大泉洋、柳楽優弥がW主演、劇団ひとりが脚本・監督の『浅草キッド』。ビートたけしの同名の自伝を元にしている。日本のネットフリックスが制作した最新のオリジナル作品で、12月9日から世界配信されている Photo:NETFLIX
コロナ禍の巣ごもり消費の中でも特に急成長したサービスの一つが、動画配信のNETFLIX(以下ネットフリックス)だ。日本市場への外資系参入はハードルが高いと言われる中で、なぜネットフリックスは日本で成功できたのだろうか?その理由を知る上で、カギとなる作品がある。
※この記事は『NETFLIX 戦略と流儀』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。
ネットフリックスが日本で普及したのは
「日本オリジナル作品」のおかげ
ネットフリックスは日本においてもテレビメディアを凌ぐ存在にのし上がった。そのカギを握ったのは日本オリジナル作品だった。日本はどこの国よりも、日本人に受け入れられる作品であることがヒットの絶対条件にある。ネットフリックスはどのようにして日本オリジナル作品を作り出していったのか。ここでは、日本オリジナル作品が作られた背景から、ネットフリックスが日本で成功することができた理由をひもといていこう。
日本におけるネットフリックス人気の火を付けたのは間違いなく、AV監督・村西とおるの半生を描いたドラマ『全裸監督』だ。2019年8月8日の『全裸監督』公開から約1カ月後に発表されたネットフリックスの日本の有料会員数は約300万人。話題作を見たいがために新たに加入した会員が増え、結果、ネットフリックスは日本上陸後、初めて会員数を明かしたという経緯からも明白だ。それだけ『全裸監督』のヒットは、日本でネットフリックスを定着させる意味でも大きかった。
 NETFLIXオリジナルドラマ『全裸監督』 Photo:NETFLIX
NETFLIXオリジナルドラマ『全裸監督』 Photo:NETFLIX
続く、2020年のコロナ禍の巣ごもり消費の中で起こった韓国ドラマ『愛の不時着』ブームへの布石も作ったと、そんな解釈もできる。「これが世界スタンダードのネットフリックスオリジナルドラマか」という驚きと満足した体験があったからこそ、ヒットの連鎖は生まれる。ネットフリックスブランドに対する信頼も増し、新たなファンも引き寄せたと言える。