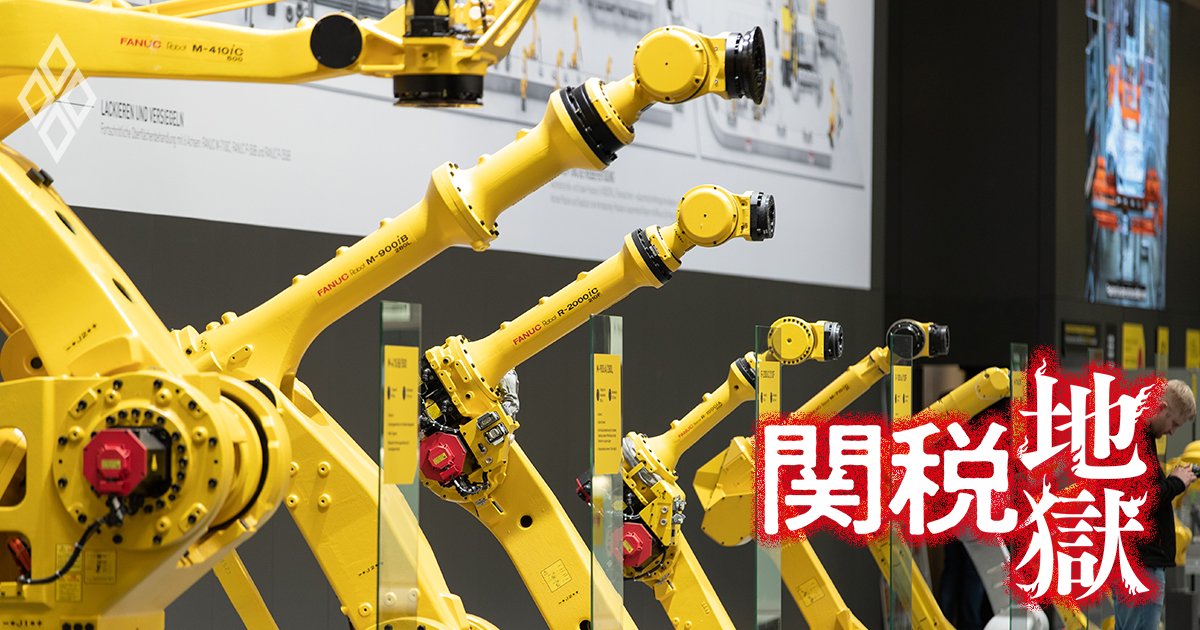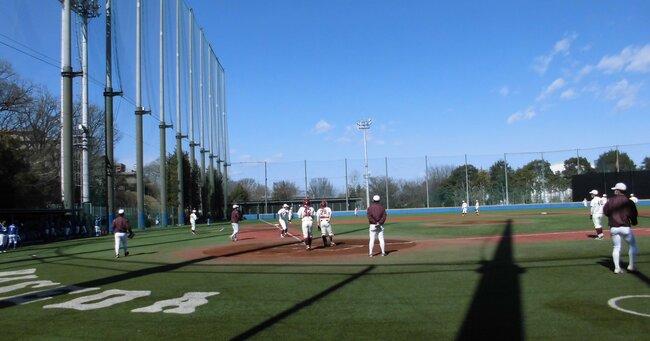 ノック練習をする早大野球部の選手たち 撮影:須藤靖貴
ノック練習をする早大野球部の選手たち 撮影:須藤靖貴
2020年秋季リーグ開幕を控えた8月のある日、小宮山監督が就任以来最大の「カミナリ」を落とした。これまで「我慢、我慢」を言い聞かせていたが、堪忍袋の緒が切れたのだ。小宮山はチームビルディングの難しさを感じながら、秋季リーグ開幕を迎える。(作家 須藤靖貴)
ある学年が1人もベンチ入りせず
その理由とは?
東京・西早稲田の居酒屋「源兵衛」。1926年の創業から令和の今まで、早稲田大教授や野球部関係者らが憩う。名物のシュウマイや特大のだし巻き玉子など、なんでもおいしいわけだが、熱心な野球部ファンの会話も極上の肴となった。
2020年秋季の明治戦を終えた翌日の月曜日。私は源兵衛の縄のれんをくぐった。マスクを外したり付けたりしながらビールを飲んでいると、隣席の会話が耳に飛びこんでくる。「明治戦、2年生がベンチ入りしてなかった。何かあったのかな」。ファンの女性である。春季スタメンに名を連ねていた2年生の名はなく、他の2年生部員もベンチから外れたことを看破したのだ。
話は秋季リーグ戦の前に戻る。
8月下旬。オープン戦の合間に1日のオフがあった。自由行動ではあるものの、部員は相応の過ごし方――身体を休めつつ気持ちの張りをたゆめない――をする。翌日は城西国際大に遠征。以降も東都リーグを中心とした強豪校との8試合を予定している。
その夜、小宮山監督の元に部員がケガをしたとの報が入った。自主練のやりすぎでのトラブルか、と眉を寄せたわけだが……。
2年生十数人が秋川渓谷に出かけて、そのうちの1人が岩場で滑って頭を打ったというのだった。
ケガが軽傷であることを確認して、小宮山は電話を切った。
緊急事態宣言の解除(5月25日)から3カ月たっているとはいえ、この状況で川遊びとは――。
春季リーグ戦の後、4年生幹部を呼びつけて「このままでは絶対に勝てないぞ」と叱咤した。膝詰めで話し合ったのは昨年にはなかったこと。4年生は1年の春からこれまで、優勝の経験がない。監督の激励に4年生たちは気持ちを寄せた。ベンチ入りできない4年生も「自分たちの代で優勝するんだ」との思いでグラウンドに立った。秋季開幕まで、タイトなスケジュールでオープン戦を組んでいる。高い緊張感を保ちながら、9月19日の秋季リーグ戦開幕に向かうのである。
その矢先だった。