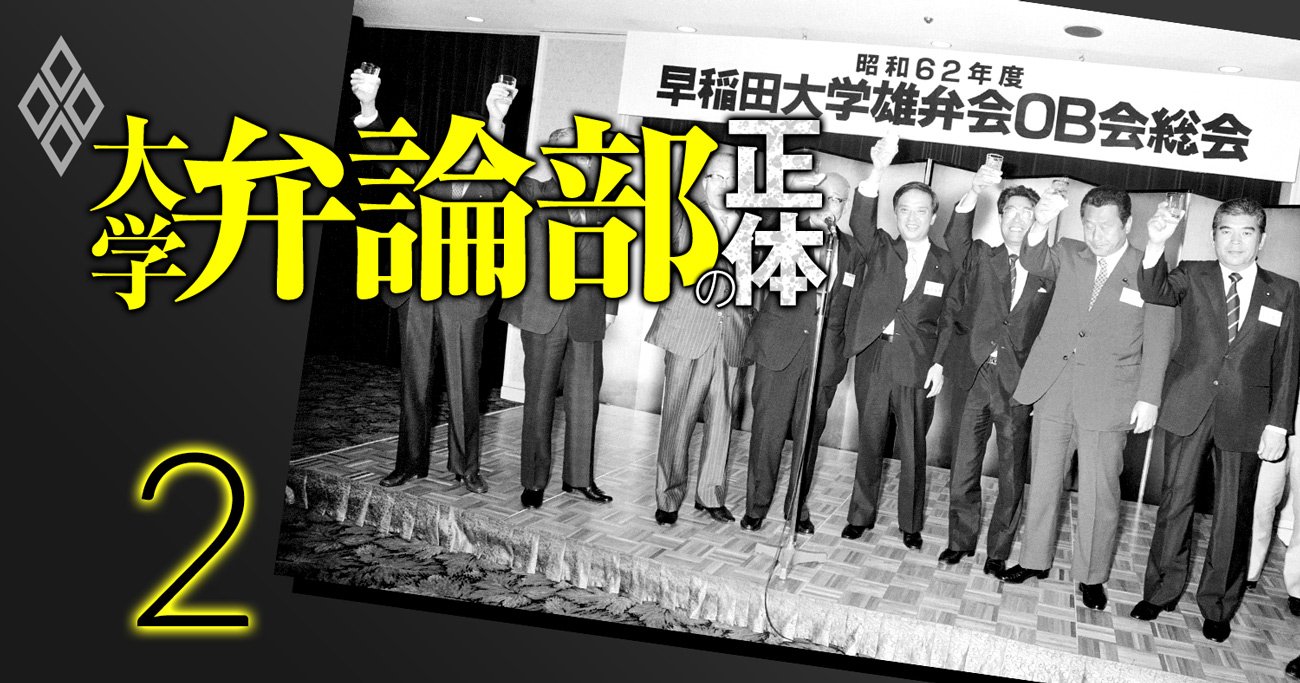 Photo:JIJI
Photo:JIJI
5人の首相を輩出した早稲田大学雄弁会は政治家への“登竜門”とされてきた。かつては政治家を目指す学生も多く集まり、激しい選挙活動や派閥抗争を繰り広げてきた。しかし、近年はその様相は一変し、選挙や派閥はほぼなくなった。特集『知られざるエリート人脈 大学弁論部の正体』(全10回)の#2では、雄弁会の歴史をひもとくとともに、名門弁論部で起きた地殻変動について解説する。(ダイヤモンド編集部副編集長 名古屋和希)
早大雄弁会はかつて「政治」の場
「選挙なし・派閥なし」路線へ
「政治や駆け引きの技術を学んだ」。早稲田大学雄弁会のあるOBはそう打ち明ける。その言葉が象徴するように、5人の首相を輩出した名門弁論部は、弁論活動よりも激しい派閥抗争や選挙戦に明け暮れているとのイメージが色濃い。
実際、それは1983年に出版された『早稲田大学雄弁会八十年史』にも見て取れる。67年卒業のOBによる当時の幹事長選挙を巡る手記を引用していこう。
第2回目総会は、ここ数年の間では1番激しい争いとなり、右派系は喫茶店ナポリ、左派系は茶房とジュリアンを根城に、時にはなぐり合いもある集票合戦となった。
双方の個人的行動は、数日禁止され、三々五々と下宿に泊りがけとなった。総会当日は、早稲田の左派団体が支援して雄弁会を乗っ取り、革命団体にするとの情報も流れ、“右”は金城庵、“左”は三朝庵に集結。ドンブリ飯を食べ、全員討ち入りのような気持ちで、8号館21教室へ向かった。
時あたかも、全学共闘会議(全共闘)が登場するなど学生運動が最も盛り上がりを見せていた時代でもある。世相を反映し、雄弁会の幹事長選挙でも左右が激しく対立していた。
そもそも雄弁会発足の契機は、田中正造による明治天皇への直訴でも知られる、足尾銅山鉱毒事件だ。事件の惨状を訴えるべく、演説会を開いた学生らが中心となり、02年に雄弁会は立ち上げられた。
発足の経緯からしても、雄弁会は政治・社会活動とは切っても切れない存在だったといえる。戦前には「赤(社会主義者)の巣窟」と見なされ、29(昭和4)年に雄弁会は解散に追い込まれている。
終戦後は、副総理を務めた自由民主党の緒方竹虎や、刺殺された日本社会党委員長の浅沼稲次郎ら雄弁会OBの政治家が活躍した。雄弁会も46年に再建され、左から右まで幅広い人士が集まり、弁論活動のみならず「部内の政治」が繰り広げられてきた。
時代は下り、87年に雄弁会出身では石橋湛山以来31年ぶり2人目となる竹下登氏が首相に就任。与野党幹部に雄弁会OBがずらりと並び、「雄弁会人脈」が喧伝された。雄弁会に対する、「政治ごっこ」批判も上がった。
実際のところ、冒頭のOBの発言のように、雄弁会では「部内政治」が活動の多くを占めてきたことは間違いない。しかし、近年の雄弁会の様相はそうしたイメージとは大きく異なる。選挙や派閥とは距離が置かれているのだ。
なぜ雄弁会から「政治」が消えたのか。実は、雄弁会ではこの30年、三つの派閥が鎬を削る「3派闘争」の時代を経て、何度も揺り戻しが生じている。次ページでは、関係者の証言や記念誌などの資料を基に雄弁会で起きた地殻変動について解説していく。







