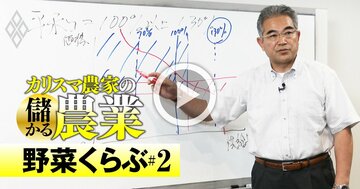自民党の農林部会の会長として、与党側から農協改革を取りまとめてくれた小泉進次郎議員(左)と筆者 Photo:SANKEI
自民党の農林部会の会長として、与党側から農協改革を取りまとめてくれた小泉進次郎議員(左)と筆者 Photo:SANKEI
「60年ぶりの大改革」と銘打たれた農協の改革。これは安倍政権が2013年に打ち出した日本再興戦略の中の「農林水産業を成長産業へ」との目標、つまり農政改革の大きな柱の一つだった。その過程では農協の強い反対に遭い、農林族といわれる議員や農林水産省も当初は改革に後ろ向きだった。それでも敢行し、最後は議員や官僚の後押しを得た改革を振り返る。(第99代内閣総理大臣/衆議院議員 菅 義偉)
農業が生き残っていくためにこそ
農協も全中も「改革」は必至
戦後、1600万人を超えていた農業従事者は、現在では約200万人にまで減り、平均年齢も67歳と高齢化が進んでいる。農政改革を掲げた13年時点で、20年前と比較した農業の総産出額は10.4兆円から8.4兆円へ減少しており、農業所得も4.6兆円から2.8兆円へと減少していた。
これでは若い世代が農業に希望を持てるわけがない。5年に1度計測される全国の耕作放棄地も、1995年の24万ヘクタールが15年には42万ヘクタール近くまで増加している。
本来、こうした苦境に直面する農家を支援すべき存在が農協だ。農協は、戦後の食糧難の時代に農地改革で生まれた農家の自立を支援するために結成された。そして各地の農協を統括し、指導や支援を行うのが、「全中(全国農業協同組合中央会)」と呼ばれる中央会制度だ。
戦後間もない頃、こうした制度が必要だったのは間違いない。だが年々社会の変化のスピードが速くなり、均一性より地域ごとの魅力を生かして付加価値を高める「攻める農業」への転換が求められる時代にあっては、農業が生き残っていくためにこそ、農協も全中も改革を免れることはできない。
農政改革には、個人的な思い入れもあった。農業が元気にならなければ、地方は元気にならない。農業で得られる所得を上げることで、若い人が農業を魅力ある成長産業と考え、次々に新規参入する。そして農業を日本の国力を支える柱の一つにしたい――。これが秋田の農家に長男として生まれた私の大きな目標でもあったためだ。
父の影響も大きかった。コメどころの秋田にありながら、父は「これからはコメを作るだけでは食っていけない」と考え、独自農法により出荷時期をずらしたイチゴの栽培に取り組んだ。付加価値の高い農産物に活路を見いだそうと考えたのだ。
そしてコメ作りからの転換に反対する地元農協とたもとを分かち、独自に「秋ノ宮いちご生産出荷組合」というイチゴ栽培の組合を結成した。農家の現状を見れば先見性があったといっていいだろう、父のこの経験こそが攻める農業であり、私自身の農政改革の原点にもなっているのである。
なぜ「コメでは食っていけない」のか。戦時中から、政府はコメ全量管理を原則として、政府が農家からコメを買い上げる価格を引き上げてきた。そのためコメを作っていれば、ある程度コストがかかっても農業を続けられる体制になっていた。
しかし、コメ生産量の調整は減反政策を生んだ。71年に本格的に始まった減反政策は、国が定めた毎年の生産目標を自治体が農家に割り当てて生産量を調整するもので、コメの生産過剰と価格暴落を防ぐ目的があった。
だがこれも、2000年代以降は役割を終えつつあった。コメの消費量が減り、生産コストが上がる中で農家を稲作に縛り付けるのはおかしい。また、減反に参加するかどうかはコメ農家が選択すべきであり、国や自治体が「たくさん作るな」と指示する性質のものでもない。国内でコメが余るなら、海外に売ることだって考えていいはずだ。
何より問題なのは、こうした政策が、結果として地域の特色を生かした農業や各農家の創意工夫を阻害していた点であろう。そこで安倍官邸は成長戦略の一環として、13年5月、「農林水産業・地域の活力創造本部」を設置した。減反の見直し、農家の規模拡大や土地の集約、若手の新規参入を促す仕組みづくりなどの本格的な検討を開始したのである。
予想通り、農協を含む農業団体は減反の見直しなどの政策転換に強く反対した。農家や農業団体は自民党の支持基盤であり、選挙区に多く農家を抱える候補者もこうした改革には慎重な姿勢を取る傾向がある。また、農協は組織力を使って政府の農政改革に影響を及ぼしてきた。これらが農政改革を大胆に進められない理由でもあったのだ。